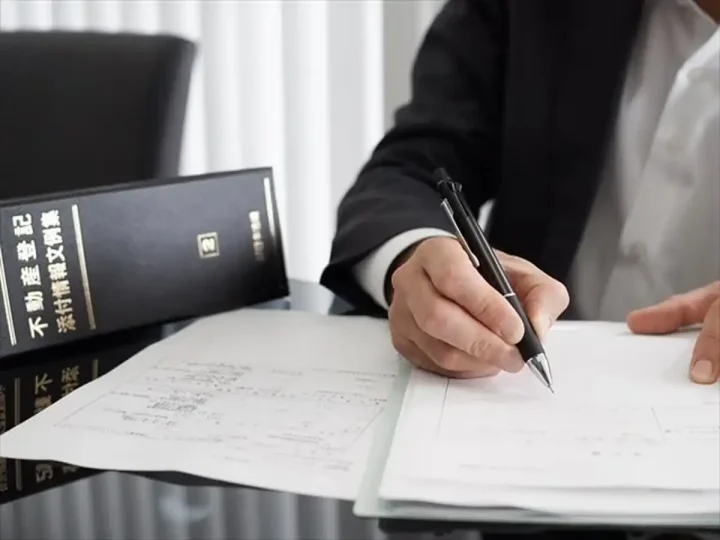【司法書士が読み解く】成年後見制度見直し中間試案:あなたの知るべき重要点

はじめに
「成年後見制度って、一度始まったら終わりがないんでしょ?」
そう思って、ご自身やご家族の万が一に備えることをためらっていませんか? 2025年現在、超高齢社会が進む日本で、認知症などで判断能力が不十分になる方は増え続けています。そんな中、大切な財産を守り、ご本人の意思を尊重した生活を支えるための「成年後見制度」は、私たちにとって非常に身近な存在になりつつあります。しかし、残念ながら現行の制度には多くの課題が指摘されており、その利用は伸び悩んでいるのが実情です。
しかし、今、この成年後見制度が大きく変わろうとしています。法務省の法制審議会は、制度の抜本的な見直しに向けた「民法(成年後見等関係)等の改正に関する中間試案」を公表し、現在、国民からの意見(パブリックコメント)を募集しています。
今回は、この中間試案の主要なポイントを司法書士の視点から分かりやすく解説し、制度の未来について考察します。
成年後見制度、なぜ今見直しが必要なのか? 現行制度の課題
現行の成年後見制度は、判断能力が不十分な方を保護するために重要な役割を担ってきましたが、社会の変化とともに様々な課題が浮き彫りになってきました。
主な課題は以下の点に集約されます。
- 「終身制」という心理的障壁: 一度後見等が開始されると、原則として本人の判断能力が回復しない限り終了できないため、「一度始まったら抜け出せない」「一生涯続くもの」というイメージが強く、制度利用をためらう大きな要因となっていました。
- 類型(後見・保佐・補助)の硬直性: 本人の判断能力の程度に応じて「後見」「保佐」「補助」の3類型に分かれていますが、一度類型が決まると、その後の本人の状態の変化(例えば、症状の改善や悪化)に対応しきれず、柔軟性に欠けるという指摘がありました。
- 本人の自己決定権の限界: 障害者権利条約の批准など、国際的な潮流として本人の自己決定権を最大限尊重することが求められています。しかし、現行制度の運用においては、本人の意思が十分に反映されにくい場面があるという批判もありました。
- 後見人等の選任・交代の難しさ: 親族が後見人になることに抵抗があったり、専門職への依頼費用が懸念されたりすることも利用のハードルとなっていました。また、一度選任された後見人等の交代が容易ではない点も課題でした。
これらの課題は、認知症高齢者の増加という社会状況にもかかわらず、制度の利用率が伸び悩む一因となっていました。
中間試案の主要ポイントを司法書士が徹底解説!
今回の見直しの中間試案では、これらの課題を克服し、より使いやすく、本人の意思を尊重する制度を目指す画期的な内容が多数盛り込まれています。
1.「期間設定・更新制」の導入(最大の目玉!)
これが、今回の見直しで最も注目され、利用者にとって大きなメリットとなるポイントです。
現行の「終身制」を根本的に改め、成年後見等の開始に際して期間を定めることが可能になり、期間満了後も必要に応じて更新できる制度が提案されています。具体的な仕組みとしては、以下のような点が検討されています。
- 期間の定め: 家庭裁判所が後見等を開始する際に、例えば「5年間」といった形で期間を定めることを可能とします。
- 期間満了後の対応: 期間が満了する際に、改めて本人の状況を確認し、後見等の必要性が継続している場合は更新手続きを行う形が想定されています。本人の判断能力が回復したり、他の支援で十分になったりした場合は、そこで終了することも可能になります。
- 「出口」の新設: これにより、一度制度を利用したら原則終了できないという心理的負担が軽減され、利用へのハードルが大きく下がることが期待されます。例えば、「一時的に判断能力が低下している状況だが、数年後には回復する可能性がある」といったケースでも、より利用しやすくなるでしょう。
2.類型の柔軟化/「特定行為に関する支援」の検討
現行の「後見」「保佐」「補助」の3類型は維持しつつ、よりきめ細やかな支援を可能にするための柔軟化が図られます。
- 後見・保佐の対象範囲の見直し: 例えば、これまで後見の対象とされていた「判断能力を欠く常況にある者」であっても、保佐や補助の制度を利用できるようにする(ただし、その場合は本人の同意を必須とする)といった案が検討されています。
- 特定の法律行為のみを支援: 本人のニーズに応じて、特定の法律行為のみを支援するなど、さらに柔軟な制度の導入も検討されています。例えば、「遺産分割協議のためだけ後見人を付けたい」「所有する不動産の売却手続きのためだけ保佐人の同意がほしい」といった具体的な目的に絞った支援が可能になるかもしれません。これにより、本人の残された判断能力を最大限に活かし、自己決定権を尊重した利用が期待されます。
3.本人の自己決定権の尊重の強化
障害者権利条約の理念を反映し、本人の意思を最大限に尊重する方向性が示されています。
- 制度開始要件における本人の同意の重視: これまで本人の同意が不要であった類型(後見、保佐)についても、本人の同意を制度開始の要件とすることを原則とすることが検討されています(ただし、同意ができない場合や、本人の利益が著しく害される恐れがある場合は例外規定を設ける)。
- 後見人等の職務における本人の意思の反映: 後見人等(成年後見人、保佐人、補助人)が職務を行う際、ご本人の意思や心情をさらに尊重するよう、具体的な規定の整備が検討されています。例えば、どのような介護を受けたいか、どの施設に入居したいかなど、身上監護に関する本人の意思をより重視する方向性です。
4.後見人等の交代の円滑化
現状では、一度選任された後見人等が不適切であったり、職務を継続できなくなったりした場合でも、その交代は容易ではありませんでした。試案では、本人の利益のために特に必要な場合に、よりスムーズに後見人等を交代できるような規定の整備も検討されています。これにより、後見人等による不適切な行為が発覚した場合の対応が迅速に行えるようになり、本人の保護が強化されます。
5.報酬制度の透明化
成年後見人等の報酬について、家庭裁判所が報酬を決定する際に、行われた事務の内容や本人の資産状況、地域の実情などが考慮要素であることを明確にする案も検討されています。これにより、報酬決定の透明性が高まり、利用者の理解と信頼を得やすくなることが期待されます。
司法書士から見た、改正の光と影
今回の見直しは、成年後見制度を大きく前進させるものとして大いに期待されています。
【光】期待されるメリット
- 制度の利用促進と普及: 「期間設定・更新制」により、心理的ハードルが下がり、これまで利用をためらっていた層が制度を検討しやすくなるでしょう。
- 本人の自己決定権の尊重強化: 同意の原則化や類型の柔軟化により、本人の意思がより制度に反映されやすくなります。
- 多様化する社会のニーズへの対応力強化: 医療や介護、財産管理など、複雑化・多様化する高齢者のニーズに対して、より柔軟かつ適切な支援が提供できるようになります。
- 「気軽に相談・利用できる」制度への変革: これまでの「重い」「終わりがない」というイメージが刷新され、より身近な制度として認知されることが期待されます。
【影】考えられる課題・懸念点
- 「期間設定・更新」に伴う事務負担の増加: 家庭裁判所や、後見人等、そして本人や親族にとって、期間満了時の手続きや、本人の判断能力の再評価、後見の必要性継続の判断が新たな負担となる可能性があります。
- 専門職後見人の育成・確保: 制度の利用が増加すれば、それに伴い専門職後見人の需要も高まります。質の高い後見人を安定的に供給するための育成や確保が喫緊の課題となるでしょう。
- 制度が複雑化する可能性: 柔軟化はメリットである一方で、制度の仕組みがより複雑になり、一般の人が理解しにくくなるという側面も持ち合わせています。
司法書士が果たすべき役割と未来
今回の見直しは、私たち司法書士の業務にも大きな影響を与えるでしょう。
制度がより柔軟になり、利用しやすくなることで、成年後見制度に関するご相談が増えることが予想されます。司法書士は、引き続き申立て支援、成年後見人等としての職務、任意後見契約の支援などを通じて、市民の皆様の財産と生活を守る役割を担っていきます。
特に、新しい「期間設定・更新制」の導入に伴い、期間満了時の手続きや、本人の状況に応じた適切な対応について、専門家としての助言が不可欠になります。また、類型が柔軟化すれば、どの類型が本人にとって最適なのか、より専門的な判断が求められる場面も増えるでしょう。
私たちは、常に最新の制度改正の動向を把握し、依頼者の皆様に最適な選択肢を提案できるよう、専門知識の研鑽に努めてまいります。
まとめ
法務省の法制審議会で議論されている成年後見制度の見直しは、より本人の意思を尊重し、社会のニーズに即した制度へと発展させるための重要な一歩です。特に「期間設定・更新制」の導入は、制度利用のハードルを下げ、多くの方が安心して利用できる未来を拓く可能性を秘めています。
成年後見制度は、ご自身や大切なご家族の将来を守るための大切な備えです。この度の見直しによって、より多くの人が安心して利用できる制度へと進化することが期待されます。
成年後見制度についてご不安なことやご不明な点がございましたら、いつでもお気軽にご相談ください。私たち司法書士は、あなたの「もしも」の時に寄り添い、最適なサポートを提供いたします。
◇ 当サイトの情報は執筆当時の法令に基づく一般論であり、個別の事案には直接適用できません。
◇ 法律や情報は更新されることがあるため、専門家の確認を推奨します。
◇ 当事務所は情報の正確性を保証せず、損害が生じた場合も責任を負いません。
◇ 情報やURLは予告なく変更・削除されることがあるため、必要に応じて他の情報源もご活用ください。
この記事を書いた人

司法書士・行政書士 和田正俊事務所 代表和田 正俊(Wada Masatoshi)
- 滋賀県司法書士会所属 登録番号 滋賀第441号
- 簡裁訴訟代理関係業務 認定番号 第1112169号
- 滋賀県行政書士会所属
登録番号 第13251836号会員番号 第1220号 - 公益社団法人 成年後見センター・リーガルサポート滋賀支部所属
会員番号 第6509213号
後見人候補者名簿 及び 後見監督人候補者名簿 搭載 - 法テラス契約司法書士
- 近畿司法書士会連合会災害相談員
法改正・時事情報に関連する記事
令和8年4月施行・住所変更登記の義務化とは?~改正不動産登記法のポイントと実務対応~
2025年12月4日
【2025年改正解説】供託金払渡し時の印鑑証明書添付義務が緩和されました
2025年12月3日
紙からデジタルへ!「電子署名」は実印を超える?法的有効性と司法書士が使う電子証明書
2025年12月15日