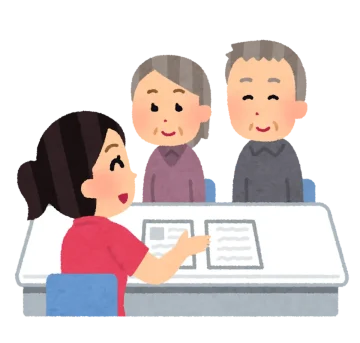
最終更新日:2025年11月27日
認知症と夫婦の財産管理:知っておきたい法律と対策
認知症は高齢化社会においてますます重要な課題となっています。内閣府の統計によれば、2025年には65歳以上の高齢者の約5人に1人が認知症を患うと予測されており、これは約700万人に相当します。特に、夫婦の一方が認知症を患った場合、日常生活の支援だけでなく、財産管理が大きな問題となることがあります。この記事では、認知症と財産管理に関する法律とその対策について詳しく解説します。
認知症と財産管理の課題
認知症の影響と法的な課題
認知症が進行すると、本人が財産管理を適切に行うことが難しくなります。民法では、判断能力が不十分な状態で行った契約は、後から取り消すことができる場合がありますが(民法第7条)、これは相手方にとっては不安定な状況をもたらします。そのため、銀行では認知症の疑いがある方の取引に慎重になり、以下のような問題が生じることがあります:
- 預金の引き出しや振込ができなくなる
- 新規の口座開設が難しくなる
- クレジットカードの更新ができない
- 不動産の売却や担保設定ができない
- 遺産分割協議に参加できない
特に問題となるのは、判断能力が完全に失われていない「グレーゾーン」の状態です。この段階では、本人も家族も認知症の影響を十分に認識できておらず、適切な対応が遅れがちになります。
夫婦間の財産管理の特殊性
夫婦の一方が認知症になった場合、もう一方の配偶者が財産管理を引き継ぐことが一般的ですが、日本の法律では夫婦であっても自動的に財産管理権が移るわけではありません。特に以下のケースで問題が生じやすくなります:
問題が生じやすいケース
- 名義が認知症の配偶者になっている財産:預金口座や不動産が認知症の配偶者名義である場合、健常な配偶者が勝手に処分することはできません
- 共有財産の処分:不動産などが夫婦共有の場合、一方の同意なしに処分できません
- 年金や保険金の受け取り:本人名義の年金や保険金の受取手続きができなくなる場合があります
- 高額な医療・介護費用の支払い:預金が凍結されると、必要な費用の支払いに支障をきたします
例えば、夫が認知症になり、自宅が夫名義である場合、住宅ローンの借り換えや自宅の売却を妻だけの判断で行うことはできません。また、夫名義の預金口座からの引き出しも制限される可能性があります。
法律に基づく対策の選択肢
1. 成年後見制度の活用
成年後見制度は、認知症などにより判断能力が不十分になった方を法律的に支援する制度です。家庭裁判所によって選任された後見人が、本人の財産を管理し、保護します。成年後見制度には以下の3つの類型があります:
| 類型 | 対象者 | 権限の範囲 |
|---|---|---|
| 後見 | 判断能力が欠けているのが通常の状態の方 | 財産に関するすべての法律行為を代理可能 |
| 保佐 | 判断能力が著しく不十分な方 | 重要な財産行為に同意権・取消権あり、特定の事項は代理可能 |
| 補助 | 判断能力が不十分な方 | 特定の法律行為について同意権・取消権あり、特定の事項は代理可能 |
夫婦間での成年後見制度の利用において、多くの場合は配偶者が後見人に選任されますが、必ずしもそうなるとは限りません。裁判所は本人の福祉を最優先に考え、最適な後見人を選任します。
成年後見制度のメリットとデメリット
メリット
- 法的に安全な財産管理が可能
- 第三者からの不当な契約や詐欺から保護される
- 本人の生活全般の支援が可能
- 定期的な裁判所のチェックにより不正防止
デメリット
- 申立てから開始までに通常2〜3ヶ月かかる
- 年間10〜20万円程度の後見人報酬が発生
- 家庭裁判所の監督下に置かれる
- 後見人の交代には裁判所の許可が必要
- 本人の死亡で終了(相続手続きはできない)
2. 任意後見契約の活用
任意後見契約は、将来、判断能力が低下したときのために、あらかじめ信頼できる方を任意後見人として選び、財産管理や身上監護について委任する制度です。認知症になる前に、自分の意思で後見人と契約内容を決められる点が大きな特徴です。
任意後見契約は公正証書で作成され、以下のような特徴があります:
- 本人が希望する方を任意後見人に指定できる
- 委任する事務の内容を自由に決められる
- 報酬額を事前に取り決めることができる
- 将来、判断能力が低下した時点で家庭裁判所が任意後見監督人を選任し、契約が発効する
夫婦間での任意後見契約は、お互いを任意後見人に指定し合うケースが多く見られます。ただし、将来双方が認知症になる可能性も考慮して、第三者(子や専門職)を代替の任意後見人として指定しておくことも検討すべきでしょう。
任意後見契約のメリットとデメリット
メリット
- 自分で後見人と委任事項を選べる
- 判断能力があるうちに契約内容を自分で決定できる
- 発効前の見守り契約も併用できる
- 法定後見よりも柔軟な運用が可能
デメリット
- 公正証書作成費用が必要(約5万円前後)
- 発効には医師の診断書と家庭裁判所の審判が必要
- 任意後見監督人への報酬が必要(月1〜2万円程度)
- 任意後見人が高齢化・死亡した場合の交代手続きが複雑
3. 家族信託(民事信託)の活用
家族信託は、本人(委託者)が信頼できる家族(受託者)に財産管理を任せる仕組みです。認知症になる前に信託契約を結んでおくことで、認知症発症後も受託者が委託者の財産を管理し続けることができます。
家族信託の基本的な仕組み

※イメージ図です。実際の契約内容により詳細は異なります。
家族信託では、以下の3つの立場が存在します:
- 委託者:財産を信託する人(例:認知症リスクのある配偶者)
- 受託者:財産を管理・処分する人(例:健康な配偶者)
- 受益者:信託の利益を受ける人(通常は委託者本人、次いで推定相続人)
家族信託の特徴として、受託者は信託財産の名義人となるため、委託者が認知症になっても、受託者の判断で財産管理や処分が可能になります。例えば、夫名義の自宅不動産を信託財産とし、妻を受託者とすれば、夫が認知症になっても妻の判断で自宅の売却や建て替えなどが可能となります。
家族信託のメリットとデメリット
メリット
- 認知症発症後も柔軟な財産管理が可能
- 家庭裁判所の関与なく手続きできる
- 財産管理の方針を事前に細かく決められる
- 不動産や株式など幅広い財産に対応
- 相続対策と認知症対策を同時に行える
デメリット
- 設定費用がかかる(50〜100万円程度)
- 不動産の場合、信託登記の登録免許税が必要
- 受託者に第三者チェック機能がない
- 金融機関によっては預金の信託に対応していない場合も
- 信託契約の変更には委託者の判断能力が必要
4. 夫婦間の財産管理のための代理権授与契約
代理権授与契約(委任契約)は、特定の法律行為について代理権を与える契約です。例えば、妻が夫に対して銀行取引や不動産管理などの代理権を与えることで、夫が妻の財産を管理できるようになります。
代理権授与契約は公正証書で作成することが一般的で、代理権の範囲を具体的に定めることができます。ただし、この契約は本人の判断能力がある間しか有効ではなく、認知症が進行して判断能力が失われると効力を失います。そのため、認知症の初期段階での対応策として有効です。
5. 遺言書の作成
認知症が進行する前に遺言書を作成しておくことで、財産の分配について明確な指示を残すことができます。特に公正証書遺言は、公証人の関与により法的効力が高く、内容の確実な実現が期待できます。
遺言書には以下のような内容を記載することが可能です:
- 特定の財産を特定の相続人に相続させる指定
- 相続人以外の方への遺贈
- 遺言執行者の指定
- 後継ぎ遺贈(条件付遺贈)
遺言書は、認知症による判断能力低下後の財産争いを防ぐための有効な手段となります。特に、夫婦間で互いの意向を尊重した遺言書を作成しておくことで、将来的なトラブルを未然に防ぐことができます。
認知症に備える具体的なステップ
早期対応の重要性
認知症対策で最も重要なのは、早期の対応です。判断能力が低下する前に対策を講じることで、選択肢が広がります。以下のようなサインが見られたら、専門家に相談することをお勧めします:
- 同じことを何度も質問する
- お金の計算や管理がおろそかになる
- 日付や場所の認識が曖昧になる
- 物の置き場所がわからなくなる頻度が増える
- 判断力や決断力が低下している
段階別の対応策
【認知症の前段階】
- 夫婦間で財産の全体像を共有する
- 預金口座やローンの名義状況を確認する
- 共同名義の口座を設けることを検討する
- 任意後見契約の検討と締結
- 家族信託の検討と契約
- 公正証書遺言の作成
【認知症の初期段階】
- かかりつけ医への相談と診断
- 代理権授与契約(委任契約)の締結
- 任意後見契約(未締結の場合)
- 金融機関での手続き(代理人届出等)
- 日常生活の支援体制の構築
【認知症が進行した段階】
- 成年後見制度の利用申立て
- 任意後見契約の発効手続き(契約済みの場合)
- 介護サービスの導入検討
- 身上監護と財産管理の体制確立
専門家への相談
認知症と財産管理の問題は、法律・医療・福祉など多岐にわたる知識が必要です。早い段階から専門家に相談することで、適切な対策を講じることができます。
相談先と役割
- 司法書士・行政書士:成年後見制度の申立て、任意後見契約、遺言書作成の支援
- 弁護士:法的紛争の解決、複雑な財産管理の相談
- 税理士・公認会計士:相続税対策、財産管理の税務相談
- 社会福祉士:介護サービスの調整、生活支援
- 医師(精神科・神経内科):認知症の診断、治療方針の相談
特に、認知症の早期段階では、法律専門家と医療専門家の連携が重要です。司法書士や行政書士は、認知症に関連する法的対応について、実務的なアドバイスを提供することができます。
まとめ
認知症と財産管理の問題は、事前の準備と適切な法的対応によって大きく改善することができます。特に夫婦間での財産管理では、以下のポイントを押さえておくことが重要です:
- 早期対応:認知症の兆候が見られたら、早めに専門家に相談する
- 夫婦間の情報共有:お互いの財産状況を把握しておく
- 適切な法的対策:任意後見契約、家族信託、遺言書などを活用する
- 段階に応じた対応:認知症の進行度に合わせて適切な対策を講じる
- 専門家のサポート:法律・医療・福祉の専門家に相談する
認知症は誰にでも起こりうる可能性がある病気です。「もしも」の時に慌てないよう、元気なうちから準備を進めておくことが、ご自身とご家族を守ることにつながります。当事務所では、認知症に関連する財産管理のご相談を承っておりますので、お気軽にご相談ください。
■■□―――――――――――――――――――□■■
司法書士・行政書士和田正俊事務所
【住所】 〒520-2134 滋賀県大津市瀬田5丁目33番4号
【電話番号】 077-574-7772
【営業時間】 9:00~17:00
【定休日】 日・土・祝
■■□―――――――――――――――――――□■■
🌟 わずか10秒!あなたのその悩み、LINEで即解決しませんか?
相続や登記、会社設立の疑問を抱えたまま、重い腰を上げる必要はありません。
当事務所では、ご多忙な皆様のためにLINE公式アカウントを開設しています。
✅ 【手軽】 氏名や住所の入力は不要。匿名で相談OK!
✅ 【迅速】 お問い合わせから最短5分で司法書士に直接つながります。
✅ 【無料】 もちろん、初回のLINE相談は完全無料です。
▼ 今すぐLINEで友だち追加して、相談を開始!
◇ 当サイトの情報は執筆当時の法令に基づく一般論であり、個別の事案には直接適用できません。
◇ 法律や情報は更新されることがあるため、専門家の確認を推奨します。
◇ 当事務所は情報の正確性を保証せず、損害が生じた場合も責任を負いません。
◇ 情報やURLは予告なく変更・削除されることがあるため、必要に応じて他の情報源もご活用ください。
この記事を書いた人

司法書士・行政書士 和田正俊事務所 代表和田 正俊(Wada Masatoshi)
- 滋賀県司法書士会所属 登録番号 滋賀第441号
- 簡裁訴訟代理関係業務 認定番号 第1112169号
- 滋賀県行政書士会所属
登録番号 第13251836号会員番号 第1220号 - 公益社団法人 成年後見センター・リーガルサポート滋賀支部所属
会員番号 第6509213号
後見人候補者名簿 及び 後見監督人候補者名簿 搭載 - 法テラス契約司法書士
- 近畿司法書士会連合会災害相談員
成年後見・権利擁護に関連する記事
年の瀬に見直す成年後見制度|高齢の親との年末年始で考えるべきこと
2025年12月24日
【司法書士解説】地面師詐欺から高齢者を守る
2025年7月2日




