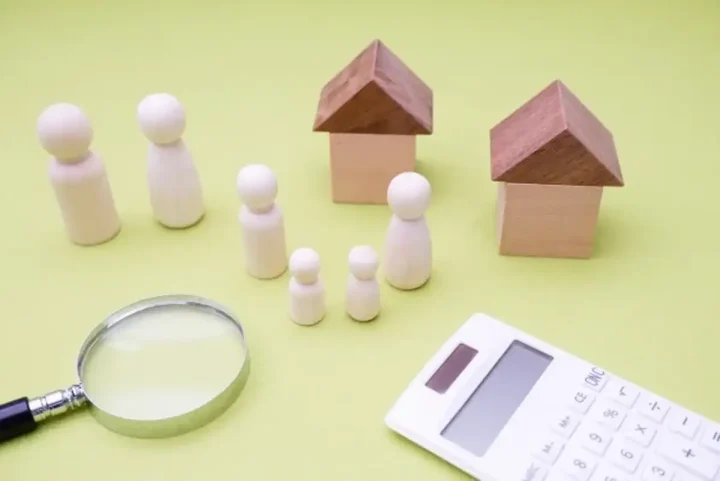こんなお悩みADRで解決しませんか? ~司法書士会調停センターの活用法~
日常生活の中で、私たちはさまざまなトラブルや紛争に直面することがあります。そんなとき、裁判に頼らずに問題を解決できる方法として「ADR(裁判外紛争解決手続)」があります。今回は、司法書士会調停センターを活用したADRの魅力とその利用方法についてご紹介します。
ADRのメリット:
- 裁判より迅速に解決できる
- 費用が抑えられる
- 手続きが柔軟で話し合いによる解決が可能
- 当事者同士の関係修復が期待できる
- プライバシーが守られる(非公開の手続き)
ADRとは?
裁判外紛争解決手続
ADR(Alternative Dispute Resolution)は、「裁判に代わる紛争解決手段」を意味し、裁判所の訴訟手続きを使わずに紛争を解決する方法です。調停、仲裁、あっせん、和解などの手続きが含まれます。
裁判は時間と費用がかかり、また勝ち負けを決める手続きであるため、当事者同士の関係が悪化することもあります。一方、ADRは話し合いによる合意形成を目指すため、お互いの関係を修復しながら問題解決できる点が大きな特徴です。
司法書士会調停センターの役割
調停センターの誕生と現状
司法書士会調停センターは、紛争解決を支援するために設立された機関です。最初のセンターが神奈川に誕生してから20年が経ち、現在では全国に29のセンターが稼働しています。
しかし、その存在はまだ十分に知られておらず、利用件数も限られています。多くの方にその存在と利便性を知っていただくことが、現在の大きな課題となっています。
取り扱い事件の範囲
調停センターで扱える事件は、原則として簡易裁判所の事物管轄に限られています。ただし、弁護士の助言を取り入れている7つのセンターでは、より幅広い分野での利用が可能です:
- 遺産分割協議
- 離婚時の財産分与
- 養育費の取り決め
- 不動産登記に関する紛争
- その他、民事上のトラブル
調停センターの利用方法
STEP 1: 相談・申込み
まずは最寄りの司法書士会調停センターに相談します。紛争の内容や相手方の連絡先などを伝え、ADR手続きの申込みを行います。
STEP 2: 相手方への連絡
センターから相手方に連絡し、ADR手続きへの参加を依頼します。相手方が同意すれば手続きが開始されます。
STEP 3: 調停の実施
中立的な立場の調停人(司法書士)が間に入り、双方の話を聞きながら解決策を探ります。複数回の話し合いが行われることもあります。
STEP 4: 和解成立
合意に達した場合は和解契約書を作成します。必要に応じて、裁判所での即決和解手続きを利用し、執行力を持たせることも可能です。
利用に適した事例
遺産分割トラブル
「父が亡くなり遺産分割で兄弟と話がまとまらない」
「遺言書の解釈について親族間で意見が分かれている」
離婚関連の問題
「離婚時の財産分与について合意できない」
「養育費の金額や支払方法について話し合いたい」
不動産関連トラブル
「境界線について隣人と争いがある」
「共有不動産の管理や処分について意見が対立している」
金銭トラブル
「貸したお金が返ってこない」
「請負契約の代金支払いについてもめている」
和解に執行力を持たせる
調停センターでの和解は、当事者の合意に基づくものですが、そのままでは相手が約束を守らなかった場合に強制執行することができません。そこで重要なのが「執行力」を持たせる手続きです。
執行力を持たせる方法
- 即決和解手続き:和解成立後、裁判所で即決和解手続きを行います。これにより、裁判所の和解調書と同じ効力を持ちます。
- 公正証書の作成:和解内容を公正証書にすることで執行力を持たせることもできます。
これらの手続きを行うことで、相手が和解内容を守らない場合でも、強制執行により確実に履行させることが可能になります。
調停センターの利用促進に向けて
リーフレットの作成
司法書士会では、調停センターの利用を促進するために、手に取りやすいリーフレットを作成しました。このリーフレットには以下の情報が掲載されています:
- ADRの利用に適した事例紹介
- 和解に執行力を持たせる方法
- 遺産分割協議に利用できるセンターの案内
- 近隣のセンターを探せる二次元コード
会員への周知と利用拡大
リーフレットを通じて、司法書士会の会員にも調停センターの存在とその利便性を広く知ってもらい、クライアントへの紹介や活用を促進しています。
今後は、さらに一般の方々への周知活動も強化し、より多くの方が調停センターを活用して紛争を円滑に解決できるようになることを目指しています。
まとめ
司法書士会調停センターは、裁判に頼らずに紛争を解決するための有効な手段です。迅速性、経済性、柔軟性といったADRの特徴を生かし、当事者同士の関係を修復しながら問題解決ができる点が大きな魅力です。
遺産分割や離婚時の財産分与、不動産関連のトラブルなど、身近な問題でお悩みの際は、ぜひ司法書士会調停センターの利用をご検討ください。話し合いによる解決を通じて、より良い人間関係の構築と平和な社会の実現に貢献できることでしょう。
ADRに関するご相談
裁判外紛争解決手続き(ADR)や司法書士会調停センターの利用方法について、詳しく知りたい方はお気軽にご相談ください。トラブル解決のための最適な方法をご提案いたします。
司法書士・行政書士和田正俊事務所
住所:〒520-2134 滋賀県大津市瀬田5丁目33番4号
電話番号:077-574-7772
営業時間:9:00~17:00
定休日:日・土・祝
事務所からのお知らせに関連する記事
滋賀県大津市の司法書士・行政書士にLINEで無料法律相談|和田正俊事務所
2025年11月7日
司法書士が警鐘! 凍結口座3億円引き出し事件に見る「公正証書」の光と影
2025年7月10日