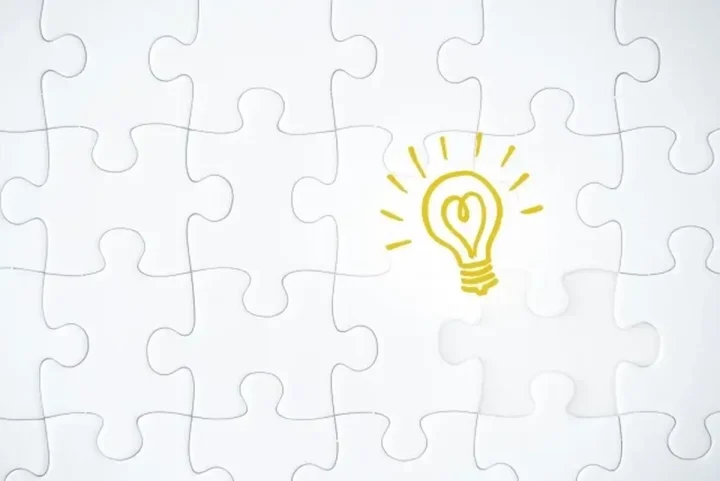【京都】司法書士が生前贈与7年内加算を解説!遺産承継の相談はお気軽に

生前贈与や遺産承継で損をしたくないなら
京都での手続きは司法書士へご相談を!
生前贈与をご検討なら、生前贈与加算にご注意ください。生前贈与の時期や相続人によっては、思ったような節税効果は得られないことがあります。損をしないためにも、京都での生前贈与は司法書士へご相談ください。
生前贈与7年内加算とは?

生前贈与とは、亡くなってから行われるはずの財産の承継を生前に行うものです。メリットとしては、相続税の節税になること、渡したい相手やタイミングを自分で決められること、争族トラブルを回避できることなどが挙げられます。
法定相続人以外にも贈与する相手を選べるのが、相続における遺産承継との大きな違いです。贈与には「贈与税」が課されますが、非課税枠や控除が用意されており、上手に活用すれば節税効果が期待できます。
生前贈与7年内加算とは
生前贈与をするにあたり気をつけたいのが、「生前贈与7年内加算」制度です。この制度は、贈与する人が亡くなった日より、丸7年さかのぼった日からの生前贈与が「なかったもの」とされるもので、死期が予見できる人の「駆け込み贈与」を防ぐ目的があります。
例えば、毎年200万円の贈与を受け、贈与税として9万円支払っていたとしても、亡くなる以前の7年間の贈与分1400万円は「贈与されなかった」ことにされ、本来の相続財産に戻されてしまいます。毎年支払っていた合計63万円の贈与税は、二重課税にならないよう控除されるので心配いりません。
つまり、結局「何もしなかった」のと同じということになるのです。「非課税枠を使えばお得」と思って始めた生前贈与であっても、生前贈与7年内加算の対象になってしまうと、努力が徒労に終わってしまいます。わかった時点で贈与する人はすでに故人のため、どうすることもできません。
基礎控除110万円も加算対象
この生前贈与加算は、毎年の非課税枠110万円の基礎控除ですら対象になってしまいます。例えば、非課税になるよう毎年110万円ずつ贈与をしていても、亡くなった日から7年さかのぼって贈与した770万円は、「贈与しなかったことと同じ」になります。この770万円は相続財産に戻されるため、非課税ではなく、きっちりと相続税の課税対象となるのです。
生前贈与加算の対象外
いつ相続が発生するかは誰にもわかりませんが、生前贈与加算の対象から逃れる方法が2つあります。
・相続人以外に贈与
贈与を法定相続人ではない第三者へ行う場合、生前贈与加算に該当しなくなります。対象は配偶者、子、親、兄弟への贈与の際に発生します。すなわち、子の配偶者や孫、孫の配偶者など非相続人であれば対象外となるのです。ただし、子がすでに死亡して、孫が代わりに相続人となっている場合(代襲相続)、遺言書により孫を相続人と決めている場合は生前贈与加算の対象となります。
・4つの特例
以下の特例も対象外となるため、可能であれば積極的に利用したほうがよいでしょう。
- 「贈与税の配偶者控除」
- 「住宅取得資金の贈与」
- 「教育資金の贈与」
- 「結婚・子育て資金の贈与」
いずれも非課税になる金額の上限や取得の条件が限られており、贈与した全額が対象になるというものではありません。しかし、相続人に贈与したい場合は上記が適用になるか確認をしておきます。上記の贈与が非課税と認められれば、相続人が生前贈与されていたとしても、7年以内の生前贈与加算の対象外となります。
生前贈与加算の対象外をうまく活用!遺産承継のご相談はお気軽に

生前贈与を成功させるためには、相続人である配偶者や子ではなく、相続人ではない孫や子の配偶者に贈与をすることです。ただし、遺言書で孫を相続人に定めていた場合はこの限りではなくなるため、遺言書を書く際には注意が必要です。
また、住宅取得金や教育資金などについては、贈与した相手が相続人であっても、特例として7年内贈与加算の対象にはなりません。取得要件には細かい条件もありますが、ただ現金を贈与するのではなく、特例に該当する贈与があればうまく活用しましょう。
「生前贈与がお得」と思い込んでしまうのは少々危険です。相続人へ生前贈与したいのであれば、少しでも若く元気なうちに始めましょう。あらかじめ資産の分け方を工夫すれば、誰も損をしない結果が得られます。
和田正俊事務所では、初回無料の出張相談やオンライン相談を承っております。家族により多くの財産を残すためにも、遺産承継のプロに相談してはいかがでしょうか。相続は手続きも複雑なことが多いため、お一人で悩まずお気軽にご相談ください。
◇ 当サイトの情報は執筆当時の法令に基づく一般論であり、個別の事案には直接適用できません。
◇ 法律や情報は更新されることがあるため、専門家の確認を推奨します。
◇ 当事務所は情報の正確性を保証せず、損害が生じた場合も責任を負いません。
◇ 情報やURLは予告なく変更・削除されることがあるため、必要に応じて他の情報源もご活用ください。
【滋賀・京都・司法書士】相続・遺産に関するお役立ちコラム
滋賀県で不動産相続の手続きにお悩みなら和田正俊事務所へ
| 事務所名 | 司法書士・行政書士 和田正俊事務所 |
|---|---|
| 住所 | 〒520-2134 滋賀県大津市瀬田5丁目33−4 |
| TEL | 077-574-7772 |
| FAX | 077-574-7773 |
| URL | https://wada7772.com/ |
| 営業時間 | 9:00~17:00 |
| 定休日 | 土・日・祝(事前予約により対応させていただきます。) |
| 取扱業務 | ・不動産登記(相続・生前贈与・売買・抵当権抹消等) ・遺言書作成(自筆証書・秘密証書・公正証書) ・商業・法人登記(会社設立・役員変更・機関変更・組織再編・その他) ・簡易裁判所における民事事件 ※ ・債務整理 ※(裁判外での和解交渉・民事再生・特定調停・破産申立て) ・債権回収 ※(電話での支払交渉・内容証明郵便・支払督促・民事訴訟) ・裁判所提出書類作成(民事事件・家事事件・非訟事件 等) ・成年後見(法定後見・任意後見) ・相談(面接相談・出張相談・電話相談・メール相談・FAX相談) ・継続的相談契約(アドバイザー契約) ・遺産承継業務(預貯金・株式・投資信託・生命保険等) ・相続財産調査業務(取引有無確認・残高照会等) ※簡易裁判所の事物管轄に限ります。簡易裁判所の事物管轄に収まらない場合は訴訟支援としてお手伝いさせていただきます。 上記以外の業務も承っております。お気軽にお声かけ下さいませ。 |
🌟 わずか10秒!あなたのその悩み、LINEで即解決しませんか?
相続や登記、会社設立の疑問を抱えたまま、重い腰を上げる必要はありません。
当事務所では、ご多忙な皆様のためにLINE公式アカウントを開設しています。
✅ 【手軽】 氏名や住所の入力は不要。匿名で相談OK!
✅ 【迅速】 お問い合わせから最短5分で司法書士に直接つながります。
✅ 【無料】 もちろん、初回のLINE相談は完全無料です。
▼ 今すぐLINEで友だち追加して、相談を開始!
◇ 当サイトの情報は執筆当時の法令に基づく一般論であり、個別の事案には直接適用できません。
◇ 法律や情報は更新されることがあるため、専門家の確認を推奨します。
◇ 当事務所は情報の正確性を保証せず、損害が生じた場合も責任を負いません。
◇ 情報やURLは予告なく変更・削除されることがあるため、必要に応じて他の情報源もご活用ください。
この記事を書いた人

司法書士・行政書士 和田正俊事務所 代表和田 正俊(Wada Masatoshi)
- 滋賀県司法書士会所属 登録番号 滋賀第441号
- 簡裁訴訟代理関係業務 認定番号 第1112169号
- 滋賀県行政書士会所属
登録番号 第13251836号会員番号 第1220号 - 公益社団法人 成年後見センター・リーガルサポート滋賀支部所属
会員番号 第6509213号
後見人候補者名簿 及び 後見監督人候補者名簿 搭載 - 法テラス契約司法書士
- 近畿司法書士会連合会災害相談員
相続・遺産に関するお役立ちコラムに関連する記事