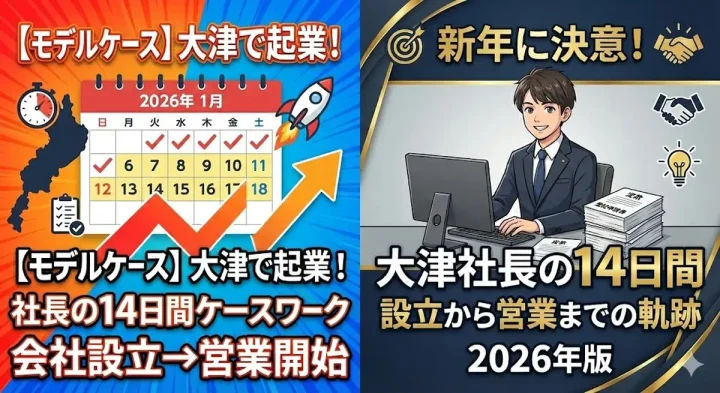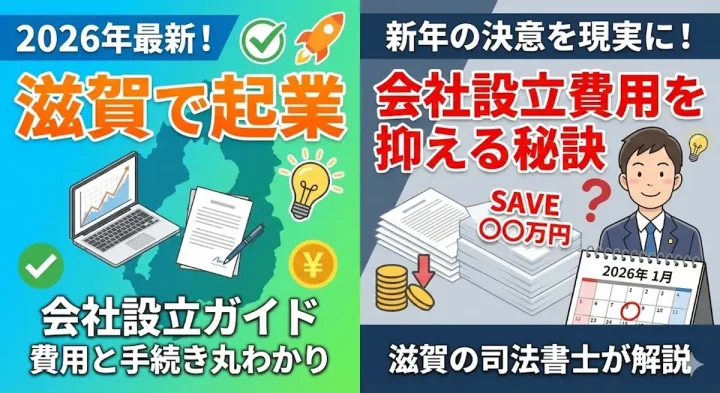はじめに:会社役員のプライバシー保護と商業登記規則改正の重要性

2024年10月1日から施行された代表取締役等住所非表示措置は、会社役員のプライバシー保護を目的とした重要な法改正です。しかし、新しい制度には実務上の疑問も多く、司法書士の間でも運用に関する情報が錯綜していました。
この度、日本司法書士会連合会から、実務上の疑問に答えるQ&Aの修正版が発表されました。今回はこの最新情報を基に、非表示措置の概要と、特に司法書士が実務で直面しやすい疑問点、そしてそれが私たちにどう影響するのかを解説します。
第1章:代表取締役等住所非表示措置とは?基本を押さえよう
まず、この制度がどのようなものなのか、改めてその基本を確認しましょう。
- 制度の目的: なぜ役員の住所を非表示にする必要があるのか?(プライバシー保護、ハラスメント対策など)
- 対象となる役員: 代表取締役だけでなく、代表執行役や代表清算人も対象です。
- 非表示になる範囲: どこまでが非表示になり、どこまでが公開されるのか?(市区町村まで表示され、それ以降は非表示)
- 対象となる会社: 株式会社に限定され、特例有限会社や持分会社は対象外です。
この措置によって、会社や役員にとってどのようなメリットがあるのかを解説します。
第2章:申出のタイミングが重要!非表示措置を希望する際のポイント
住所非表示措置は、いつでも申出ができるわけではありません。特定の登記申請と同時に行う必要があります。
- 申出が可能な登記: 設立登記、代表取締役等の就任・重任登記、住所変更登記、管轄外本店移転登記など。
- 申出ができない登記: 氏名変更登記や住所更正登記では申出ができません。
- 施行日前の原因日付でも可能か?: 2024年10月1日(施行日)より前の原因日付であっても申出は可能です。
オンラインでの申出方法や、申出に不備があった場合の取り扱いについても触れます。
第3章:実務の肝!申出に必要な「添付書類」の具体的な注意点
今回のQ&A修正のポイントにもなったのが、申出の際に添付する書類です。特に複雑なのは以下の3点。
- 本店所在場所の実在性を証する書面:
- 会社のオフィスが実際に存在することを示す書類です。
「配達証明書等」または「資格者代理人証明書」が必要です。
バーチャルオフィスやシェアオフィスを利用している場合は、その契約書や、郵便物の受取サービスに関する書類など、より厳格な確認が必要になります。
レンタルオフィスやコワーキングスペースの場合も、利用契約書や住所の使用許可書などを確認します。
設立登記と同時申出の場合の特例あり。 - 代表取締役等住所証明書:
- 役員の現在の住所を証明するものです。
住民票の写し、運転免許証の写しなどが該当します。
今回のQ&Aの修正点「AⅢ-23」は、この証明書上の住所と登記申請書上の住所の記載が重要になる点です。 記載が一致しているか、少しでもずれがないか、細心の注意を払って確認します。
ハイフン表記の場合の注意点など。 - 実質的支配者の本人特定事項を証する書面:
- 会社の利益の大部分を支配している人物(実質的支配者)の氏名や住所などを確認する書類です。
法務局に提出済みの「実質的支配者情報一覧の写し(実質的支配者リスト)」を代わりに使える場合もあります。
司法書士が作成する確認記録や、公証人の認証を受けた書面などが該当します。 - 上場会社であることを証明する書類:
- 上場会社が非表示措置を申し出る場合に必要です。
各書類の具体的な要件や、司法書士が確認すべきポイントを掘り下げます。
第4章:非表示措置は「自動継続」する?「終了」する?継続と終了の条件
1.非表示措置はずっと続くの?
原則として、役員が同じ会社で役職を続ける限り、自動的に非表示措置は継続します。
ただし、役員が非表示を希望しなくなった場合や、会社の本店の場所が実在しなくなった場合、上場会社でなくなった場合など、特定の条件を満たすと非表示措置は終了します。
- 自動継続するケース: 住所変更がない重任・再任登記、管轄外本店移転登記(新本店側)など。
- 自動継続しないケース: 住所変更を伴う重任・再任登記、最小行政区画内での住所移転など。
また、非表示措置が終了する条件は次のとおりです。
- 会社が非表示を希望しなくなった場合
- 本店の実在性が認められなくなった場合(不達郵便など)
- 上場会社でなくなった場合など
2.非表示にした住所は、誰でも見られなくなるの?
通常の登記簿謄本からは見えなくなります。
ただし、特別な事情がある場合(例えば、会社の債権者や裁判所の命令など)は、一定の手続きを経て非表示の住所を確認できる仕組みがあります。これは、会社の透明性を完全に失わせないための重要なルールです。
私たち司法書士が、非表示措置がされた会社の登記申請を受任した場合は、ウェブ会議サービスを利用して法務局の担当者と面談し、本人確認を行うなど、より厳格な手続きが求められます。
まとめ:司法書士が知っておくべき実務上の注意点と、会社への適切なアドバイスのために
今回のQ&A修正からもわかるように、代表取締役等住所非表示措置は、細かな実務上の判断が求められる制度です。
司法書士は、この最新のQ&Aを常に確認し、正確な知識をもって登記申請を行う必要があります。
また、会社経営者の方々に対しては、この制度のメリット・デメリット、そして申出に必要な手続きや継続・終了の条件を適切にアドバイスすることが重要です。
ご自身の会社や、関与する会社の役員のプライバシー保護のためにも、この制度を正しく理解し、活用していきましょう。
◇ 当サイトの情報は執筆当時の法令に基づく一般論であり、個別の事案には直接適用できません。
◇ 法律や情報は更新されることがあるため、専門家の確認を推奨します。
◇ 当事務所は情報の正確性を保証せず、損害が生じた場合も責任を負いません。
◇ 情報やURLは予告なく変更・削除されることがあるため、必要に応じて他の情報源もご活用ください。
この記事を書いた人

司法書士・行政書士 和田正俊事務所 代表和田 正俊(Wada Masatoshi)
- 滋賀県司法書士会所属 登録番号 滋賀第441号
- 簡裁訴訟代理関係業務 認定番号 第1112169号
- 滋賀県行政書士会所属
登録番号 第13251836号会員番号 第1220号 - 公益社団法人 成年後見センター・リーガルサポート滋賀支部所属
会員番号 第6509213号
後見人候補者名簿 及び 後見監督人候補者名簿 搭載 - 法テラス契約司法書士
- 近畿司法書士会連合会災害相談員
法人・会社に関連する記事
【ケーススタディ】大津市で新年に起業した社長の14日間|会社設立から営業開始まで密着レポート
2026年1月12日
【2026年最新】滋賀県で起業する完全ガイド|会社設立の手続きと費用を司法書士が徹底解説
2026年1月5日
事業目的を追加・変更する登記。費用と期間、必要書類
2025年11月20日