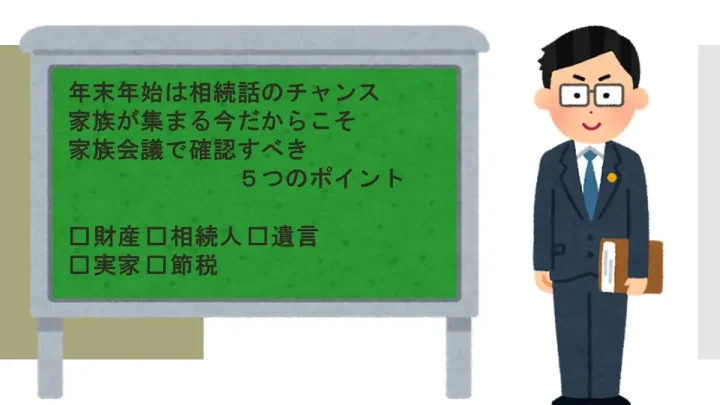自筆証書遺言の作り方完全ガイド - 法的に有効な遺言書を自分で書く方法
遺言書は、ご自身の大切な財産や想いを確実に引き継ぐための重要な法的文書です。中でも自筆証書遺言は、公正証書遺言と比べて費用をかけずに手軽に作成できる方法として知られています。しかし、法律で定められた厳格な要件を満たさなければ無効となってしまうリスクもあります。本記事では、自筆証書遺言の基本から作成のポイント、法的要件、そして専門家によるサポートの重要性までを詳しく解説します。
本記事のポイント:
- 自筆証書遺言の定義と法的要件
- 自筆証書遺言のメリット・デメリット
- 有効な自筆証書遺言を作成するためのステップ
- よくある間違いと対処法
- 自筆証書遺言保管制度の活用方法
- 当事務所による作成サポートの内容
自筆証書遺言とは - その定義と特徴
自筆証書遺言とは、遺言者が自分自身で全文を手書き(自筆)する遺言書です。民法968条に規定されている正式な遺言方式の一つであり、一定の法的要件を満たすことで有効な法的文書となります。
自筆証書遺言の最大の特徴は、公証人や証人の立会いなく、いつでもどこでも自分一人で作成できることです。そのため、プライバシーを守りながら、自分のペースで遺言内容を検討できる点が大きな魅力となっています。
ただし、パソコンやワープロ、コピーは認められておらず、手書きで作成する必要があります。また、法律で定められた厳格な要件を満たさないと無効となる可能性があるため、作成には注意が必要です。
自筆証書遺言の特徴
- 全文を手書きで作成
- いつでも自分で作成可能
- 費用がほとんどかからない
- プライバシーが守られる
- 厳格な形式要件あり
自筆証書遺言の法的要件 - これを守らないと無効になる可能性も
自筆証書遺言が法的に有効となるためには、民法で定められた以下の要件を厳格に満たす必要があります。これらの要件が一つでも欠けると、せっかく作成した遺言書が無効となってしまう可能性があります。
財産目録に関する特例(2019年1月施行):
2019年1月13日以降に作成する自筆証書遺言では、「財産目録」についてはパソコン等で作成したものや、預金通帳のコピー、不動産の登記事項証明書などを添付することが認められるようになりました。ただし、この場合も遺言者が各ページに署名押印する必要があります。
この特例を利用すると、財産の特定が容易になり、相続手続きがスムーズになるメリットがあります。
加除訂正の方法 - 間違えたときの正しい直し方
遺言書の作成中に間違えた場合や、後から修正したい場合は、民法968条2項に定められた「間接法」による加除訂正が必要です。一般的な文書の訂正方法とは異なるため、特に注意が必要です。
❌ 間違った訂正方法
- 二重線で消して上から書き直す
- 修正液・修正テープで消す
- 文字を上から訂正する
- 訂正箇所に印を押すだけ
✓ 正しい訂正方法
- 変更箇所に二重線を引く
- 欄外または余白に「○字目○○を△△に訂正」と明記
- 訂正部分の傍らに署名
- 訂正部分に押印
例えば、「財産を長男太郎に」と書いたものを「次男一郎に」と訂正したい場合、「太郎」に二重線を引き、欄外に「○行目の『太郎』を『一郎』に訂正」と書いて、その箇所に署名・押印します。
自筆証書遺言のメリット・デメリット
自筆証書遺言は手軽に作成できる反面、様々なリスクも伴います。以下にメリットとデメリットを整理しました。
メリット
- 費用が少ない:紙と筆記用具があれば作成可能
- 手続きが簡単:公証役場に行く必要がない
- いつでも作成可能:時間や場所を選ばない
- プライバシーが守られる:第三者に内容を知られずに作成できる
- 何度でも書き直せる:状況変化に応じて気軽に更新可能
デメリット
- 形式不備で無効になるリスク:要件を満たさないと全て無効に
- 紛失・破棄のリスク:保管方法によっては見つからない可能性
- 改ざんのリスク:悪意ある相続人による改ざんの可能性
- 検認手続きが必要:家庭裁判所での検認手続きが原則必要
- 解釈の争いが起きやすい:表現によっては相続人間で解釈が分かれる可能性
自筆証書遺言保管制度(法務局保管制度)の活用:
2020年7月からスタートした法務局における「自筆証書遺言保管制度」を利用すると、以下のメリットがあります:
- 紛失・破棄・改ざんのリスクを防止できる
- 家庭裁判所の検認手続きが不要になる
- 相続発生後に法務局が相続人等に遺言の有無を通知する
保管手数料は1通につき3,900円で、最寄りの法務局(遺言書保管所)で申請できます。ただし、この場合も自筆証書遺言の法的要件は満たす必要があります。
有効な自筆証書遺言を作成するためのステップ
法的に有効で、かつご自身の意思を正確に反映した自筆証書遺言を作成するためのステップを紹介します。
STEP 1: 財産の洗い出しと受取人の検討
まず、ご自身の財産を全て洗い出し、誰に何を相続させたいかを明確にします。預金、不動産、有価証券、貴金属、自動車など、できるだけ詳細に財産を特定しましょう。また、相続人の氏名・続柄・生年月日なども確認しておくと良いでしょう。
STEP 2: 遺言の内容を下書き
内容を整理したら、まず下書きを作成します。この段階では消しゴムで修正しても問題ありません。財産の表記は「○○銀行△△支店普通預金口座(口座番号●●●●)」など、できるだけ具体的に記載します。相続人の氏名も「長男 山田太郎」など、関係性と氏名を明記しましょう。
STEP 3: 専門家によるチェック(推奨)
下書きの段階で司法書士などの専門家にチェックしてもらうことをお勧めします。表現の適切さや法的な問題点、遺留分の侵害がないかなどをアドバイスしてもらえます。当事務所でも遺言内容の専門的なチェックを承っています。
STEP 4: 清書
チェックを受けた内容に問題がなければ、A4用紙などに清書します。この段階では間違えないよう慎重に書きましょう。万が一間違えた場合は、前述の「間接法」で正しく訂正します。また、複数ページになる場合は、各ページに通し番号を付け、契印(ページの継ぎ目に押す印)を押すことをお勧めします。
STEP 5: 日付・氏名の記入と押印
遺言書の最後に作成日(西暦または元号で年月日)を記入し、氏名を自署して押印します。印鑑は実印が望ましいですが、認印でも法的には有効です。
STEP 6: 保管
完成した遺言書は、以下のいずれかの方法で大切に保管します:
- 法務局での保管(自筆証書遺言保管制度を利用)
- 自宅の金庫など安全な場所での保管
- 信頼できる専門家(司法書士等)への保管依頼
また、遺言の存在と保管場所を信頼できる人(遺言執行者など)に伝えておくことも大切です。
自筆証書遺言の文例
以下に、基本的な自筆証書遺言の文例を紹介します。これはあくまで参考例ですので、実際には個別の状況に応じた内容にカスタマイズする必要があります。
遺言書
私、山田太郎(住所:滋賀県大津市○○町1-2-3)は、以下のとおり遺言します。
- 私が所有する滋賀県大津市△△町4-5-6所在の土地(地番○○番、地積○○平方メートル)及び同所に存する建物(家屋番号○○番、床面積○○平方メートル)を、長男 山田一郎(昭和○○年○月○日生)に相続させる。
- 株式会社○○銀行△△支店の普通預金口座(口座番号:○○○○○○○)の預金全額を、長女 山田花子(平成○年○月○日生)に相続させる。
- 株式会社△△証券○○支店の証券口座(口座番号:○○○○○○○)の有価証券及び預り金の全てを、次男 山田次郎(平成○年○月○日生)に相続させる。
- 私の葬儀及び埋葬に関する事項並びに遺言の執行に関する事項は、長男 山田一郎に一任する。
令和○年○月○日
山田 太郎 印
注意点:
- 上記は例文です。実際に作成する際は、全文を自筆で書く必要があります
- 財産は正確に特定できるよう、詳細な情報を記載しましょう
- 相続人も名前だけでなく続柄や生年月日などで特定するとより確実です
- 遺言執行者を指定しておくと、遺言の実現がスムーズになります
当事務所の自筆証書遺言作成サポート
自筆証書遺言は自分で作成できるものですが、法的要件を満たし、かつ自分の意思を正確に反映した内容にするためには、専門家のサポートを受けることをお勧めします。当事務所では、お客様の大切な想いが確実に実現するよう、自筆証書遺言の作成を総合的にサポートしています。
当事務所でお手伝いできること
- 自筆証書遺言の内容検討・専門的なアドバイス
- 財産の洗い出しと相続人の確認
- 遺留分を考慮した財産分配のアドバイス
- 法的に明確で争いを生まない表現の提案
- 自筆証書遺言の法律的な要件チェック
- 形式要件の確認と不備の指摘
- 記載内容の法的妥当性の確認
- 加除訂正が必要な場合の適切な方法指導
- 遺言書の保管サポート、遺言執行
- 自筆証書遺言保管制度(法務局保管)の手続き代行
- 当事務所での保管サービス(ご希望の場合)
- 遺言執行者としての就任と適切な遺言の執行
- その他、ご要望に応じた各種サポート
- 相続人への遺言内容の説明サポート
- 遺言と併用した生前対策のアドバイス
- 定期的な見直しと更新のお手伝い
ご自身の大切な思いが確実に実現するよう、最適な方法を一緒に考えさせていただきます。お気軽にご相談ください。
自筆証書遺言の作成サポートの流れ
STEP 1: お電話・メールでご相談受付
「遺言で相談」とご連絡ください。専門家が丁寧にヒアリングし、お客様のご要望や状況を確認いたします。初回相談は30分無料です。
STEP 2: 文案の打ち合わせ
相続財産の内容や、誰に何を遺したいかをじっくり打ち合わせします。この段階で以下の資料をご用意いただくとスムーズです:
- 固定資産税課税明細書(不動産所有者の方)
- 銀行通帳や証券口座の明細
- 相続人となる方々の情報(氏名、続柄、生年月日など)
STEP 3: 遺言書文案の作成
打ち合わせ内容に基づき、遺言者様の意思を正確に反映した文案を作成します。法的に有効で、かつ相続人間で争いが生じないような明確な表現を心がけます。作成した文案はお客様にご確認いただき、必要に応じて修正します。
STEP 4: 自筆清書
ご用意した文案をもとに、遺言者様ご自身に自筆清書していただきます。当事務所のサポートのもと、法的要件を満たしながら丁寧に清書することで、無効リスクを大幅に減らすことができます。必要に応じて、清書の際の注意点や筆記具の選び方などもアドバイスいたします。
また、複数ページになる場合は、各ページの綴じ方や契印の押し方など、細かな点までサポートいたします。加除訂正が必要になった場合も、正しい方法で行えるようお手伝いします。
STEP 5: 完成・保管
完成した遺言書は、お客様のご希望に応じて以下のいずれかの方法で保管します:
- ご自身での保管:安全な場所(金庫など)で保管される場合のアドバイス
- 法務局保管制度の利用:法務局での保管手続きのサポート(手数料3,900円が別途必要)
- 当事務所での保管:お客様のご希望により、当事務所で責任をもって保管(オプションサービス)
また、遺言書の存在と保管場所を誰に知らせておくべきか、遺言執行者をどうするかなど、遺言書作成後の対応についてもアドバイスいたします。
自筆証書遺言に関するよくある質問
Q1. 遺言書の作成に費用はどれくらいかかりますか?
A. 自筆証書遺言自体の作成には、紙と筆記用具以外の費用はかかりません。ただし、専門家のサポートを受ける場合は相談料・文案作成料などが発生します。当事務所では、初回相談30分は無料で、その後のサポート内容に応じた明確な料金体系をご案内しています。また、法務局保管制度を利用する場合は別途3,900円の手数料が必要です。
Q2. 自筆証書遺言と公正証書遺言はどちらがおすすめですか?
A. どちらが良いかは状況によって異なります。自筆証書遺言は手軽に作成でき、プライバシーが守られる一方、形式不備のリスクがあります。公正証書遺言は費用がかかりますが、公証人が関与するため形式不備の心配がなく、原本が公証役場で保管されるため紛失の心配もありません。相続財産が多額・複雑な場合や、相続人間で争いが予想される場合は公正証書遺言がおすすめです。詳しくはご相談の上、最適な方法をご案内いたします。
Q3. 遺言書は何歳から作成できますか?
A. 遺言書は満15歳以上であれば作成できます(民法第961条)。ただし、未成年者(20歳未満)の場合は、公正証書遺言や秘密証書遺言はできず、自筆証書遺言のみ作成可能です。また、遺言者が遺言能力(遺言の内容を理解し、自分の意思を表明できる能力)を有していることが前提となります。認知症などで判断能力が著しく低下すると、遺言能力がないと判断され、遺言が無効となる可能性があります。
Q4. 自筆証書遺言を法務局で保管する方法を詳しく教えてください
A. 2020年7月から始まった「自筆証書遺言保管制度」は、以下の手順で利用できます:
- 最寄りの法務局(遺言書保管所)に予約(電話等)
- 遺言者本人が法務局に出向く(代理人不可)
- 必要書類(本人確認書類、遺言書、財産目録など)を持参
- 手数料3,900円を納付
- 法務局で遺言書の形式確認、データ化、保管
保管後は「遺言書保管証」が交付され、相続発生後には法務局から相続人等に遺言書の有無が通知されます。また、法務局保管の自筆証書遺言は家庭裁判所の検認手続きが不要になります。当事務所では、この手続きの同行サポートも承っております。
Q5. 遺言書の内容は自由に決められますか?
A. 遺言の内容は基本的に自由ですが、完全に自由というわけではありません。特に注意すべきは「遺留分」の存在です。配偶者、子、直系尊属(親・祖父母)には遺留分(法定相続分の一定割合)が法律で保障されており、これを侵害する内容の遺言であっても、遺留分権利者が遺留分侵害額請求をすることができます。また、公序良俗に反する内容や、法律で認められていない事項(婚姻や離婚の強制など)は無効となります。遺言の内容については、専門家に相談することをお勧めします。
まとめ - 自筆証書遺言で想いを確実に伝えるために
自筆証書遺言は、比較的手軽に作成できる遺言方式として多くの方に選ばれています。費用をかけずに自分のペースで作成できるメリットがある一方で、法的要件を満たさないと無効になるリスクもあります。
特に注意すべきは、全文自筆であること、日付の記載、氏名の自署と押印という3つの基本要件です。また、加除訂正も特定の方法でしか認められないため、正しい知識を持って作成することが大切です。
せっかく書いた遺言書が形式不備で無効になったり、紛失・改ざんされたりすることのないよう、専門家のサポートを受けることをお勧めします。当事務所では、自筆証書遺言の内容検討から文案作成、法的要件のチェック、保管まで一貫してサポートしております。
また、2020年から始まった法務局の自筆証書遺言保管制度も、遺言書の紛失や改ざんを防ぎ、家庭裁判所の検認手続きを省略できる便利な制度です。積極的な活用をご検討ください。
遺言書は、ご自身の大切な財産や想いを確実に引き継ぐための重要な法的文書です。「書いておけばよい」という姿勢ではなく、法的に有効で、かつ自分の意思が正確に反映された内容になるよう、慎重に作成することが大切です。当事務所では、お客様の大切な想いを確実に実現するためのサポートを提供しております。お気軽にご相談ください。
司法書士・行政書士和田正俊事務所
住所:〒520-2134 滋賀県大津市瀬田5丁目33番4号
電話番号:077-574-7772
営業時間:9:00~17:00
定休日:日・土・祝
遺言・相続に関するご相談は、お電話またはメールにて「遺言について相談したい」とお伝えください。初回相談30分は無料です。
※本記事の内容は一般的な情報提供を目的としており、個別のケースに対する法的アドバイスを構成するものではありません。具体的な遺言作成については、当事務所までお問い合わせください。
相続・財産管理に関連する記事
【お正月限定】親族会議で必ず決めるべき相続の5項目|滋賀の司法書士が教える円満解決法2026
2025年12月26日
年末年始の帰省で話し合いたい相続の話:家族会議で確認すべき5つのポイント
2025年12月12日
遺言書作成のポイント|自筆・公正証書どちらがよい?比較&事例紹介
2025年12月12日