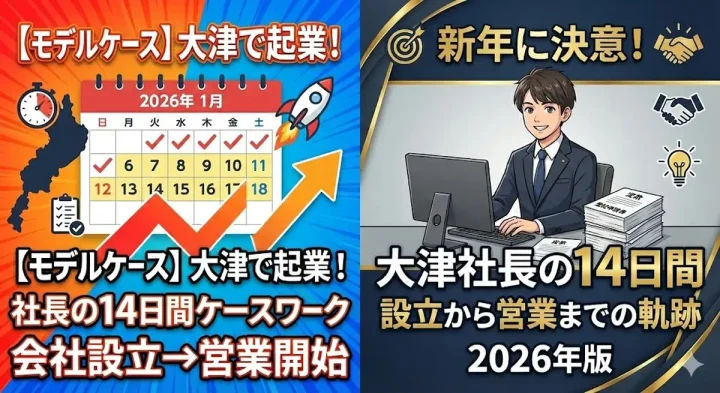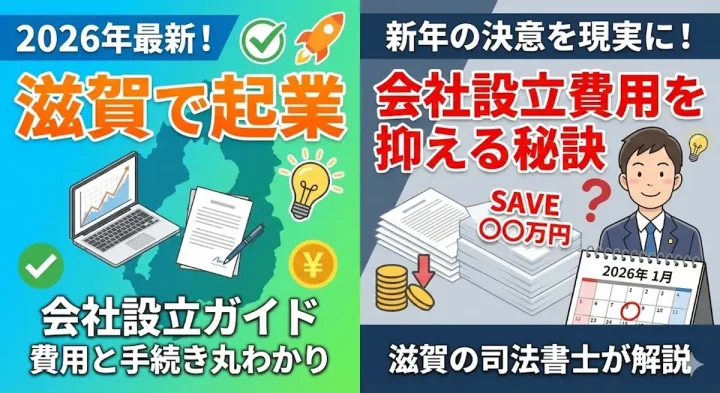役員報酬削減の法的手続きと注意点
この記事のポイント
- 役員報酬削減には適切な法的手続きと内部的プロセスが必要
- 定款規定や会社法に基づいた株主総会・取締役会の決議が不可欠
- 役員の同意取得や公平性確保など法的リスク回避のための配慮が重要
- 税務上の注意点を踏まえた計画的な実施が求められる
- 文書化と丁寧なコミュニケーションで円滑な実施を目指す
役員報酬の削減は、企業の経営状況や方針に応じて行われることがありますが、法的手続きや注意点をしっかりと理解して進めることが重要です。以下に、役員報酬削減の際の一般的な法的手続きと注意点を示します。
法的手続き
定款の確認
役員報酬の決定方法について、会社の定款に規定がある場合は、それに従う必要があります。定款には通常、以下のような規定が含まれています:
- 役員報酬を株主総会で決議すること
- 報酬総額のみを株主総会で決議し、各役員への配分は取締役会に委任すること
- 報酬の種類(基本報酬、賞与、退職慰労金など)に関する規定
重要:定款に規定がない場合は、会社法の原則に従い、株主総会での決議が必要となります。
株主総会の決議
役員報酬は通常、株主総会で決議されます。報酬の削減も同様に、株主総会での決議が必要です。定款で取締役会に委任されている場合は、取締役会の決議で行うことができます。
株主総会決議の内容例
「取締役の報酬額を年額○○百万円以内(うち社外取締役△△百万円以内)に改定する。なお、取締役の報酬額には使用人兼務取締役の使用人分の給与は含まないものとする。」
ポイント:
- 通常は年間の総額上限を決定
- 社内取締役と社外取締役の報酬枠を区分することが一般的
- 削減の場合は、新たな上限額を決議
- 普通決議(出席株主の議決権の過半数)で決定可能
取締役会の決議
取締役会で報酬の具体的な金額や削減の内容を決定します。取締役会の決議が必要な場合は、適切に議事録を作成します。
取締役会で決定する事項
- 各役員の具体的な報酬額
- 削減率または削減額
- 削減の適用時期
- 削減の期間(一時的か恒久的か)
- 特定の役員カテゴリーへの適用条件
議事録に記載すべき内容
- 開催日時・場所
- 出席取締役・監査役
- 議長の氏名
- 決議事項の具体的内容
- 決議に反対した取締役がいる場合はその氏名
- 議事の経過と結果
通知と同意
役員に対して報酬削減の内容を通知し、同意を得ることが望ましいです。特に、役員が労働者としての地位を持つ場合は、労働契約の変更として同意が必要です。
| 役員の区分 | 同意の必要性 | 法的根拠・留意点 |
|---|---|---|
| 社内取締役(使用人兼務なし) | 原則として不要だが、取得が望ましい | 委任契約関係(会社法330条) 信頼関係維持のため同意を得るのが望ましい |
| 使用人兼務取締役 | 使用人分給与の削減には同意が必要 | 労働契約関係(労働基準法) 役員報酬と使用人給与を明確に区分 |
| 社外取締役 | 原則として不要だが、取得が望ましい | 委任契約関係(会社法330条) 独立性確保の観点から丁寧な説明が必要 |
| 監査役 | 原則として不要だが、取得が望ましい | 監査の独立性に配慮 監査役会の意見聴取が望ましい |
注意点
法令遵守
会社法や労働基準法など、関連する法令を遵守することが重要です。特に以下の点に注意が必要です:
- 会社法上の手続き:定款規定と会社法の規定に従った適切な機関決定
- 労働基準法:使用人兼務取締役の使用人分給与削減は労働契約の不利益変更となる可能性
- 税法上の注意:期中での報酬変更は恣意的な課税回避と見なされるリスク
- 任期途中の削減:株主総会の決議を経ていても、個別の同意なしに大幅な削減を行うと「報酬請求権の侵害」と判断されるリスク
役員の同意
役員の同意を得ることが望ましいです。特に、役員が労働者としての地位を持つ場合は、労働契約の変更として同意が必要です。
同意取得のポイント:
- 削減の必要性や会社の状況を丁寧に説明
- 同意書を作成し署名・押印を得る
- 期間限定の削減の場合は、その旨を明記
- 使用人兼務取締役の場合、役員報酬部分と使用人給与部分を明確に区分
- 可能であれば、業績回復時の報酬復元条件も検討
同意書の記載例
「私は、○○株式会社の経営状況に鑑み、令和○年○月○日開催の取締役会において決議された役員報酬削減(月額報酬を○○円から△△円に減額)について同意します。なお、本削減は令和○年○月から令和○年○月までの期間適用されるものとします。」
公平性の確保
報酬削減が特定の役員に対して不公平にならないように注意します。役員間での不公平感は、モチベーション低下や内部対立の原因となる可能性があります。
公平性を確保するアプローチ
- 役職や責任に応じた段階的な削減率の設定
- 全役員一律の削減率の適用
- 業績連動型の報酬体系への移行
- 社外役員と社内役員の削減率の区別
削減例(役職別)
- 代表取締役社長:30%削減
- 専務・常務取締役:25%削減
- 取締役:20%削減
- 社外取締役:10%削減
- 監査役:15%削減
コミュニケーション
役員や関係者に対して、報酬削減の理由や必要性を十分に説明し、理解を得ることが重要です。
効果的なコミュニケーション方法:
- 取締役会や経営会議での丁寧な説明
- 会社の財務状況や将来見通しの共有
- 削減が一時的な措置か恒久的な措置かの明確化
- 削減により期待される効果の説明
- 必要に応じて個別面談の実施
- 株主や従業員への適切な情報開示
文書化
決議内容や役員の同意を文書化し、適切に記録を残すことが重要です。法的紛争を予防するとともに、税務調査などにも対応できるようにします。
文書化すべき書類:
- 株主総会議事録
- 取締役会議事録
- 役員報酬規程の改定版
- 役員からの同意書
- 報酬削減の通知書
- 削減の必要性を示す財務資料
税務上の観点からの文書化:
税務調査において役員報酬の恣意的な操作と見なされないよう、削減の合理的理由を示す資料(業績悪化を示す財務資料など)も保管しておくことが望ましいです。
税務上の注意点
役員報酬の削減を行う際には、税務上の取り扱いにも注意が必要です。
法人税法上の「定期同額給与」の要件
法人税法上、役員報酬は原則として「定期同額給与」であることが求められています。期中で報酬額を変更する場合、以下の要件を満たす必要があります:
- 経営状況の著しい悪化に伴う減額
単なる業績不振ではなく、「著しい悪化」と認められる状況である必要があります - 業績悪化を示す客観的な資料の保存
売上の大幅減少、赤字転落、資金繰り悪化などを示す資料が必要です - 適正な手続きによる減額
株主総会・取締役会の決議など適正な手続きを経ていること - 不当に減額後の報酬水準が低くないこと
役員としての職務内容に比して著しく低い金額に設定されていないこと
注意:上記要件を満たさない場合、期中の報酬減額は税務上認められず、当初の報酬額に基づいて損金算入の可否が判断されることがあります。
実務上のポイント
事例:製造業A社の役員報酬削減
背景:主要取引先の海外移転により売上が前年比30%減少、2四半期連続赤字に転落
対応:
- 取締役会で経営状況と報酬削減の必要性を説明
- 役員報酬の一時削減を株主総会で決議(報酬総額の上限変更)
- 役職に応じた段階的な削減率を設定(社長30%、その他取締役20%、社外取締役10%)
- 全役員から個別に同意書を取得
- 削減期間を1年間と明確に設定し、その後の見直し条件も明示
- 業績悪化を示す財務資料を保存
- 主要株主や取引金融機関への説明を実施
結果:全役員の理解と協力を得て円滑に報酬削減を実施。コスト削減効果と共に、従業員や取引先に対しても経営陣の危機意識を示すことができた。税務調査においても「経営状況の著しい悪化」による削減として認められた。
まとめ
役員報酬の削減は、企業の経営戦略や財務状況に大きく影響を与えるため、慎重に進める必要があります。法的手続きを適切に踏むことはもちろん、役員間の公平性確保、丁寧なコミュニケーション、適切な文書化が重要です。また、税務上の影響も考慮した上で計画的に実施することが求められます。
特に重要なのは、削減の必要性を関係者に十分理解してもらうことと、法的リスクを最小化するための適切な手続きです。削減が一時的な措置である場合は、回復条件も明確にしておくことで、役員のモチベーション維持にもつながります。
具体的な手続きや法的なアドバイスについては、専門の法律顧問やコンサルタントに相談することをお勧めします。状況に応じた最適な方法を選択し、円滑な報酬削減を実現しましょう。
役員報酬に関するご相談はお気軽に
役員報酬の削減や設計に関するお悩みは、当事務所までお気軽にご相談ください。法的手続きの適正化から税務上の最適化まで、幅広くサポートいたします。初回相談は無料で承っております。
■■□―――――――――――――――――――□■■
司法書士・行政書士和田正俊事務所
【住所】 〒520-2134 滋賀県大津市瀬田5丁目33番4号
【電話番号】 077-574-7772
【営業時間】 9:00~17:00
【定休日】 日・土・祝
■■□―――――――――――――――――――□■■
法人・会社に関連する記事
【ケーススタディ】大津市で新年に起業した社長の14日間|会社設立から営業開始まで密着レポート
2026年1月12日
【2026年最新】滋賀県で起業する完全ガイド|会社設立の手続きと費用を司法書士が徹底解説
2026年1月5日
事業目的を追加・変更する登記。費用と期間、必要書類
2025年11月20日