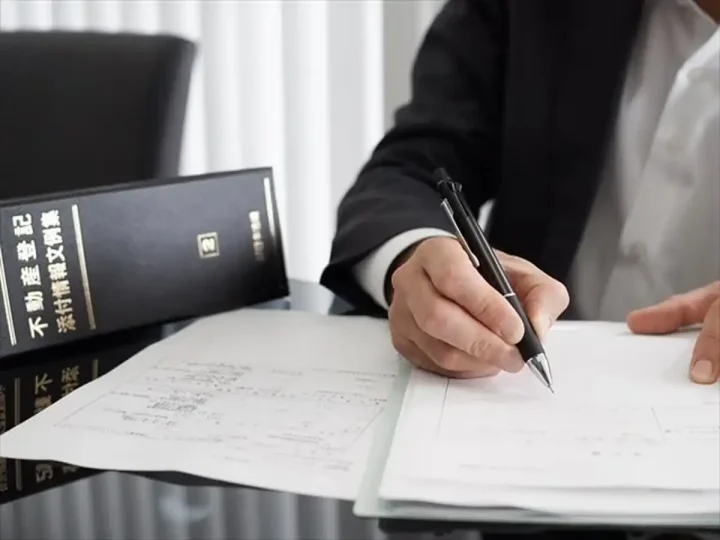最終更新日:
1. 任意後見契約関連手続きの改正について
法務省民事局から令和7年(2025年)9月8日に施行される「民法の一部を改正する法律等の施行に伴う公証事務の取扱いについて」の一部改正に関する通達が発表されました。この改正は、任意後見契約の公正証書作成および登記嘱託手続きに関わる重要な変更を含んでいます。
司法書士にとって特に重要なのは、司法書士等の専門資格者が任意後見受任者となる場合の本人確認方法が明確化されたことです。これにより手続きが効率化され、依頼者の負担軽減にもつながります。
改正のポイント:専門資格者の身分証明方法の追加、住所記載方法の変更、外国人関連手続きの現代化など、実務上重要な変更点が多数含まれています。
改正の背景と目的
高齢化社会の進展に伴い、任意後見契約の需要は年々増加しています。弁護士や司法書士などの専門家が任意後見受任者となるケースも増えていることから、従来の本人確認方法(住民票等による確認)に加えて、より効率的な確認方法が求められていました。
この改正は、手続きの合理化と時代に即した運用の実現を目的としています。特に行政手続きのデジタル化推進の流れに沿った形で、証明書類の扱いが整理されました。
適用開始時期
改正内容は令和7年(2025年)9月8日から適用されます。それまでの間は従来の手続きが継続されますが、改正の内容を先取りして準備を進めておくことが重要です。
2. 改正のポイント①:専門資格者が任意後見受任者となる場合の新たな確認方法
今回の改正で最も重要なポイントは、弁護士や司法書士などの専門資格者が職務として任意後見受任者となる場合の身分確認方法が新設されたことです。
従来の本人確認方法
従来は、任意後見受任者の氏名および住所について、住民票の写し(法人の場合は登記事項証明書)の提出が必須でした。これは専門資格者であっても例外なく求められていました。
新設された証明方法
改正後は、弁護士、司法書士等の専門資格者がその職務として任意後見受任者となる場合、任意後見受任者の氏名または住所については、以下の書類で確認することが可能になります:
- 当該専門資格者の所属する団体が発行する証明書
- その他の証明書類(詳細は今後通知予定)
注意点:日本司法書士会連合会からの通知によると、具体的な証明書の内容については現在確認中とのことで、後日詳細が通知される予定です。
戸籍上の氏名と職務上の氏名の併記
証明書に戸籍上の氏名と職務上の氏名が併記されている場合は、公正証書には戸籍上の氏名に続けて職務上の氏名を括弧書きで併せて記載することが相当とされています。これは実務上よく生じる旧姓使用の場合などに対応するものです。
3. 改正のポイント②:記載事項・様式の変更
住所の記載方法の変更点
従来は「住民票上の住所地」と明記されていましたが、改正後は単に「住所」と表現されています。ただし、本人及び任意後見受任者の住民票上の住所地が現住所と異なる場合は、両者を併記するという原則は維持されています。
外国人に関する表記の変更
外国人の居住地確認に関する表記が現代化されました:
| 改正前 | 改正後 |
|---|---|
| 外国人登録証明書、外国人登録上の居住地 | 在留カード、特別永住者証明書等 |
これは、2012年の外国人登録法廃止に伴う在留管理制度の変更を反映したものです。
公正証書様式に関する規定の整理
公正証書の用紙に関する規定(日本産業規格B列4番の丈夫な紙とする等)が削除されました。これは、公証人法施行規則の一般規定に委ねることとしたためです。
4. 改正のポイント③:その他の手続き変更
登記嘱託書の様式
登記嘱託書の様式も一部変更され、より明確な記載方法が示されています。特に「フリガナ」欄が明示的に設けられ、氏名にはフリガナを付すことが明確化されました。
登記手数料に関する条文番号の変更
登記手数料については、金額(1件につき2,600円)に変更はありませんが、根拠条文が「登記手数料令第17条第1項」から「登記手数料令第16条第1項」に変更されています。
登記手数料の納付方法(収入印紙を登記の嘱託書に貼付)については変更ありません。
5. 司法書士が任意後見受任者となる場合の実務対応
必要となる準備と書類
司法書士が任意後見受任者となる場合、改正後は日本司法書士会連合会が発行する証明書等を活用できるようになります。ただし、具体的な証明書の内容については今後の通知を待つ必要があります。
当面は次の準備が望ましいでしょう:
- 司法書士会の会員証の有効期限確認
- 職印証明書の更新
- 戸籍上の氏名と職務上の氏名が異なる場合の確認資料準備
依頼者への説明ポイント
任意後見契約締結を検討している依頼者に対しては、次の点をしっかり説明しておくことが重要です:
- 2025年9月の制度変更の概要
- 公正証書作成時に必要となる書類
- 登記手続きの流れと費用
- 任意後見契約と法定後見の違い
6. 任意後見契約制度の基本と今後の動向
任意後見契約制度の概要(復習)
任意後見契約とは、本人が判断能力が不十分になった場合に備えて、あらかじめ自らが選んだ任意後見人に、自分の生活、療養看護や財産管理に関する事務について代理権を与える契約です。この契約は公正証書による作成が必須とされています。
高齢社会における任意後見制度の重要性
日本の高齢化率は世界最高水準に達し、認知症高齢者の数も増加しています。このような社会背景から、自己決定権を尊重する任意後見制度の重要性は今後ますます高まるでしょう。
任意後見制度は「将来の自分を守るための制度」という視点から、相続対策や資産管理と併せて提案することが効果的です。
今後予想される制度変更の展望
成年後見制度全体としては、利用促進に向けた様々な取り組みが進んでいます。今後も手続きの効率化やデジタル化、中核機関の整備などが進むことが予想されます。司法書士は、これらの動向を注視し、適切な助言ができるよう準備しておくことが重要です。
7. まとめ:実務上の注意点と対応策
今回の改正は、専門家が任意後見受任者となる場合の手続きを合理化するもので、実務に大きな影響をもたらします。以下のポイントを押さえておきましょう:
- 専門資格者証明制度の詳細については、日本司法書士会連合会からの続報を待つこと
- 公正証書作成の際の本人・受任者確認書類の変更点を理解しておくこと
- 戸籍上の氏名と職務上の氏名の併記方法に注意すること
- 登記嘱託書の様式変更に対応すること
滋賀県・大津市での相談窓口のご案内
任意後見契約や相続対策に関するご相談は、当事務所でも承っております。滋賀県大津市を中心に、親切・丁寧な対応を心がけております。特に高齢者の方の権利擁護や財産管理に関するご相談は、お気軽にお問い合わせください。
また、滋賀県司法書士会では任意後見制度に関する相談会も定期的に開催されています。制度改正の最新情報も含め、専門家による適切なアドバイスを受けることができます。
◇ 当サイトの情報は執筆当時の法令に基づく一般論であり、個別の事案には直接適用できません。
◇ 法律や情報は更新されることがあるため、専門家の確認を推奨します。
◇ 当事務所は情報の正確性を保証せず、損害が生じた場合も責任を負いません。
◇ 情報やURLは予告なく変更・削除されることがあるため、必要に応じて他の情報源もご活用ください。
この記事を書いた人

司法書士・行政書士 和田正俊事務所 代表和田 正俊(Wada Masatoshi)
- 滋賀県司法書士会所属 登録番号 滋賀第441号
- 簡裁訴訟代理関係業務 認定番号 第1112169号
- 滋賀県行政書士会所属
登録番号 第13251836号会員番号 第1220号 - 公益社団法人 成年後見センター・リーガルサポート滋賀支部所属
会員番号 第6509213号
後見人候補者名簿 及び 後見監督人候補者名簿 搭載 - 法テラス契約司法書士
- 近畿司法書士会連合会災害相談員
法改正・時事情報に関連する記事
令和8年4月施行・住所変更登記の義務化とは?~改正不動産登記法のポイントと実務対応~
2025年12月4日
【2025年改正解説】供託金払渡し時の印鑑証明書添付義務が緩和されました
2025年12月3日
紙からデジタルへ!「電子署名」は実印を超える?法的有効性と司法書士が使う電子証明書
2025年12月15日