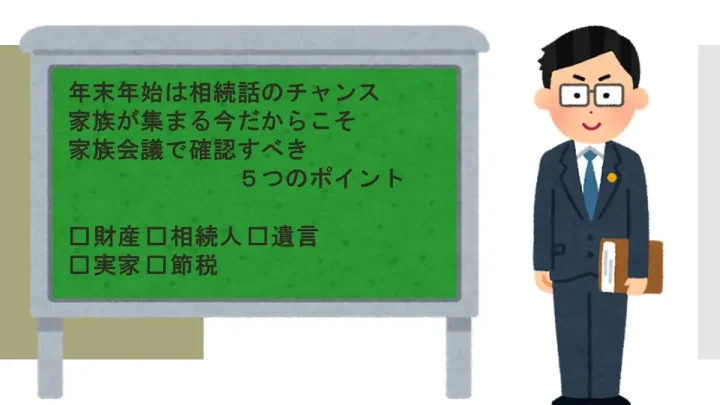未成年者がいる場合の相続費用比較 - 遺言書の有無による違い
相続が発生したとき、遺言書の有無により相続手続きの費用が大きく異なることをご存知でしょうか。特に相続人に未成年者がいる場合、その差は顕著になります。
「あのとき一筆書いておいてもらえれば...」という後悔の声は、当事務所での相続相談でよく聞かれます。しかし、一生のうちにそう何度もない相続の費用や、自分が亡くなった後の状況を想像するのは難しいものです。
このページでは、実際のケーススタディを通じて、遺言の有無による相続費用の違いを具体的な金額でご紹介します。将来の相続対策の参考にしていただければ幸いです。

ケーススタディ: 未成年の子どもがいる相続のシミュレーション
想定事例
- 被相続人: 40歳の夫が突然死亡
- 相続人: 妻36歳、長子10歳、次子6歳
- 相続財産: 土地600万円、建物400万円の計1,000万円(評価額)
- 相続方針: 妻が不動産を単独で相続したい
注目ポイント: 相続人に未成年者(子ども)が含まれているため、遺言がない場合は特別な手続きが必要になります。
遺言の有無による相続費用比較表
| 費用項目 | 遺言がない場合 | 自筆証書遺言がある場合 | 公正証書遺言がある場合 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 公証役場の費用 | 0円 | 0円 | 28,000円 | 遺産総額1,000万円の場合 |
| 当事務所での遺言作成費用 ※ | 0円 | 10,000円 | 40,000円 | 基本料金のみの場合 |
| 遺言書の検認申立 ※ | 0円 | 30,000円 | 0円 | 自筆証書遺言のみ必要 |
| 相続登記の費用 ※ | 38,000円 | 38,000円 | 38,000円 | 筆数、評価額により変動 |
| 登録免許税 | 40,000円 | 40,000円 | 40,000円 | 評価額1,000万円の0.4% |
| 遺産分割協議書の作成 ※ | 12,500円 | 0円 | 0円 | 遺言があれば不要 |
| 相続関係説明図の作成 ※ | 12,500円 | 12,500円 | 12,500円 | 1親等間の相関図 |
| 特別代理人選任申立 ※ | 56,000円 | 0円 | 0円 | 1人目35,000円、追加1人21,000円 |
| 特別代理人報酬 | 0円~ | 0円 | 0円 | 弁護士選任時は別途費用発生 |
| その他諸費用 | 約10,000円 | 約10,000円 | 約10,000円 | 戸籍取得費用、送料など |
| 合計 | 169,000円~ | 140,500円 | 168,500円 | |
| 補足 | 特別代理人の選任は家庭裁判所の決定による(不確定要素あり) | 遺言書作成指導のみの費用 | 遺言書の起案・打ち合わせ・証人立会いを含む |
※印がついているものは、当事務所の報酬に相当する部分です。
◎ 費用は想定例であり、実際の相続費用は手続内容や遺産の内容により異なります。
◎ 本費用例には消費税等は含まれておりません。費用発生時の税法に従い、税金が発生します。
◎ 本費用例はあくまでも参考としてお考えください。
遺言なし
169,000円~
特別代理人報酬が別途必要になる
可能性があります
自筆証書遺言あり
140,500円
最も費用が抑えられる
選択肢です
公正証書遺言あり
168,500円
法的安定性が高く
検認不要のメリット
ケーススタディの解説:未成年者がいる場合の特殊事情
このケーススタディでは、40歳の夫が突然の事故や病気で亡くなり、36歳の妻と10歳と6歳の子どもが相続人となった状況を想定しています。相続財産は土地と建物(評価額合計1,000万円)のみで、住宅ローンは団体信用生命保険で完済されています。
妻は将来の生活費や子どもの学費確保のための銀行借入れの担保として、また不動産の管理・売却・賃貸などの活用を考え、不動産を単独で相続することを希望しています。
ここで問題となるのが、相続人に未成年者(子ども)が含まれている点です。
遺言がない場合、法定相続分に従い、妻が2分の1、子どもたちがそれぞれ4分の1ずつ相続することになります。全財産を妻に相続させるためには、子どもたちの法定相続分を放棄する形での遺産分割協議が必要になります。
しかし、未成年者は自分で法律行為(相続放棄や遺産分割協議への参加)ができないため、家庭裁判所に特別代理人選任の申立てが必要になります。これが遺言なしの場合に費用が高くなる主な理由です。

特別代理人選任が必要な理由
民法では、親権者(この場合は母親)と子どもの間で利益相反する場合、親権者は子どもを代理できないと定められています。遺産分割協議では、母親は「全財産を自分が取得したい」、子どもは「法定相続分を取得したい」という利益相反の関係が生じるため、子どもの権利を守るために第三者(特別代理人)が必要になるのです。
特別代理人は家庭裁判所によって選任され、弁護士など法律の専門家が選任されると別途報酬が発生する可能性があります。この報酬額は案件の複雑さによって変動するため、事前に正確な総額を見積もることが困難です。
遺言書を残すメリット - 未成年の子どもがいる場合
費用削減
特別代理人選任申立てが不要となり、費用を大幅に削減できます。特に自筆証書遺言の場合、トータルコストを最も抑えられます。
手続きの簡素化
遺産分割協議が不要となり、相続手続きが大幅に簡素化されます。特に公正証書遺言の場合、検認も不要でスムーズに手続きが進みます。
時間短縮
家庭裁判所への申立てや審理を待つ必要がなく、相続手続きの期間が大幅に短縮されます。突然の出費が必要な時にも迅速に対応できます。
不確定要素の排除
特別代理人の選任や報酬といった不確定要素がなくなり、相続手続きの費用を事前に正確に把握することができます。
精神的負担の軽減
配偶者の突然の死に対応しながら、複雑な裁判所手続きを行う必要がなく、残された家族の精神的負担を軽減できます。
確実な意思の実現
自分の望む形で財産を分配できることが保証され、未成年の子どもがいる場合も確実に配偶者の生活基盤を確保できます。
当事務所の遺言・相続サポート
当事務所では、お客様のご意向を確実に実現するため、以下のような遺言・相続に関するサポートを提供しております:
- 遺言の作成支援:最適な遺言の形式や内容についてアドバイス
- 遺言書の起案作成:法的要件を満たした適切な文言での遺言書作成
- 遺言内容の法的検討:遺留分や特別受益など法律上の問題点のチェック
- 公証役場との調整:公正証書遺言作成時の公証人との事前打ち合わせ
- 公正証書遺言の証人:公正証書遺言作成時の証人としての立会い
- 遺言書の保管:自筆証書遺言の安全な保管サービス
- 遺言の執行:遺言執行者としての役割の遂行
- 相続登記の申請:相続不動産の名義変更手続き
- 遺産分割協議書の作成:法的に有効な遺産分割協議書の作成
- 特別代理人選任申立:必要な場合の家庭裁判所への申立て支援
その他にも、お客様の個別のご事情やご要望に応じたサポートを提供しております。どんな小さなことでもお気軽にご相談ください。

遺言書作成・相続手続きでお悩みの方はお気軽にご相談ください
未成年の子どもがいる場合の相続は特に複雑です。事前の対策で将来の負担を軽減しましょう。初回相談30分は無料です。
司法書士・行政書士和田正俊事務所
電話番号:077-574-7772(平日9:00〜17:00)
住所:〒520-2134 滋賀県大津市瀬田5丁目33番4号
相続に関する関連情報
当事務所では、相続に関する様々な情報を発信しています。以下のページもぜひご参考ください。
相続についてのページ
遺言書の種類と特徴
自筆証書遺言
メリット
- 費用が安い(紙と筆記用具があれば作成可能)
- いつでも手軽に作成・変更できる
- プライバシーが保たれる
デメリット
- 形式不備で無効になるリスクがある
- 紛失・偽造・変造のリスクがある
- 家庭裁判所での検認手続きが必要
10,000円~
公正証書遺言
メリット
- 公証人が関与するため法的安全性が高い
- 原本は公証役場で保管され紛失リスクがない
- 検認手続きが不要
デメリット
- 費用がかかる(公証人手数料+証人費用)
- 公証役場での手続きが必要
- 証人2名が必要
68,000円~
令和2年7月10日施行の新制度:自筆証書遺言保管制度
法務局で自筆証書遺言を保管する制度が始まりました。この制度を利用すると、以下のメリットがあります:
- 遺言書の紛失・亡失・偽造・変造を防止できる
- 家庭裁判所での検認手続きが不要になる
- 相続人等が法務局で遺言書の有無を確認できる
保管手数料:3,900円(財産目録をPDFで添付する場合は別途700円)
ご依頼までの流れ
初回無料相談(30分)
お電話(077-574-7772)またはメールにてご予約の上、ご来所ください。ご事情をお伺いし、適切な対応策をご提案いたします。
ご依頼・お見積り
サービス内容と費用をご説明し、ご納得いただいた上でご依頼を承ります。費用は案件の複雑さにより異なりますが、明確にご説明いたします。
必要書類の収集・準備
相続関係や財産状況を確認するための書類を収集します。お客様ご自身で収集いただくか、当事務所での代行も可能です。
手続きの実施
遺言書作成支援や相続手続きを進めます。途中経過は随時ご報告し、必要に応じて公証役場への同行も行います。
完了・アフターフォロー
手続き完了後も、必要に応じたアドバイスやフォローアップを行います。将来の不安やご質問にもお応えします。
まとめ:事前の遺言準備で将来の負担を軽減
今回のケーススタディでは、未成年の子どもがいる場合の相続において、遺言書の有無が手続きの複雑さと費用に大きな影響を与えることが明らかになりました。特に以下のポイントを押さえておきましょう:
- 遺言書がない場合:未成年者のために特別代理人選任申立てが必要となり、費用も手間も増大します。
- 自筆証書遺言がある場合:費用面では最も経済的で、手続きも簡素化されます。ただし、形式不備に注意が必要です。
- 公正証書遺言がある場合:法的安全性が高く、検認不要というメリットがあります。費用は比較的高めですが、手続きの確実性を重視する方におすすめです。
「まさか自分が…」と思われるかもしれませんが、特に小さなお子様がいらっしゃるご家庭では、万一に備えた遺言書の準備が家族を守る重要な対策となります。当事務所では、お客様のご状況に合わせた最適な遺言書作成のサポートを行っております。
司法書士・行政書士和田正俊事務所
住所:〒520-2134 滋賀県大津市瀬田5丁目33番4号
電話番号:077-574-7772
営業時間:9:00~17:00
定休日:日・土・祝
相続・財産管理に関連する記事
【お正月限定】親族会議で必ず決めるべき相続の5項目|滋賀の司法書士が教える円満解決法2026
2025年12月26日
年末年始の帰省で話し合いたい相続の話:家族会議で確認すべき5つのポイント
2025年12月12日
遺言書作成のポイント|自筆・公正証書どちらがよい?比較&事例紹介
2025年12月12日