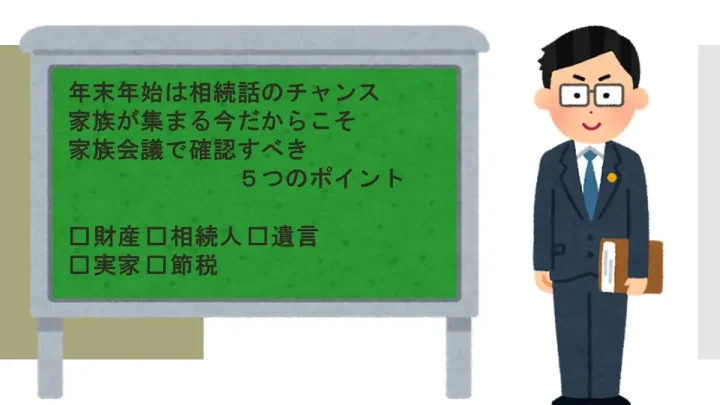子供のいない夫婦の相続費用 - 遺言書の有無による衝撃的な差
相続が発生したとき、遺言書の有無により相続手続きの費用が劇的に異なることをご存知でしょうか?特に子供がおらず、配偶者と兄弟姉妹が相続人となる場合、その差は驚くほど大きくなります。
「あのとき一筆書いておいてもらえれば...」という後悔の声は、当事務所での相談でよく耳にします。本記事では、実際のケーススタディを通じて、遺言の有無による相続費用の違いを具体的な金額でご紹介します。将来の相続対策の参考にしていただければ幸いです。

ケーススタディ: 子供のいない高齢夫婦の相続問題
想定事例
- 被相続人: 86歳の夫が死亡
- 相続人: 妻80歳、妹82歳(子供はいない)
- 相続財産: 土地600万円、建物400万円の計1,000万円(評価額)
- 相続方針: 妻が自宅不動産を継続して使用したい
注目ポイント: 兄弟姉妹には遺留分がありませんが、法定相続分(財産の1/4)は主張できます。
兄弟姉妹が相続人の場合の法定相続分
民法で定められた法定相続分
子供がいない場合の法定相続分は以下のとおりです:
3/4
配偶者は常に相続人となり、優先的に保護されます
1/4
兄弟姉妹には遺留分がないため、遺言で除外可能
遺言がなければ、兄弟姉妹は法定相続分を主張できます
遺言の有無による相続費用比較表
| 費用項目 | 遺言がない場合 | 自筆証書遺言がある場合 | 公正証書遺言がある場合 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 公証役場の費用 | 0円 | 0円 | 28,000円 | 遺産総額1,000万円の場合 |
| 当事務所での遺言作成費用 ※ | 0円 | 10,000円 | 40,000円 | 基本料金のみの場合 |
| 遺言書の検認申立 ※ | 0円 | 30,000円 | 0円 | 自筆証書遺言のみ必要 |
| 相続登記の費用 ※ | 38,000円 | 38,000円 | 38,000円 | 筆数、評価額により変動 |
| 登録免許税 | 40,000円 | 40,000円 | 40,000円 | 評価額1,000万円の0.4% |
| 相続関係説明図の作成 ※ | 12,500円 | 12,500円 | 12,500円 | 2親等間の相関図 |
| 家事調停申立 ※ | 50,000円 | 0円 | 0円 | 調停申立書・陳述書作成 |
| 家事代理人への報酬 | 150,000円~ | 0円 | 0円 | 弁護士費用(着手金・報酬) |
| 妹に対する遺産の分配額 | 100万円~ | 0円 | 0円 | 調停での交渉結果による |
| その他諸費用 | 約15,000円 | 約15,000円 | 約15,000円 | 戸籍取得費用、送料など |
| 合計 | 130万円~ | 145,500円 | 173,500円 | |
| 補足 | 調停内容により費用は大きく変動します | 遺言書作成指導のみの費用 | 遺言書の起案・打ち合わせ・証人立会いを含む |
※印がついているものは、当事務所の報酬に相当する部分です。
◎ 費用は想定例であり、実際の相続費用は手続内容や遺産の内容により異なります。
◎ 本費用例には消費税等は含まれておりません。費用発生時の税法に従い、税金が発生します。
◎ 本費用例はあくまでも参考としてお考えください。
遺言なし
130万円~
調停費用・弁護士費用・遺産分配額を
含む総額
自筆証書遺言あり
145,500円
遺言書の費用を含めても
大幅な節約に
公正証書遺言あり
173,500円
検認不要で安全性が高い
遺言方式
ケーススタディの解説:兄弟姉妹が相続人の場合の問題点
このケーススタディでは、86歳の夫が亡くなり、80歳の妻と82歳の夫の妹が相続人となった状況を想定しています。相続財産は夫婦の自宅(土地と建物、評価額合計1,000万円)のみです。
遺言がなかったため、妻は夫の妹に連絡を取って遺産分割協議を行おうとしましたが、妹は「法定相続分(1/4)をもらいたい」と主張しました。しかし、相続財産は自宅の不動産しかなく、これを売却しないと妹に現金で相続分を渡すことができません。
ここで深刻な問題が発生します:
- 自宅を売却すると妻の住む場所がなくなる
- 高齢の妻が新たに住居を購入・賃借するのは困難
- 不動産を共有名義にすると将来的な管理や処分で問題が生じる可能性がある
協議がまとまらず、最終的に家庭裁判所への調停申立てが必要になりました。調停では、妻側が弁護士を代理人として立て、「夫婦が共同で築いた財産であること」などを主張。結果として妹への分配額を法定相続分(250万円)より減額した100万円とする合意に至ったと想定しています。

遺言がない場合の深刻な影響
- 経済的損失:調停費用、弁護士費用、兄弟姉妹への分配金を合わせると、遺言を残すコストの約10倍になることも
- 時間的負担:調停は数ヶ月から1年以上かかることもあり、その間ずっと相続問題に時間を取られる
- 精神的負担:配偶者を亡くした悲しみの中、法的手続きや兄弟姉妹との交渉に追われる精神的ストレス
- 関係悪化:兄弟姉妹との関係が悪化し、家族の絆が壊れることも
これらすべての問題は、生前に遺言書を作成しておくことで防ぐことができます。
重要ポイント:兄弟姉妹には「遺留分」がない
遺言があれば兄弟姉妹を相続から除外できる
民法では、配偶者・子・親には遺留分(最低限保障される相続分)が認められていますが、兄弟姉妹には遺留分がありません。
遺言がない場合
- 兄弟姉妹は法定相続分(1/4)を主張できる
- 配偶者は協議か調停・審判で解決を図る必要がある
- 不動産のみの場合、売却や共有という選択を迫られる
遺言がある場合
- 「すべての財産を配偶者に相続させる」旨の遺言で完結
- 兄弟姉妹は遺留分がないため異議申立てはできない
- 調停・裁判などの法的手続きは不要
子供がいない夫婦は特に、お互いに遺言を残すことが重要です
遺言書を残すことで得られるメリット
経済的メリット
遺言書作成費用(約1〜5万円)を投資することで、将来的に100万円以上の費用を節約できる可能性があります。特に子供がいない夫婦の場合、投資対効果は絶大です。
配偶者の生活保障
自宅に住み続けられることを保証し、高齢配偶者の住居問題を防ぎます。長年連れ添った伴侶の老後の安心を確保できます。
手続きの簡素化
調停や裁判といった煩雑な法的手続きが不要になり、相続手続きがスムーズに進みます。残された配偶者の負担を大幅に軽減できます。
家族関係の維持
相続をめぐる争いを未然に防ぎ、家族・親族間の良好な関係を維持できます。金銭的トラブルで家族の絆が壊れることを防止します。
精神的な安心
自分の死後、大切な人が困らないよう準備することで得られる安心感は計り知れません。遺言は「最後の愛の表現」とも言えます。
相続の明確化
「誰に何を相続させたいか」を明確に示すことで、自分の意思を確実に実現できます。特に子供がいない場合、遺言なしでは法定相続が複雑になります。
子供のいない夫婦の相続対策 - 推奨される方法
子供がいないご夫婦の場合、お互いのために最適な相続対策を講じることが特に重要です。以下に、当事務所が推奨する具体的な対策をご紹介します。
1. 夫婦それぞれが遺言書を作成する
夫婦お互いに「全財産を配偶者に相続させる」旨の遺言書を作成することが最も効果的です。どちらが先に亡くなっても、残された配偶者の生活が守られます。
2. 公正証書遺言の活用
特に高齢の方や認知症リスクがある方は、法的安全性が高く検認不要の公正証書遺言をお勧めします。当事務所では公正証書遺言作成の全プロセスをサポートしています。
3. 配偶者居住権の活用
2020年の民法改正で創設された「配偶者居住権」を活用すると、残された配偶者が自宅に住み続ける権利を確保しつつ、財産の一部を他の相続人に分配することも可能です。
4. 生前贈与の検討
生前に夫婦間で居住用不動産の共有化や贈与を行うことで、相続時の問題を軽減できる場合があります。贈与税の配偶者控除(2,000万円まで非課税)も活用できます。

遺言書の種類と特徴
自筆証書遺言
メリット
- 費用が安い(紙と筆記用具があれば作成可能)
- いつでも手軽に作成・変更できる
- プライバシーが保たれる
デメリット
- 形式不備で無効になるリスクがある
- 紛失・偽造・変造のリスクがある
- 家庭裁判所での検認手続きが必要
10,000円~
公正証書遺言
メリット
- 公証人が関与するため法的安全性が高い
- 原本は公証役場で保管され紛失リスクがない
- 検認手続きが不要
デメリット
- 費用がかかる(公証人手数料+証人費用)
- 公証役場での手続きが必要
- 証人2名が必要
68,000円~
令和2年7月10日施行の新制度:自筆証書遺言保管制度
法務局で自筆証書遺言を保管する制度が始まりました。この制度を利用すると、以下のメリットがあります:
- 遺言書の紛失・亡失・偽造・変造を防止できる
- 家庭裁判所での検認手続きが不要になる
- 相続人等が法務局で遺言書の有無を確認できる
保管手数料:3,900円(財産目録をPDFで添付する場合は別途700円)
当事務所の遺言・相続サポート
当事務所が提供するサービス
和田正俊事務所では、お客様の状況に合わせた最適な遺言・相続サポートを提供しております:
遺言書作成支援
- 遺言書の内容・文言についてのアドバイス
- 法的に有効な遺言書の起案・作成
- 遺言の要件確認と法的リスクのチェック
- 公証役場との打ち合わせ・調整
- 公正証書遺言作成時の証人としての立会い
相続手続きサポート
- 遺言の執行・相続財産の名義変更
- 相続登記の申請手続き
- 遺産分割協議書の作成
- 戸籍・住民票等の必要書類収集
- 家事調停申立書・提出書類の作成
- 法定相続情報証明制度の活用
その他のサポート
- 遺言書の保管サービス
- 遺産分割方法のシミュレーション
- 相続税の基本的なアドバイス(※詳細は税理士と連携)
- 成年後見制度の活用提案
- 生前贈与の法的アドバイス
- 不動産の共有持分の整理
ご依頼までの流れ
初回無料相談(30分)
お電話(077-574-7772)またはメールにてご予約の上、ご来所ください。ご事情をお伺いし、適切な対応策をご提案いたします。
ご依頼・お見積り
サービス内容と費用をご説明し、ご納得いただいた上でご依頼を承ります。費用は案件の複雑さにより異なりますが、明確にご説明いたします。
必要書類の収集・準備
相続関係や財産状況を確認するための書類を収集します。お客様ご自身で収集いただくか、当事務所での代行も可能です。
手続きの実施
遺言書作成支援や相続手続きを進めます。途中経過は随時ご報告し、必要に応じて公証役場への同行も行います。
完了・アフターフォロー
手続き完了後も、必要に応じたアドバイスやフォローアップを行います。将来の不安やご質問にもお応えします。
まとめ:子供のいない夫婦は必ず遺言を
今回のケーススタディから明らかなように、子供がいない夫婦の場合、遺言書の有無により相続手続きの費用と労力に劇的な差が生じます。
遺言がない場合のリスク
兄弟姉妹が法定相続分(1/4)を主張すると、居住用不動産が唯一の財産の場合、残された配偶者は:
- 家庭裁判所での調停・審判という法的手続きに直面
- 弁護士費用や調停費用の経済的負担
- 兄弟姉妹への分配金の支払いが必要
- 最悪の場合、自宅の売却を迫られる可能性も
遺言書作成の効果
一方、数万円の遺言書作成費用を投資するだけで:
- 配偶者が安心して自宅に住み続けられる
- 兄弟姉妹への分配金・調停費用・弁護士費用など100万円以上の費用節約
- 相続をめぐる争いや法的手続きの精神的・時間的負担から解放
- 家族・親族間の良好な関係維持
「万一の場合に備えて」という言葉がありますが、相続は誰にでも必ず訪れるものです。
特に子供のいないご夫婦は、お互いのために今すぐ遺言書の準備を始めましょう。
相続・遺言書作成のご相談は和田正俊事務所へ
子供のいないご夫婦の相続対策は特に重要です。将来の不安を今すぐ解消しませんか?初回相談30分は無料です。
司法書士・行政書士和田正俊事務所
電話番号:077-574-7772(平日9:00〜17:00)
住所:〒520-2134 滋賀県大津市瀬田5丁目33番4号
相続に関する関連情報
当事務所では、相続に関する様々な情報を発信しています。以下のページもぜひご参考ください。
相続についてのページ
司法書士・行政書士和田正俊事務所
住所:〒520-2134 滋賀県大津市瀬田5丁目33番4号
電話番号:077-574-7772
営業時間:9:00~17:00
定休日:日・土・祝
相続・財産管理に関連する記事
【お正月限定】親族会議で必ず決めるべき相続の5項目|滋賀の司法書士が教える円満解決法2026
2025年12月26日
年末年始の帰省で話し合いたい相続の話:家族会議で確認すべき5つのポイント
2025年12月12日
遺言書作成のポイント|自筆・公正証書どちらがよい?比較&事例紹介
2025年12月12日