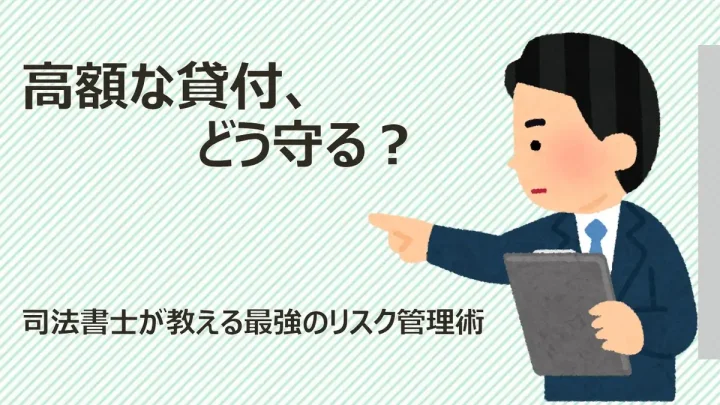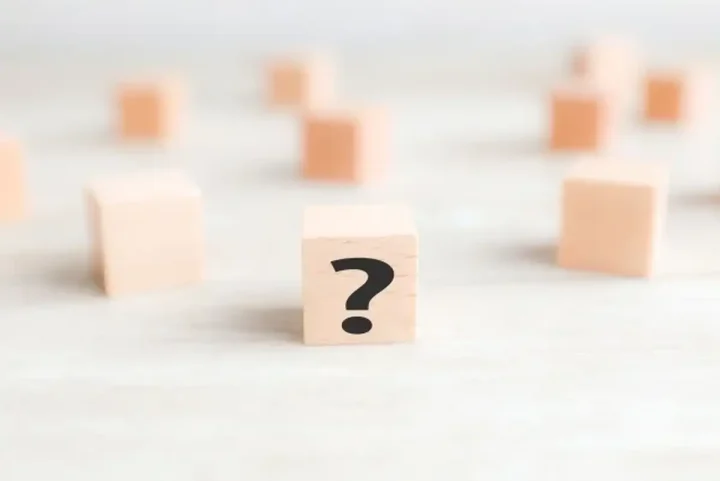共有名義とは?基本的な概念

共有名義とは、一つの不動産を複数の人が共同で所有することを意味します。不動産登記簿上では「共有者」として記載され、それぞれの所有割合(持分)が明記されます。
共有名義の特徴は以下の通りです:
- 一つの不動産に対して複数の所有者が存在する
- 各共有者は持分(所有割合)を持つ
- 共有者全員の同意なしに不動産全体の処分はできない
- 共有者はそれぞれの持分を自由に処分できる
共有名義と区分所有の違い
マンションなどでよく見られる「区分所有」は共有とは異なります。区分所有では、専有部分(各部屋)と共用部分(廊下・エレベーターなど)が分かれていますが、共有名義では不動産全体を共同で所有します。【例】 ・共有名義:山田太郎と佐藤花子が一軒家を共有(それぞれ2分の1ずつ所有)・区分所有:マンションの一室を単独所有し、共用部分を区分所有者全員で共有
滋賀県で多い共有名義の不動産パターン
滋賀県では、以下のような共有名義の不動産パターンがよく見られます:
1. 琵琶湖周辺の別荘地
琵琶湖周辺、特に高島市や大津市北部のリゾート地では、家族や親族間で別荘を共有するケースが多くあります。維持費や税金の負担を分散する目的で選ばれることが多いです。
2. 相続による共有
相続発生後、遺産分割協議が整わない場合や、あえて分割せずに共有のまま保有するケースが増えています。特に滋賀県の農村部では先祖代々の土地を分割せず共有で継承するケースが見られます。
3. 夫婦間での共有
住宅ローンを共同で組む際など、夫婦で共有名義にするケースが増加傾向にあります。特に共働き世帯が多い草津市や大津市などの都市部で顕著です。
4. 投資用不動産の共有
近年、滋賀県内でも投資用不動産を複数人で共有するケースが増えています。特にJR沿線の駅周辺物件などでこの傾向が見られます。
共有名義のメリット・デメリット
メリット
1. 購入・維持コストの分散
不動産の購入費用や維持管理費を複数人で分担できるため、経済的負担が軽減されます。特に琵琶湖周辺の別荘などでは、季節ごとの利用と合わせてコスト分散のメリットが大きいです。
2. 相続対策としての活用
生前に子どもたちに持分を分けておくことで、将来の相続手続きを簡略化できることがあります。滋賀県内でも事業承継や相続対策として活用されるケースが増えています。
3. リスク分散
投資用不動産を共有することで、一人あたりの投資リスクを軽減できます。
デメリット
1. 意思決定の複雑化
共有者全員の合意が必要なため、売却や大規模な改修などの意思決定が複雑になります。特に共有者間で意見が分かれると、不動産の有効活用が難しくなることも。
2. 持分の処分制限
自分の持分のみを売却しようとしても、買い手が見つかりにくいという問題があります。
3. 共有者間のトラブルリスク
利用方法や維持管理、費用負担などをめぐって共有者間でトラブルが発生するリスクがあります。滋賀県内でも、別荘の利用権や農地の管理をめぐる共有者間トラブルの相談が増えています。
4. 固定資産税の支払い管理
共有者間で固定資産税の支払いをどう分担するかを決めておく必要があります。滋賀県内の市町村では、原則として納税通知書は代表者宛てに送付されます。
共有持分の意味と表記方法
共有持分とは、共有不動産における各所有者の権利割合のことです。登記簿には分数で表記されます。
持分の表記例
【例1】夫婦で均等に共有する場合 甲区(所有者)欄: 山田太郎 持分 2分の1 山田花子 持分 2分の1 【例2】3人で不均等に共有する場合 甲区(所有者)欄: 佐藤一郎 持分 5分の2 佐藤二郎 持分 5分の2 佐藤三郎 持分 5分の1
持分の決め方
持分は共有者間の協議で自由に決めることができます。一般的には以下のような基準で決められることが多いです:
- 出資額に応じた割合
- 家族構成に応じた割合
- 均等割り
- 将来の相続を見据えた割合
滋賀県内でも、家族構成や出資額に応じて様々な持分割合のケースがありますが、夫婦間では「2分の1ずつ」とする例が最も一般的です。
共有名義にするための登記手続き
1. 新規に購入する場合の共有名義登記
新しく不動産を購入し、最初から共有名義にする場合の手続きです。
手続きの流れ
- 売買契約書に共有者全員の氏名と持分を明記
- 必要書類を準備(詳細は後述)
- 法務局に所有権移転登記を申請
- 登録免許税を納付
- 登記完了
申請先
滋賀県内の不動産の場合は、所在地を管轄する法務局に申請します:
- 大津地方法務局(大津市、草津市、栗東市、守山市、野洲市)
- 大津地方法務局甲賀支局(甲賀市、湖南市)
- 大津地方法務局彦根支局(彦根市、犬上郡(豊郷町、甲良町、多賀町)、愛荘町)
- 大津地方法務局長浜支局(長浜市、米原市)
- 大津地方法務局高島出張所(高島市)
- 大津地方法務局東近江出張所(東近江市、近江八幡市、蒲生郡(日野町、竜王町))
2. 既に所有している不動産を共有名義に変更する場合
単独所有の不動産の一部を他の人に譲渡し、共有名義にする場合の手続きです。
手続きの流れ
- 持分の移転方法を決定(売買、贈与など)
- 共有持分の割合を決定
- 移転の契約書を作成
- 必要書類を準備
- 法務局に所有権の一部移転登記を申請
- 登録免許税を納付
- 登記完了
3. 必要書類と費用
必要書類
共有名義の登記に必要な主な書類は以下の通りです:
1. 新規購入の場合
- 登記申請書
- 売買契約書
- 共有者全員の住民票(マイナンバーの記載がないもの)
- 売主の印鑑証明書(発行から3ヶ月以内)
- 固定資産評価証明書(登録免許税算出用)
- 登記識別情報(権利証)
- 共有者全員の認印(または実印)
2. 持分を移転する場合
- 登記申請書
- 持分移転契約書(売買/贈与証書など)
- 現所有者の印鑑証明書(発行から3ヶ月以内)
- 新共有者の住民票(マイナンバーの記載がないもの)
- 固定資産評価証明書(登録免許税算出用)
- 登記識別情報(権利証)
- 当事者全員の認印または実印
4. 費用
1. 登録免許税
共有名義の登記に係る登録免許税は、移転する持分の価値に基づいて計算されます。
- 売買の場合: 固定資産評価額 × 移転する持分 × 1.5%(租税特別措置法適用)
- 贈与の場合: 固定資産評価額 × 移転する持分 × 2%
- 相続の場合: 固定資産評価額 × 移転する持分 × 0.4%
2. 司法書士報酬(目安)
司法書士に依頼する場合の報酬目安は以下の通りです(金額は一般的な相場であり、実際には司法書士により異なります):
- 新規購入時の共有名義登記: 5〜10万円程度
- 既存不動産の持分移転登記: 3〜8万円程度
- 相続による共有名義登記: 5〜15万円程度(相続人の数や財産の複雑さにより変動)
3. その他の費用
- 住民票取得費用: 1通あたり200〜500円程度
- 印鑑証明書取得費用: 1通あたり200〜500円程度
- 固定資産評価証明書取得費用: 1通あたり200〜500円程度
共有名義でよくあるトラブルと対策
1. 共有者間の意見対立による不動産の利用・処分の困難
トラブル事例
琵琶湖畔の別荘を4人の兄弟で共有していましたが、1人が売却を希望し、他の3人が継続保有を希望。結果として不動産が塩漬け状態になってしまった。
<対策>
共有者間で事前に「共有不動産の管理に関する協定書」を作成
将来的な売却条件や共有者が死亡した場合の持分の扱いについてもあらかじめ取り決めておく
定期的に共有者間で話し合いの場を設ける
2. 共有者の一人が行方不明になるケース
トラブル事例
滋賀県内の山林を複数人で共有していたが、共有者の一人が海外移住し連絡が取れなくなった。その結果、不動産の売却や有効活用ができなくなった。
<対策>
共有者の連絡先を定期的に更新する仕組みを作る
不在者財産管理人の選任申立てを検討(家庭裁判所に申立て)
持分の買取りルールをあらかじめ決めておく
3. 固定資産税の支払いトラブル
トラブル事例
共有不動産の固定資産税を代表者が立て替え払いしていたが、他の共有者からの回収が滞り、トラブルになった。
<対策>
固定資産税の支払い方法と分担割合を書面で取り決める
滋賀県内の各市町村では、申請により納税通知書を共有者ごとに分けて送付可能な場合も(市町村により対応が異なる)
口座引き落としなど自動的な支払い方法を活用
4. 相続発生時のさらなる共有関係の複雑化
滋賀県内の農地を3人で共有していたが、その一人が亡くなり相続人が4人いたため、結果的に6人での共有になり、意思決定がさらに複雑化した。
<対策>
遺言書で持分の承継者を一人に指定しておく
生前贈与や他の共有者への持分譲渡を検討
民法上の共有物分割請求を検討(ただし不動産の現物分割が難しい場合は競売になる可能性あり)
専門家に相談するメリット
共有名義の不動産登記は複雑なケースが多く、以下のような点で専門家への相談がおすすめです:
1. 最適な共有形態の提案
司法書士や弁護士は、目的や状況に応じた最適な共有形態を提案できます。例えば:
・共有持分の割合設定
・共有に代わる選択肢(信託、不動産の共同所有を目的とした会社設立など)
2. トラブル予防の助言
将来起こりうるトラブルを予測し、予防策を助言します:
・共有者間協定書の作成サポート
・将来の売却や相続を見据えた持分設計
3. 税務面のアドバイス
税理士と連携し、税務面での最適化アドバイスも可能です:
・持分の移転方法による税負担の違い
・相続税評価への影響
・共有不動産の経費計上方法
4. 登記手続きの正確な実施
複雑な登記手続きを正確に行います:
・必要書類の過不足なき準備
・登記申請書の適切な作成
・管轄法務局との連携
滋賀県内では、琵琶湖周辺の別荘地や古くからの農地・山林の共有名義についての相談が多く、地域の実情に詳しい専門家への相談が特に有効です。
まとめ:共有名義登記の主なポイント
共有名義の不動産登記を考える際は、以下のポイントを押さえておきましょう:
- 目的の明確化: なぜ共有名義にするのか目的を明確にする
- 持分割合の慎重な決定: 出資割合や将来の相続を見据えた持分設定
- 共有者間の取り決め: 利用方法、経費負担、将来の売却条件などを書面化
- 将来を見据えた計画: 相続発生時や意見対立時の対応策を事前に検討
- 専門家への相談: 複雑なケースは早めに専門家に相談
滋賀県内でも共有名義の不動産に関するトラブルは年々増加傾向にあります。特に相続発生時に問題が顕在化するケースが多いため、共有名義にする際は将来を見据えた慎重な検討が必要です。
お問い合わせ
共有名義の不動産登記についてご不明点がございましたら、お気軽に当事務所にご相談ください。滋賀県内の不動産事情に精通した司法書士が、最適なアドバイスを提供いたします。
司法書士・行政書士和田正俊事務所
〒520-2134 滋賀県大津市瀬田5丁目33番4号
TEL: 077-574-7772(受付時間:平日9:00~17:00)
FAX: 077-574-7773
※事前予約で土日祝日も対応可能です
◇ 当サイトの情報は執筆当時の法令に基づく一般論であり、個別の事案には直接適用できません。
◇ 法律や情報は更新されることがあるため、専門家の確認を推奨します。
◇ 当事務所は情報の正確性を保証せず、損害が生じた場合も責任を負いません。
◇ 情報やURLは予告なく変更・削除されることがあるため、必要に応じて他の情報源もご活用ください。
この記事を書いた人

司法書士・行政書士 和田正俊事務所 代表和田 正俊(Wada Masatoshi)
- 滋賀県司法書士会所属 登録番号 滋賀第441号
- 簡裁訴訟代理関係業務 認定番号 第1112169号
- 滋賀県行政書士会所属
登録番号 第13251836号会員番号 第1220号 - 公益社団法人 成年後見センター・リーガルサポート滋賀支部所属
会員番号 第6509213号
後見人候補者名簿 及び 後見監督人候補者名簿 搭載 - 法テラス契約司法書士
- 近畿司法書士会連合会災害相談員
不動産に関連する記事
【司法書士が徹底解説】個人間の高額融資で絶対に失敗しない!不動産担保(抵当権・譲渡担保)活用の完全ガイド
2025年12月17日
法改正で必須に!登記はメールアドレスで速く
2025年11月10日
司法書士による本人確認手続きの流れと実務のQ&A
2025年12月7日