相続とは

相続とは、人が亡くなったときにその人の財産を法律や遺言に基づいて分配することです。相続は、亡くなった人の意思や家族の関係を尊重しつつ、財産の公正な分け方を決める重要なプロセスです。
相続は、亡くなった人の財産だけでなく、その人の借金や税金も引き継ぐことを意味します。したがって、相続する前に、亡くなった人の財産や債務の状況を把握することが必要です。また、相続放棄という選択肢もあります。相続放棄とは、相続権を放棄することで、財産だけでなく債務も受け継がないことを表します。相続放棄は、亡くなった人の死亡から三か月以内に行わなければなりません。
相続は、多くの人にとって一度しか経験しないかもしれませんが、非常に複雑で重要な問題です。相続に関する知識や情報を得ることで、自分や家族の将来を守ることができます。
相続には、大きく分けて二つのステップがあります。
一つ目は、相続人の調査(確定)、二つ目は、遺産分割協議です。
■相続登記に必要な書類
◎亡くなられた方の戸籍・除籍・原戸籍謄本(出生から死亡まですべて)※
◎相続人全員の戸籍謄本 ※
◎亡くなられた方の除票 ※
◎不動産を相続する方の住民票 ※
◎固定資産評価証明書又は固定資産課税明細書 ※
◎遺産分割協議書(すでに作成されている場合のみ)◎相続人全員の印鑑証明書
※当事務所で取得することもできます。
相続人の調査(確定)とは
相続人の調査(確定)とは、被相続人(亡くなった方)と相続人全員の出生から死亡までのすべての戸籍を取寄せ、被相続人の法定相続人が誰であるのかを調べることを指します。
もし相続人の調査をしなかったり、自分なりに調査をしたものの漏れなどがあって本来の相続人が全員揃っていない状態で遺産分割の協議をしてしまうと、協議がまとまったとしても、その協議は法的に無効になります。
このように相続人調査・戸籍調査を怠ると、相続が長期間に渡ったり、親族関係が修復不可能なまでに争ったりしますので、相続において、最も大切なものが相続人調査なのです。
相続人調査を行った後は、法務局へ申請して法定相続情報一覧図を作成すると、金融機関等での手続もスムーズに進みます。
相続人調査は、遺産分割協議や遺言執行など、相続手続きの基礎となる重要な作業です。しかし、多くの方は相続人調査について十分な知識や経験がありません。そのため、自力で行う場合は時間や費用がかかったり、ミスやトラブルが発生したりするリスクが高くなります。そこで、専門家に依頼することで、安心して正確な相続人調査を行うことができます。
遺産分割協議とは
遺産分割協議とは、相続人が亡くなった人の財産をどのように分けるかを話し合うことです。遺産分割協議は、相続人の意思に基づいて行われますが、法律や税金の面からも注意が必要です。
遺産分割協議のメリットとデメリット
遺産分割協議のメリットは、相続人が自由に財産を分け合えることです。相続人の数や関係によっては、法定相続分とは異なる分け方をしたい場合もあるでしょう。例えば、亡くなった人が特に親しかった相続人に多くの財産を残したいという場合や、亡くなった人が望んでいた財産の使い方を実現したいという場合などです。また、遺産分割協議では、プラスの財産だけでなく、マイナスの財産も分けることができます。これにより、相続人の負担を公平にすることができます。
遺産分割協議のデメリットは、相続人間で合意することが難しい場合があることです。相続人の中には、自分の利益を優先したり、感情的になったりする人もいるかもしれません。その場合、遺産分割協議は円滑に進まず、トラブルや争いに発展する恐れがあります。また、遺産分割協議では、法律や税金の知識が必要です。例えば、不動産や株式などの財産を分ける場合には、贈与税や所得税などの税金が発生する可能性があります。そのため、遺産分割協議をする前には、専門家に相談することがおすすめです。
遺産分割協議の方法と手続き
遺産分割協議は、基本的には口頭で行っても有効ですが、後々のトラブルを防ぐためには、書面で行うことが望ましいです。書面で行う場合には、遺産分割協議書という文書を作成します。遺産分割協議書には、以下の内容を記載します。
- 相続人の氏名・住所・続柄
- 亡くなった人の氏名・住所・死亡日
- 相続財産の内容・価額
- 負債の内容・金額
- 分割方法・結果
- 相続人全員の署名・捺印 など
遺産分割協議は、相続人間で円満に行えれば最善の方法ですが、必ずしもそうとは限りません。相続人間で合意できない場合や紛争が起きた場合には、裁判所や家庭裁判所に調停や審判を申し立てることもできます。しかし、これらの方法は時間や費用がかかりますし、結果も不確実です。そのため、遺産分割協議をする際には、冷静かつ公正に話し合うことが大切です。
遺産分割協議書を作成したら、次に不動産や預貯金などの名義変更手続きを行います。不動産の場合には、法務局に相続登記を申請し、預貯金や株式などの場合には、金融機関や証券会社などに名義変更を依頼します。この際には、遺産分割協議書や戸籍謄本などの必要書類を提出する必要があります。
相続登記とは
不動産相続登記とは、不動産の所有者が亡くなったときに、その不動産を相続した人が、自分の名前に登記を変更することです。この登記は、相続人の権利を明確にし、不動産の売買や贈与などの取引を円滑にするために必要です。
また、期間の経過により、相続関係が複雑になってしまったり、費用が多くかかったりする可能性がありますので、お早めの手続きをお勧めしています。
不動産の相続登記は、令和6年4月1日から義務化されます。これは、相続人が相続した日から3年以内に登記をしなければならないということです。義務を怠ると、10万円以下の過料が科せられます。また、過去に相続した不動産でも、同じ期限内に登記をする必要があります。
不動産相続登記の方法は、大きく分けて2つあります。一つは、相続人全員で話し合って遺産分割協議を行い、その内容に基づいて登記をする方法と、もう一つは、法律で定められた割合(法定相続分)で登記をする方法です。どちらの方法でも、申請書や戸籍謄本などの書類が必要です。
不動産の相続登記は、自分で行うこともできますが、手続きが複雑な場合や専門的な知識が必要な場合は、司法書士や弁護士に依頼することもできます。法務局や司法書士会などでも相談を受け付けていますので、不明な点や困ったことがあれば気軽に問い合わせてくださいね。
相続預貯金とは
銀行等の預貯金の相続について、詳しく解説します。
銀行等の預貯金の相続とは、被相続人名義の銀行等の預貯金を相続によって名義書き換え・払戻し手続きをすることです。預貯金の口座名義人が亡くなった場合、亡くなったことを金融機関が確認した時点で、預貯金の口座は凍結されます。口座が凍結されるとお金を引き出すことが出来なくなります。
その口座からお金を引き出すためには、一定の戸籍や遺言書、遺産分割協議書などを用意し、必要な相続人の印鑑証明書などを提出することで、相続預金の払い戻し手続き・名義変更手続きが行えます。
銀行等の預貯金の相続には、次のような方法があります。
遺言書がある場合
- 遺言書に従って、遺言執行者または指定された相続人が預貯金を受け取る
- 遺言書には公正証書遺言や自筆証書遺言などがあり、家庭裁判所の検認済証明書や遺言執行者の委任状などが必要になる場合がある
遺言書がない場合
- 法定相続人が法定相続分に応じて預貯金を分け合う
- 相続人同士で話し合って遺産分割協議書を作成し、それに基づいて預貯金を分配する
- 遺産分割協議ができない場合は、家庭裁判所に審判や調停を申し立てる
銀行等の預貯金の相続手続きに必要な書類は、金融機関や相続方法によって異なりますが、一般的には以下のようなものです。
- 戸籍謄本(被相続人と相続人の関係を示すもの)
- 印鑑証明書(相続人全員のもの)
- 通帳やキャッシュカード(返却するもの)
- 公正証書遺言、法務局の遺言書情報証明書、家庭裁判所の検認済の自筆証書遺言、検認調書(遺言がある場合)
- 遺産分割協議書又は相続人全員が署名押印した相続届 など(遺言がない場合)
銀行等の預貯金の相続手続きにかかる期間は、1週間から数週間程度です。ただし、提出した書類に不備があったり、遺産分割協議や家庭裁判所の審判・調停が必要だったりする場合は、もっと時間がかかることもあります。例えば、
- 預貯金口座が凍結される前に勝手に引き出すと、相続放棄ができなくなったり、他の相続人からトラブルになったりする可能性がある
- 預貯金口座から入金や引き落としができなくなるため、必要に応じて口座変更手続きをする
- 預貯金は相続税の対象となるため、評価額や納税方法を確認する
以上が、銀行等の預貯金の相続についての解説です。銀行等の預貯金は多くの人が持っている資産であり、適切な手続きをすることでスムーズに相続できます。亡くなられた方への敬意としても、早めに手続きを済ませましょう。
相続の注意点とは?
農地・山林を相続した場合の届出

相続にはさまざまな手続きが必要になりますが、その中でも忘れがちなのが、農地や山林を相続した場合の届出などです。
土地を相続した場合の届出
相続財産に農地や山林が含まれている方は、「土地届け」が必要になる場合があります。農地については、平成21年12月以降、森林については、平成24年4月以降、相続が発生したときに届出を行うことが義務づけられました。相続発生から90日以内、遺産分割から90日以内にそれぞれ決められたところに届け出なければ、過料(罰金のようなものです)を科されると定められています。相続登記と合わせて行われることをオススメします。
国土交通省国土政策局が「土地届け」に関して配布しているパンフレットによると、土地届けは以下のような目的で行われます。
- 農地や森林の所有者や利用者を把握し、農林業振興や国土保全のための政策立案や施策実施に役立てる
- 農地や森林の所有者や利用者に対して、農林業振興や国土保全のための情報提供や支援を行う
- 農地や森林の所有者や利用者が変わった場合に、その変更内容を正しく登記するための手続きを促す
土地届けは、農地法や森林法で定められた対象者が対象となります。具体的には、
- 農地法で定められた対象者
- 農地を所有する人
- 農地を借りて耕作する人
- 農地を貸し出す人
- 農地を売買・贈与・交換・分割・統合・境界変更する人
- 農地を相続する人
- 森林法で定められた対象者
- 森林を所有する人
- 森林を借りて経営する人
- 森林を貸し出す人
- 森林を売買・贈与・交換・分割・統合・境界変更する人
- 森林を相続する人
これらの対象者は、それぞれ以下の機関に届出書を提出しなければなりません。
- 農地法で定められた対象者
- 市町村長(都道府県知事へ委託されている場合は都道府県知事)
- 森林法で定められた対象者
- 都道府県知事
土地届けには、必要書類や添付書類があります。詳しくは各機関に問い合わせるか、国土交通省国土政策局のホームページで確認してください。
国土交通省国土政策局が「土地届け」に関して配布しているパンフレット
滋賀県大津市の相続相談なら司法書士・行政書士和田正俊事務所当事務所でお手伝いできること
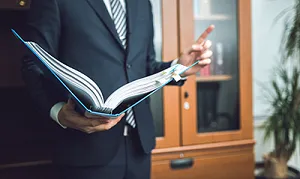
相続の手続きに関する専門家として、滋賀の司法書士・行政書士 和田正俊事務所がお客様のお手伝いをしています。
最適な相続手続きをお客様のご要望やご事情に応じて、提案し、相続登記をはじめとする各種相続手続きをお客様に代わって行います。また、手続きに必要な書類や手順を丁寧にご説明し、迅速かつ丁寧に対応いたします。
滋賀県南部・滋賀県高島市・京都市内の場合は、無料での出張相談も可能です。お気軽にお問い合わせください。
一人ひとりのお客様に誠実かつ真摯に対応いたします。
滋賀県大津市の司法書士・行政書士和田正俊事務所相続手続きサポートの流れ
1.お電話によるご相談受付
まずはお電話かFAX、メールで、「相続・遺産承継で相談」と当事務所へお問い合わせください。(相続される不動産の固定資産課税明細書などをご用意の上、ご連絡いただけますと概算の御見積を出すことができます。)
専門家が対応させていただきます。
2.専門家の面談による聞き取り
相続人の状況、遺産の概要や相談者のご希望などをしっかりお伺いします。その後、相続・遺産分割の実施に必要な書類や手続き、費用などについてご説明いたします。
3.相続人調査
お亡くなりになった方(被相続人)の出生からの戸籍謄本などを取り寄せ、相続人を確定いたします。戸籍については、相続人がわかっていても揃える必要があります。
4.遺産調査
相続財産の土地建物など不動産の価額や個数、所在を市町村役場や法務局にて調査いたします。
5.遺産分割協議
遺言書がある場合はその内容に従って、ない場合は民法の規定に従って、相続人間で遺産分割協議を行います。協議が成立したら「遺産分割協議書」を作成し、署名捺印します。
6.遺産分割協議に基づく継承手続き
「遺産分割協議書」に基づいて、不動産などの所有権移転登記を代理して行います。
7.遺産整理手続き完了のご報告
受任後は迅速な手続き処理とともに、経過について必要に応じてご報告いたします。遺産分割のすべての手続きが完了すれば、ご依頼者様に遺産整理手続きの完了報告をいたします。
【和田正俊事務所へご相談頂く方へ】
ご相談票をダウンロードのうえ、ご相談・面接時にご活用下さい。
ダウンロードしたご相談票は、以下のいずれかの方法で送信してください。
①ファックスにて送信 FAX番号:077-574-7773
②メールに添付して送信 メールアドレス:info@wada7772.com

相続放棄とは・・・

相続放棄をするためには、相続の開始を知ったとき(原則、亡くなったことを知ったとき)から3ヶ月以内に家庭裁判所で手続きする必要があります。相続放棄が家庭裁判所に認められるとその相続に関して、初めから相続人にならなかったものとみなされ、被相続人の遺産を相続しないこととなります。
限定承認とは・・・

限定承認をするためには、相続放棄と同様に相続の開始を知ったとき(原則、亡くなったことを知ったとき)から3ヶ月以内に家庭裁判所で手続きする必要があります。
相続放棄とは違い相続人全員で限定承認の手続きをする必要があります。限定承認が家庭裁判所に認められるとその相続に関して、プラスの財産とマイナスの財産を清算して、残りの財産を相続人に分配することになります。
当事務所でお手伝いできる手続き

当事務所では、相続放棄や限定承認をするための家庭裁判所に提出する書類の作成・調査等、手続きのお手伝いをさせていただいております。
滋賀県大津市の相続相談なら司法書士・行政書士和田正俊事務所相続にはその他の方法もあります。
相続分の譲渡とは・・・

煩わしい相続の手続きはしたくない、特定の誰かに相続財産を譲りたいという方むきの手続きです。相続財産を別の人に譲り、自らは相続手続きをせずに済むようになる手続きです。相続人だけでなく、相続人以外に譲ることもできます。マイナスの財産については、その譲渡を債権者に主張できませんが、譲り受けた人との間では有効です。
ご要望に応じた手続きをアドバイスいたします。

ご依頼者様のご要望に応じて、最適な相続手続のアドバイスをさせていただきます。お気軽におたずね下さい。
滋賀県大津市の相続相談なら司法書士・行政書士和田正俊事務所相続手続き・遺産分割・遺言でお困りの方へ
相続手続きでお困りの方へ
滋賀・京都で司法書士にご相談をお考えならぜひお問い合わせください。滋賀県大津市を中心に遺産・遺言・名義変更・生前贈与など、相続手続きに関するサポートを行っております。

