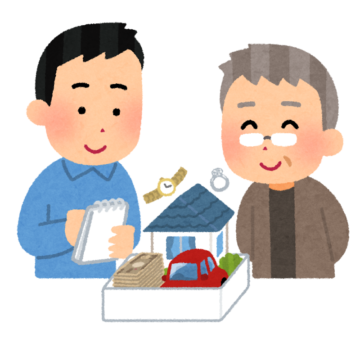
最終更新日:2025年11月27日
法定後見における財産調査の重要性とその手法:専門家が解説する実務のポイント
法定後見制度は、認知症高齢者や障害のある方など判断能力が不十分な方々の権利と財産を守るために設けられた重要な制度です。この制度において、財産調査は後見業務の最初の関門であり、適切な後見事務を行う上での基盤となります。正確な財産状況の把握なくして、被後見人の利益を守ることはできません。
本記事では、司法書士の実務経験に基づき、法定後見における財産調査の重要性、具体的な調査手法、実務上の課題と解決策について詳しく解説します。
法定後見制度と財産管理の位置づけ
法定後見制度は、後見・保佐・補助の3類型からなり、本人(被後見人等)の判断能力の程度に応じて適切な支援を行う制度です。この制度において、財産管理は身上監護と並ぶ重要な役割です。
後見人等に選任されると、まず着手するのが財産調査です。この調査は単なる事務手続きではなく、以下のような重要な意味を持っています:
- 被後見人の生活基盤の把握:どのような資産があり、どの程度の収入があるかを把握することで、生活の質を維持するための計画を立てられます
- 適切な財産管理計画の策定:資産状況に応じた収支計画を立て、長期的な視点で財産を管理できます
- 不正・搾取の発見と防止:過去の不適切な財産移動を発見し、今後の不正を防止できます
- 裁判所への報告義務の履行:後見開始時の財産目録提出は法的義務であり、その後の定期報告の基準となります
財産調査の法的根拠と基本的流れ
法的根拠
民法第853条は「成年後見人は、成年被後見人の財産の調査をし、その調査の結果を家庭裁判所に報告しなければならない」と規定しており、財産調査は後見人の法的義務です。通常、選任から1ヶ月以内に財産目録を作成し、裁判所に提出することが求められます。
財産調査の基本的な流れ
- 後見人選任直後:裁判所から後見開始審判書と後見人選任書を受け取る
- 戸籍・住民票の取得:本人の基本情報を確認する
- 本人の自宅や施設を訪問:保管されている書類や貴重品を確認する
- 金融機関への照会:預貯金口座の有無や残高を確認する
- 不動産調査:登記事項証明書の取得や固定資産評価証明書の取得
- その他財産の調査:保険、有価証券、動産などを確認
- 負債の調査:借入金、未払い料金などを確認
- 財産目録の作成:調査結果をまとめて裁判所に提出
具体的な財産調査の手法とノウハウ
財産調査は、様々な角度から本人の財産状況を把握する必要があります。以下、具体的な調査方法と実務上のポイントを解説します。
1. 現金・預貯金の調査
自宅等での現金確認
本人の自宅や入所施設を訪問し、現金の保管状況を確認します。この際の注意点は:
- 家族や施設職員など第三者の立会いのもとで行う
- 発見した現金は金額を記録し、写真を撮影しておく
- 多額の現金がある場合は、速やかに後見人名義の管理口座に入金する
- タンス預金や隠し場所がないか丁寧に確認する(特に高齢者の場合)
【実務上のポイント】
自宅調査の際は、通帳や印鑑だけでなく、重要書類(保険証券、不動産関係書類、税金関係書類など)も併せて確認しましょう。これらの書類から新たな財産が判明することがよくあります。また、公共料金の請求書や領収書は、未払い債務の有無を確認する重要な手がかりになります。
金融機関への照会
後見人選任証明書を用いて、金融機関に対して本人名義の口座の有無と残高を照会します。
- 網羅的な調査:本人の住所地や過去の居住地の金融機関を広く調査
- 支店レベルでの照会:大手銀行は本店一括照会システムがあるが、地方銀行や信用金庫は支店ごとに照会が必要な場合も
- ゆうちょ銀行の調査:全国の支店で口座開設可能なため、総合照会が効果的
- インターネットバンキングの確認:近年はネット銀行の利用も増加しているため注意
| 金融機関の種類 | 照会方法 | 必要書類 | 回答までの目安 |
|---|---|---|---|
| 都市銀行 | 本店一括照会が可能 | 後見開始審判書の謄本 後見人選任証明書 照会状 | 1~2週間 |
| 地方銀行・信用金庫 | 支店ごとの照会が必要な場合あり | 同上 | 1~3週間 |
| ゆうちょ銀行 | 貯金事務センターへの一括照会 | 同上 | 2~4週間 |
| ネット銀行 | オンラインまたは書面での照会 | 同上(電子データでの提出を求められる場合あり) | 1~3週間 |
2. 不動産の調査
不動産は多くの場合、被後見人の最大の資産です。以下の方法で調査します:
登記情報の取得
- 法務局で登記事項証明書(全部事項証明書)を取得
- 本人の本籍地や過去の住所地の法務局も調査
- 不動産の権利関係(共有、抵当権の有無など)を確認
固定資産税関係書類の確認
- 市区町村の税務課で固定資産評価証明書を取得
- 固定資産税納税通知書から未登記建物の有無を確認
- 評価額は後見人が提出する財産目録の基準となる
不動産の現況確認
- 可能であれば実際に物件を訪問し、状態や利用状況を確認
- 賃貸に出している場合は、賃貸契約書の内容を確認
- 管理状況や修繕の必要性をチェック
【実務上のポイント】
空き家となっている不動産は、防犯・防災上のリスクがあるため早急な対応が必要です。また、固定資産税の減免措置(障害者控除など)が適用されているか確認し、適用可能であれば申請手続きを行いましょう。不動産の処分が必要な場合は、家庭裁判所の許可が必要なため、計画的に進めることが重要です。
3. 有価証券・保険の調査
有価証券の確認
- 証券会社への照会で口座の有無と保有証券を確認
- 株券(特に非上場株式)は自宅保管されていることも
- 国債や地方債の所有状況も確認
保険契約の確認
- 生命保険会社への照会で契約内容を確認
- 保険証券から受取人や満期日、解約返戻金を確認
- 医療保険や介護保険の給付金請求漏れがないか確認
4. 負債の調査
負債の調査は財産管理計画を立てる上で非常に重要です:
借入金の確認
- 金融機関への照会で借入の有無を確認
- 住宅ローンや消費者金融からの借入に注意
- 借入条件(金利、返済期間など)を確認
税金・公共料金の滞納確認
- 市区町村の税務課で住民税や固定資産税の滞納を確認
- 公共料金(電気・ガス・水道など)の未払いを確認
- 国民健康保険料や介護保険料の滞納状況を確認
その他の債務確認
- 医療費や施設利用料の未払いがないか確認
- クレジットカードの利用状況と未払い額を確認
- 身元保証や連帯保証人となっている可能性も調査
5. 収入の調査
被後見人の継続的な収入源を把握することも重要です:
- 年金:年金事務所で年金証書や振込通知書を確認
- 給与・賃金:就労している場合は給与明細を確認
- 不動産収入:賃貸契約書や入金状況を確認
- 各種手当:障害年金、特別障害者手当などの受給状況を確認
- 配当金・利子:株式や預金からの収入を確認
財産目録の作成と裁判所への報告
調査結果をもとに、裁判所に提出する財産目録を作成します。この財産目録は今後の後見事務の基準となる重要な書類です。
財産目録の記載項目
財産目録には、以下の項目を正確に記載します:
- 現金・預貯金:金融機関名、支店名、口座種別、口座番号、残高
- 不動産:所在地、地番、地目、地積、評価額(固定資産評価額)
- 有価証券:種類、銘柄、数量、評価額
- 保険:保険会社名、証券番号、保険種類、解約返戻金額
- 動産:自動車、貴金属、美術品など価値のある物品
- 負債:借入先、借入額、返済条件
- 定期的な収入:年金や賃料収入など
- 定期的な支出:施設利用料、医療費、公共料金など
財産目録作成のためのチェックリスト
- □ 全ての金融機関への照会を完了したか
- □ 自宅・施設での現金・貴重品の確認を行ったか
- □ 不動産登記簿の調査を行ったか
- □ 固定資産評価証明書を取得したか
- □ 生命保険等の契約内容を確認したか
- □ 有価証券の有無と評価額を確認したか
- □ 負債の内容と金額を確認したか
- □ 年金等の収入源と金額を確認したか
- □ 定期的な支出項目と金額を確認したか
- □ 財産の評価方法は適切か(固定資産評価額、時価など)
- □ 裁判所の書式に従って作成しているか
財産目録提出後の対応
財産目録提出後も、以下の点に注意が必要です:
- 追加発見財産の報告:財産目録提出後に発見した財産は速やかに追加報告
- 財産管理計画の策定:調査結果をもとに長期的な財産管理計画を立てる
- 裁判所からの質問への対応:財産目録に関する裁判所からの質問に適切に回答
- 定期報告の準備:次回の定期報告に向けて収支管理を開始
財産調査における実務上の課題と対応策
財産調査では様々な課題に直面することがあります。以下、実務上よく遭遇する課題と対応策を紹介します。
1. 金融機関から情報提供を拒否されるケース
課題:一部の金融機関では、後見人選任証明書があっても口座情報の開示を渋る場合があります。
対応策:
- 裁判所が発行する「財産調査嘱託書」の発行を依頼する
- 金融機関の本店や法務部門に相談する
- 司法書士会や弁護士会のルートを通じて交渉する
2. 被後見人が非協力的なケース
課題:被後見人本人が後見制度を理解・受容できず、財産情報の提供を拒むことがあります。
対応策:
- 時間をかけて信頼関係を構築する
- 家族や親族、ケアマネジャーなど本人が信頼する人を介して協力を求める
- 本人のプライバシーを尊重しながら、後見制度の目的を丁寧に説明する
3. 親族等による財産隠しや不正が疑われるケース
課題:後見開始前に親族等が被後見人の財産を流用していた痕跡がある場合。
対応策:
- 通帳の取引履歴を丹念に確認し、不審な引き出しを調査
- 必要に応じて裁判所に状況を報告し、指示を仰ぐ
- 専門家(弁護士等)と連携して対応を検討
- 場合によっては不正利得の返還請求や刑事告訴も検討
4. 複雑な財産構成に対する対応
課題:事業用資産や海外資産、暗号資産など、専門的知識が必要な財産がある場合。
対応策:
- 税理士や公認会計士などの専門家と連携
- 必要に応じて専門的な評価機関に依頼
- 裁判所に状況を説明し、専門家への報酬支払いについて許可を得る
【実務上のポイント】
財産調査は単なる事務作業ではなく、被後見人の生活全体を理解するプロセスでもあります。財産状況だけでなく、本人の生活歴や価値観、人間関係などを総合的に把握することで、より適切な後見事務が可能になります。財産調査の過程で得られた情報は、後見事務の方針を決める重要な材料となります。
専門家(司法書士・行政書士)による財産調査のメリット
財産調査は、専門的な知識と経験が求められる業務です。司法書士・行政書士などの専門家に依頼するメリットは以下の通りです:
1. 法的知識に基づく適切な調査
- 不動産登記や商業登記に関する専門知識を活かした調査が可能
- 金融機関や行政機関との交渉に必要な法的知識を持っている
- 権利証や遺言書など法的文書の重要性を理解して調査できる
2. 効率的かつ網羅的な調査
- 経験に基づいたノウハウで見落としのない調査が可能
- 各種機関とのネットワークを活かした迅速な調査
- システマチックな調査手法による効率的な財産把握
3. 裁判所対応の的確さ
- 裁判所が求める書式や記載方法に精通している
- 追加調査の必要性を的確に判断できる
- 裁判所からの質問に適切に回答できる
4. 継続的な財産管理への移行
- 調査結果をもとに適切な財産管理計画を策定できる
- 定期報告に向けた収支管理の体制を整えられる
- 財産に関する法律相談にワンストップで対応可能
まとめ:適切な財産調査が後見事務の成功を左右する
法定後見における財産調査は、被後見人の財産を適切に保全・管理するための出発点です。調査が不十分だと、財産の散逸や不適切な管理につながるリスクがあります。逆に、丁寧かつ網羅的な調査を行うことで、被後見人の生活を支える堅実な財産管理が可能になります。
特に重要なポイントをまとめると:
- 財産調査は法的義務であり、後見開始直後の最重要業務
- 預貯金、不動産、有価証券、保険、負債など全ての財産を網羅的に調査
- 調査結果をもとに作成する財産目録は、今後の後見事務の基準となる
- 課題が生じた場合は、専門家の協力を得ながら適切に対処
- 単なる財産把握だけでなく、被後見人の生活全体を理解する姿勢が重要
当事務所では、長年の経験と専門知識を活かし、丁寧かつ正確な財産調査を行っています。法定後見に関するご相談やお悩みがありましたら、お気軽にご連絡ください。被後見人の権利と財産を守るお手伝いをいたします。
■■□―――――――――――――――――――□■■
司法書士・行政書士和田正俊事務所
【住所】 〒520-2134 滋賀県大津市瀬田5丁目33番4号
【電話番号】 077-574-7772
【営業時間】 9:00~17:00
【定休日】 日・土・祝
■■□―――――――――――――――――――□■■
🌟 わずか10秒!あなたのその悩み、LINEで即解決しませんか?
相続や登記、会社設立の疑問を抱えたまま、重い腰を上げる必要はありません。
当事務所では、ご多忙な皆様のためにLINE公式アカウントを開設しています。
✅ 【手軽】 氏名や住所の入力は不要。匿名で相談OK!
✅ 【迅速】 お問い合わせから最短5分で司法書士に直接つながります。
✅ 【無料】 もちろん、初回のLINE相談は完全無料です。
▼ 今すぐLINEで友だち追加して、相談を開始!
◇ 当サイトの情報は執筆当時の法令に基づく一般論であり、個別の事案には直接適用できません。
◇ 法律や情報は更新されることがあるため、専門家の確認を推奨します。
◇ 当事務所は情報の正確性を保証せず、損害が生じた場合も責任を負いません。
◇ 情報やURLは予告なく変更・削除されることがあるため、必要に応じて他の情報源もご活用ください。
この記事を書いた人

司法書士・行政書士 和田正俊事務所 代表和田 正俊(Wada Masatoshi)
- 滋賀県司法書士会所属 登録番号 滋賀第441号
- 簡裁訴訟代理関係業務 認定番号 第1112169号
- 滋賀県行政書士会所属
登録番号 第13251836号会員番号 第1220号 - 公益社団法人 成年後見センター・リーガルサポート滋賀支部所属
会員番号 第6509213号
後見人候補者名簿 及び 後見監督人候補者名簿 搭載 - 法テラス契約司法書士
- 近畿司法書士会連合会災害相談員
成年後見・権利擁護に関連する記事
年の瀬に見直す成年後見制度|高齢の親との年末年始で考えるべきこと
2025年12月24日
【司法書士解説】地面師詐欺から高齢者を守る
2025年7月2日




