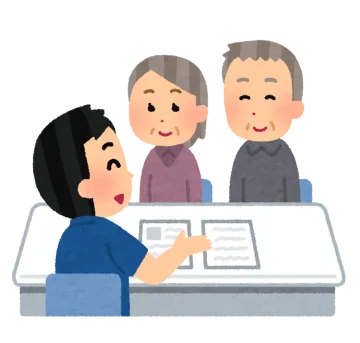
最終更新日:2025年11月27日
意思決定支援が難しい理由とは?成年後見実務の専門家が解説する5つのポイント
意思決定支援は、認知症高齢者や障害のある方など判断能力が不十分な方々の自己決定を尊重しながら支援する重要なプロセスです。2016年の成年後見制度利用促進法施行以降、「本人の意思決定支援」の重要性が強調されていますが、実務においては多くの困難が伴います。本記事では、司法書士として多くの成年後見案件に携わってきた経験から、意思決定支援が難しい理由と効果的な支援のポイントを解説します。
意思決定支援とは?法的背景と基本概念
意思決定支援とは、認知症や知的障害、精神障害などにより判断能力が不十分な方が、自らの意思に基づいた生活を送れるよう支援するプロセスです。この概念は国際的には2006年の国連障害者権利条約で明確に位置づけられ、日本でも2016年の成年後見制度利用促進法を経て、2018年の「意思決定支援ガイドライン」において具体化されました。
意思決定支援の基本原則
- 本人の意思の尊重:最大限本人の意思を尊重すること
- 自己決定の支援:本人が自ら意思決定できるよう支援すること
- 最善の利益の追求:本人の意思が確認できない場合は、最善の利益を追求すること
- エンパワメント:本人の能力を最大限に引き出し、活用すること
- チームアプローチ:多職種が連携して支援すること
意思決定支援は、成年後見制度の「代行決定」と対比されることがありますが、実際には両者は補完関係にあります。完全な自己決定が難しい場合でも、可能な限り本人の意向を汲み取り、尊重することが求められているのです。
意思決定支援が難しい5つの理由
1. コミュニケーションの困難さ
認知症や重度の障害がある方とのコミュニケーションには、多くの困難が伴います。具体的には以下のような課題があります:
- 言語表現の限界:言葉で明確に意思を表現できない場合が多い
- 一貫性の欠如:時間や場所、状況によって意思表示が変化する
- 非言語コミュニケーションの読み取り:表情や仕草などから意思を読み取る難しさ
- Yes/Noの判断:質問の意味を理解しているかの確認が困難
ある認知症高齢者の方は、施設入所について尋ねられると「家に帰りたい」と答える一方、実際に自宅に連れて行くと不安を示し「ここはどこ?」と混乱することがありました。このような場合、真の意思をどう捉えるかが大きな課題となります。
2. 本人の意思と最善の利益の葛藤
本人の表明した意思が、客観的に見て本人の健康や安全を脅かす可能性がある場合、支援者は難しい判断を迫られます。
【事例】独居を望む認知症高齢者
80歳の認知症の男性Aさんは、「自分の家で最期まで暮らしたい」と強く希望しています。しかし、火の不始末や服薬管理の問題が頻発し、支援者は施設入所を検討すべきか悩んでいます。本人の「自宅で暮らしたい」という意思を尊重するべきか、安全を優先すべきか、判断が難しいケースです。
このような場合、本人の意思と最善の利益のバランスをどう取るか、また誰がその判断を行うべきかという難しい問題が生じます。
3. 意思決定能力の変動と評価の難しさ
意思決定能力は固定的なものではなく、以下のような要因で変動します:
- 日内変動:時間帯により判断能力が変化(夕方症候群など)
- 体調による変化:体調不良や薬の影響で一時的に判断能力が低下
- 決定内容による差異:日常的な決定は可能でも、複雑な財産管理は困難など
- 環境要因:場所や同席者によって意思表示が変わる
さらに、意思決定能力を客観的に評価する確立された方法がなく、支援者の主観に左右されやすいという問題もあります。
4. 支援者の価値観の影響
支援者自身の価値観や経験が、意思決定支援に大きな影響を与えることがあります:
- 無意識のバイアス:「高齢者には施設が安全」といった思い込み
- パターナリズム:「本人のため」という名目での過剰な介入
- リスク回避志向:トラブルを恐れて消極的な選択肢を勧める傾向
- 世代間ギャップ:価値観の違いによる本人の真意の誤解
ある知的障害のある方が「一人暮らしがしたい」と希望した際、支援者が「危険だから無理」と即座に否定するケースがありました。この背景には支援者の「障害者は保護されるべき」という無意識のバイアスが影響していたかもしれません。
5. 制度的・実務的制約
理想的な意思決定支援を行いたくても、現実には様々な制約があります:
- 時間的制約:十分な意思確認のための時間が取れない
- マンパワー不足:専門職後見人が多数の案件を抱える現状
- システム上の制約:医療・福祉・法律の縦割り構造
- 責任の所在:最終的な決定の責任の所在が不明確
特に専門職後見人は多くの案件を担当しており、一人の被後見人に十分な時間をかけて意思確認を行うことが物理的に難しいという現実があります。
意思決定支援を効果的に行うための実践的アプローチ
意思決定支援の難しさを認識した上で、より効果的に支援を行うための具体的なアプローチを紹介します。
1. 段階的アプローチの採用
意思決定支援は、以下のような段階を踏むことで効果的に行えます:
- 意思表明支援:本人が自分の意思を表明できる環境を整える
- 意思形成支援:必要な情報提供と選択肢の説明を行う
- 意思実現支援:表明された意思を実現するための具体的支援
特に重要なのは、選択肢を提示する際の配慮です。専門用語を避け、視覚的な補助を用いるなど、本人の理解力に合わせた説明を心がけましょう。
2. 多職種チームによる支援体制の構築
意思決定支援は一人で行うものではなく、チームで取り組むことが重要です:
- 医療職:医学的な判断や能力評価
- 福祉職:日常生活の支援と観察
- 法律職:法的枠組みの提供と権利擁護
- 家族・親族:本人の生活歴や価値観の共有
定期的なケース会議を開催し、多角的な視点から本人の意思を探ることで、より適切な支援が可能になります。
3. 本人の生活史と価値観の理解
本人の過去の選択や価値観を理解することは、現在の意思を推定する上で非常に重要です:
- ライフヒストリーの収集:家族や知人からの情報収集
- 過去の選択パターンの分析:類似状況での過去の決定を参考にする
- 価値観の把握:何を大切にしてきた人なのかを理解する
【実践例】生活史カードの活用
当事務所では、後見開始時に「生活史カード」を作成しています。本人の人生の重要な出来事、大切にしてきた価値観、趣味・嗜好などを記録し、意思決定支援の際の参考にしています。例えば、「教師として長年働いてきた」という情報から、「人に教えること」や「規律」を重視する価値観を推測できます。
4. 意思決定支援プロセスの記録と共有
意思決定支援のプロセスを詳細に記録することは、以下の点で重要です:
- 支援の一貫性確保:支援者が変わっても同じアプローチが可能
- 説明責任の履行:なぜその決定に至ったかの根拠を示せる
- 支援方法の改善:効果的だった方法を蓄積できる
- 法的保護:問題発生時に適切な支援を行った証拠になる
記録には、試みた支援方法、本人の反応、最終的な決定とその理由を含めるようにしましょう。
専門家(司法書士・行政書士)の役割と貢献
司法書士・行政書士は、意思決定支援において以下のような重要な役割を果たします:
1. 法的枠組みの提供と権利擁護
成年後見制度や各種契約行為における法的な枠組みを提供し、本人の権利が侵害されないよう擁護します。具体的には:
- 本人の法的能力に応じた適切な支援方法の提案
- 成年後見制度の各類型(後見・保佐・補助)の適切な選択
- 任意後見契約や見守り契約など、本人の自己決定を尊重した制度の活用
2. 意思決定支援を踏まえた後見実務の実践
成年後見人等として活動する際に、意思決定支援の理念を実践します:
- 定期的な面会による本人の意向確認
- 日常生活や医療、施設入所等に関する意思決定支援
- 財産管理においても可能な限り本人の意向を反映
- 家庭裁判所への報告における意思決定支援プロセスの記録
3. 地域連携ネットワークの構築
地域における権利擁護の中核機関や協議会に参画し、多職種連携の促進に貢献します:
- 地域の中核機関との連携
- ケース会議への参加と法的視点の提供
- 地域の福祉・医療職への法的知識の啓発
まとめ:意思決定支援の難しさを認識しつつ前進するために
意思決定支援は、コミュニケーションの困難さ、本人の意思と最善の利益の葛藤、意思決定能力の変動と評価の難しさ、支援者の価値観の影響、制度的・実務的制約など、多くの難しさを伴います。
しかし、これらの困難を認識した上で、段階的アプローチの採用、多職種チームによる支援体制の構築、本人の生活史と価値観の理解、意思決定支援プロセスの記録と共有といった実践的なアプローチを取ることで、より効果的な支援が可能になります。
私たち専門職は、常に本人を中心に据え、その尊厳と自己決定権を最大限に尊重する姿勢を忘れてはなりません。困難を理由に意思決定支援を諦めるのではなく、創意工夫をもって一人ひとりに合った支援方法を模索し続けることが重要です。
当事務所では、成年後見制度をはじめとする権利擁護業務において、意思決定支援を重視した実務を心がけています。ご本人やご家族の状況に応じた丁寧な対応を行いますので、お気軽にご相談ください。
■■□―――――――――――――――――――□■■
司法書士・行政書士和田正俊事務所
【住所】 〒520-2134 滋賀県大津市瀬田5丁目33番4号
【電話番号】 077-574-7772
【営業時間】 9:00~17:00
【定休日】 日・土・祝
■■□―――――――――――――――――――□■■
🌟 わずか10秒!あなたのその悩み、LINEで即解決しませんか?
相続や登記、会社設立の疑問を抱えたまま、重い腰を上げる必要はありません。
当事務所では、ご多忙な皆様のためにLINE公式アカウントを開設しています。
✅ 【手軽】 氏名や住所の入力は不要。匿名で相談OK!
✅ 【迅速】 お問い合わせから最短5分で司法書士に直接つながります。
✅ 【無料】 もちろん、初回のLINE相談は完全無料です。
▼ 今すぐLINEで友だち追加して、相談を開始!
◇ 当サイトの情報は執筆当時の法令に基づく一般論であり、個別の事案には直接適用できません。
◇ 法律や情報は更新されることがあるため、専門家の確認を推奨します。
◇ 当事務所は情報の正確性を保証せず、損害が生じた場合も責任を負いません。
◇ 情報やURLは予告なく変更・削除されることがあるため、必要に応じて他の情報源もご活用ください。
この記事を書いた人

司法書士・行政書士 和田正俊事務所 代表和田 正俊(Wada Masatoshi)
- 滋賀県司法書士会所属 登録番号 滋賀第441号
- 簡裁訴訟代理関係業務 認定番号 第1112169号
- 滋賀県行政書士会所属
登録番号 第13251836号会員番号 第1220号 - 公益社団法人 成年後見センター・リーガルサポート滋賀支部所属
会員番号 第6509213号
後見人候補者名簿 及び 後見監督人候補者名簿 搭載 - 法テラス契約司法書士
- 近畿司法書士会連合会災害相談員
成年後見・権利擁護に関連する記事
年の瀬に見直す成年後見制度|高齢の親との年末年始で考えるべきこと
2025年12月24日
【司法書士解説】地面師詐欺から高齢者を守る
2025年7月2日




