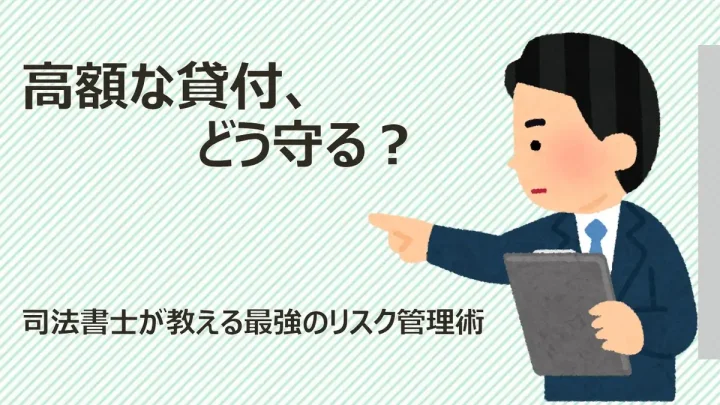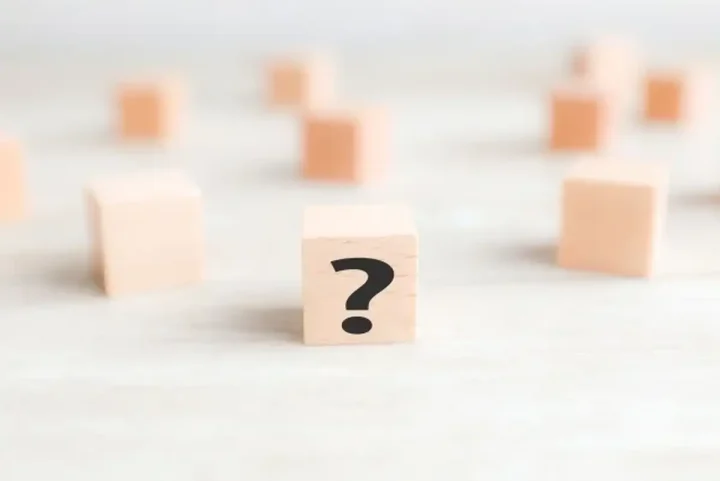不動産の登記事項証明書とは?種類と用途を詳しく解説
不動産取引や相続手続きなどで必要となる「登記事項証明書」。この公的書類には複数の種類があり、目的によって適切なものを選ぶ必要があります。本記事では、不動産の登記事項証明書の種類と特徴、用途、取得方法について詳しく解説します。
登記事項証明書の基本知識
登記事項証明書とは、法務局で保管されている不動産の登記記録に記載されている内容を証明する公的書類です。不動産の所有者や権利関係を第三者に証明するために使用されます。

登記事項証明書は通常、緑色の複写防止用紙に印刷され、登記官による認証文、作成年月日、職氏名が記載され、電子公印(黒色で印刷)が押されています。この公印があることで、公的な証明書としての効力を持ちます。
誰でも法務局に請求すれば取得できる書類ですが、用途に応じて適切な種類を選ぶことが重要です。不動産の登記事項証明書は主に以下の3種類に分類されます。
- 全部事項証明書
- 現在事項証明書
- 所有者証明書
全部事項証明書 - 過去の履歴も含めた完全版
全部事項証明書は、登記記録に記録されている事項の全部を記載した証明書です。現在有効な登記事項だけでなく、過去の所有者情報や抹消された抵当権などの履歴も含まれます。

全部事項証明書の特徴
認証文には「これは登記記録に記録されている事項の全部を証明した書面である。」と記載されています。この証明書は不動産の完全な権利関係の履歴を確認したい場合に有用です。
全部事項証明書の主な用途
- 不動産の権利関係の詳細な調査
- 過去の所有者や権利関係を確認する必要がある場合
- 不動産の権利関係に問題がないか詳細に調べたい場合
- 相続財産調査や訴訟準備などで過去の経緯を確認する場合
全部事項証明書の取得費用
不動産1物件につき600円(法務局窓口での請求時)
現在事項証明書 - 現在有効な情報のみをシンプルに
現在事項証明書は、登記記録に記録されている事項のうち、現在効力を有するもののみを記載した証明書です。過去の履歴は含まれないため、現状の権利関係をシンプルに把握することができます。

現在事項証明書の特徴
認証文には「これは登記記録に記録されている現に効力を有する事項の全部を証明した書面である。」と記載されています。過去の履歴が含まれないため、全部事項証明書よりも読みやすく、現在の権利関係を把握しやすいのが特徴です。
現在事項証明書の主な用途
- 不動産売買や賃貸契約の際の権利関係確認
- 住宅ローン申込時の提出書類
- 相続手続きにおける現在の所有者確認
- 不動産の担保評価
- 建築確認申請の添付書類
現在事項証明書の取得費用
不動産1物件につき600円(法務局窓口での請求時)
所有者証明書 - 所有者情報のみに特化
所有者証明書は、登記記録に記録されている現在の所有権の登記名義人の氏名(名称)と住所のみを証明した書類です。所有者が誰であるかを証明するためだけに使用する簡易な証明書です。

所有者証明書の特徴
認証文には「これは登記記録に記録されている所有者の氏名又は名称及び住所を証明した書面である。」と記載されています。所有権以外の権利関係(抵当権等)は記載されないため、単純明快な証明書です。
所有者証明書の主な用途
- 固定資産税の名義変更手続き
- 地域の町内会・自治会への加入手続き
- 水道・ガス・電気などの公共料金の名義変更
- 境界確定の際の隣接地所有者の確認
- 所有者の確認が必要な各種行政手続き
所有者証明書の取得費用
不動産1物件につき500円(法務局窓口での請求時)
その他の不動産登記関連書類
上記3種類が主な登記事項証明書ですが、特殊なケースで必要となる以下の書類も存在します。
閉鎖事項証明書 - 消滅した不動産の記録
閉鎖事項証明書は、過去に存在していた不動産や登記記録が閉鎖された不動産の登記事項を証明する書類です。登記記録が電子化される前の記録や取り壊された建物の記録などを調べる際に使用します。

閉鎖事項証明書の主な用途
- 取り壊された建物の情報確認
- 合筆・分筆前の土地の情報確認
- 区分所有建物の建替え前の情報確認
- 相続税申告における過去の不動産評価
- 過去の権利関係に関する訴訟資料
閉鎖事項証明書の取得費用
不動産1物件につき600円(法務局窓口での請求時)
登記事項要約書 - 証明力のない情報提供書類
登記事項要約書は、登記記録に記録されている内容を閲覧するために取得する書類です。この書類には認証文が付されないため、公的な証明書としては使用できませんが、登記事項証明書よりも安価に登記情報を確認できます。

登記事項要約書の特徴と注意点
登記事項要約書は、その不動産を管轄する法務局の窓口でのみ交付されます。オンラインや他の法務局窓口では取得できないため注意が必要です。また、公的な証明書ではないため、提出書類として認められない場合があります。
登記事項要約書の主な用途
- 不動産の権利関係を自分で確認するための参考資料
- 登記申請の準備のための事前確認
- 正式な証明書が必要ない内部資料
登記事項要約書の取得費用
不動産1物件につき500円(法務局窓口での請求時)
登記事項証明書の取得方法
取得できる場所
- 法務局窓口:全国どこの法務局でも請求可能(登記事項要約書を除く)
- オンライン:法務局の登記・供託オンライン申請システムから請求可能
- 郵送:法務局に郵送で請求することも可能
取得に必要なもの
- 不動産の所在地・地番または家屋番号
- 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
- 手数料分の収入印紙または現金
オンライン請求の場合は、電子署名やPay-easyによる電子納付が必要となる場合があります。
不動産登記のサポートは当事務所にお任せください
登記事項証明書の取得や不動産登記手続きは、専門的な知識が必要な場合があります。また、お忙しい方にとっては法務局に行く時間を確保することも難しいかもしれません。

当事務所でお手伝いできること
- 登記事項証明書の取得代行:必要な証明書を迅速に取得します
- 抵当権抹消登記:住宅ローン完済後の抹消手続きを代行します
- 住所変更登記:引っ越し後の住所変更を登記します
- 名義変更登記:相続や売買による所有者変更を登記します
- その他各種不動産登記:建物表題登記、分筆・合筆登記など
不動産登記に関するご相談は無料で承っております。専門的な観点からアドバイスをさせていただきますので、お気軽にお問い合わせください。
不動産登記でお困りのことがございましたら、ぜひ当事務所にご相談ください。迅速・丁寧に対応させていただきます。
不動産に関連する記事
【司法書士が徹底解説】個人間の高額融資で絶対に失敗しない!不動産担保(抵当権・譲渡担保)活用の完全ガイド
2025年12月17日
法改正で必須に!登記はメールアドレスで速く
2025年11月10日
司法書士による本人確認手続きの流れと実務のQ&A
2025年12月7日