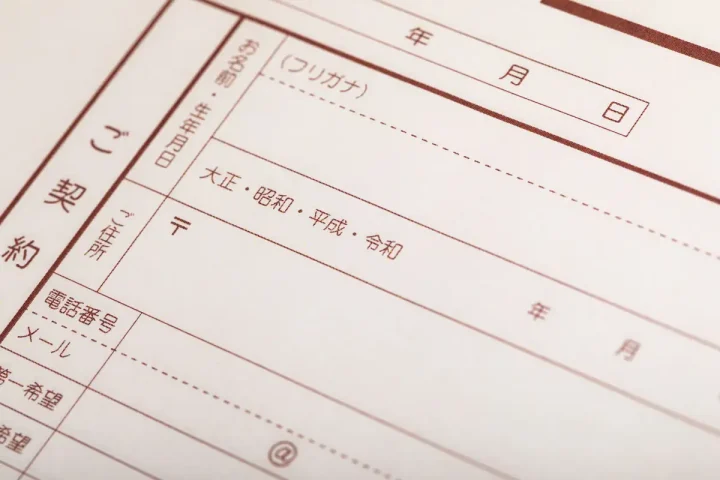最終更新日:2026年1月29日
不動産登記事項証明書の見方をマスターしよう!権利部甲区編
不動産の売買や相続、担保設定など、不動産に関わる取引や手続きでは「不動産登記事項証明書」の確認が不可欠です。この公的書類には、土地や建物の所有者情報、権利関係、制限事項など重要な情報が記録されています。特に「権利部甲区」は所有権に関する情報が記載された重要部分であり、不動産取引の安全性を確保するために正確な読み方をマスターする必要があります。
本記事では、司法書士の専門的視点から、登記事項証明書の権利部甲区の見方を詳細に解説し、実務上の注意点や活用方法までを紹介します。
不動産登記事項証明書の基本構成と権利部甲区の位置づけ
不動産登記事項証明書は、大きく分けて「表題部」「権利部」の2つのセクションから構成されています。このうち「権利部」はさらに「甲区」と「乙区」に分かれています。
| 区分 | 記載内容 | 主な確認ポイント |
|---|---|---|
| 表題部 | 不動産の物理的情報 (所在、地番、地目、地積など) | ・所在地や地番の確認 ・面積や用途の確認 ・建物の構造や床面積 |
| 権利部甲区 | 所有権に関する情報 (所有者、取得原因、取得日付など) | ・現在の所有者確認 ・所有権の取得経緯 ・共有の場合の持分割合 |
| 権利部乙区 | 所有権以外の権利に関する情報 (抵当権、地上権、賃借権など) | ・担保権の有無 ・その他の制限の確認 ・抵当権の債権額 |
「権利部甲区」は所有権に関する情報のみが記載される部分であり、不動産の真の所有者を確認するための最も基本的な情報源です。
権利部甲区に記載される具体的な項目とその意味
1. 順位番号
権利部甲区の左端に記載される番号で、所有権の変動履歴を時系列で示しています。最新の所有者情報は、最も大きな順位番号の行に記載されています。
2. 登記の目的
登記がどのような目的で行われたかを示します。主な記載は「所有権保存」「所有権移転」などです。
3. 受付年月日・受付番号
登記申請が法務局に受け付けられた日付と番号です。権利変動の優先順位を決める重要な情報となります。
4. 権利者その他の事項
最も重要な項目で、所有者の情報や権利取得の詳細が記載されています。主な記載内容は以下の通りです:
- 所有者の氏名/名称と住所/所在地
- 取得原因:売買、相続、贈与など
- 日付:権利を取得した日
- 持分:共有の場合の持分割合
実際の権利部甲区の記載例とその読み方
権利部(甲区)(所有権に関する事項)
| 順位番号 | 登記の目的 | 受付年月日・受付番号 | 権利者その他の事項 |
|---|---|---|---|
| 1 | 所有権保存 | 平成25年4月1日 第12345号 | 所有者 滋賀 太郎 滋賀県大津市○○町1番1号 |
| 2 | 所有権移転 | 平成30年7月15日 第78901号 | 原因 平成30年7月10日売買 所有者 大津 花子 滋賀県大津市△△町2番2号 |
| 3 | 所有権一部移転 | 令和2年3月20日 第23456号 | 原因 令和2年3月15日売買 所有者 大津 花子 滋賀県大津市△△町2番2号 持分 2分の1 所有者 瀬田 次郎 滋賀県大津市□□町3番3号 持分 2分の1 |
この記載例から、この不動産は現在、大津花子さんと瀬田次郎さんが各2分の1の持分で共有している状態であることが分かります。
権利部甲区を読む際の重要ポイントと注意すべき特殊ケース
1. 最新の所有者情報の確認
最も大きな順位番号に記載されている情報が最新の所有者情報です。
2. 共有持分の正確な把握
不動産が複数人によって共有されている場合、それぞれの持分割合を正確に把握することが重要です。
3. 特殊な取得原因の理解
「売買」「相続」以外にも、様々な取得原因があります。
| 特殊な取得原因 | 説明 | 注意点 |
|---|---|---|
| 遺贈 | 遺言による財産の贈与 | 遺言の有効性や遺留分侵害の可能性を確認 |
| 競売 | 裁判所の競売手続きによる取得 | 競売物件特有のリスクを理解する必要あり |
| 収用 | 公共事業のための土地収用 | 残地の利用制限や将来的な計画を確認 |
4. 住所変更の有無の確認
所有者の住所が変更されているにもかかわらず、登記上の住所が更新されていないケースがよく見られます。手続きの際に追加の書類が必要になることがあります。
5. 仮登記の確認
「所有権移転請求権仮登記」など、将来の本登記を保全するための仮登記がある場合、その内容と影響を専門家に確認することが重要です。
権利部甲区の情報を実務で活用するためのチェックリスト
不動産購入時のチェックリスト
- 売主の登記上の名義と身分証明書の情報が一致しているか
- 登記上の住所と現住所に相違がないか(ある場合は住所変更証明書類の準備)
- 共有持分がある場合、全共有者の同意があるか
- 仮登記や処分制限の登記(差押えなど)がないか
相続発生時のチェックリスト
- 被相続人が登記上の所有者と一致しているか
- 共有持分がある場合、各相続人の取得持分を正確に計算できるか
- 登記上の住所と被相続人の最後の住所が一致するか
権利部甲区と他の登記情報を組み合わせた総合的な分析
表題部との関連分析
表題部の情報(地目や面積など)と甲区の所有者情報を照らし合わせることで、農地法の許可が必要な可能性や、建物の新築年と登記時期の乖離などを分析できます。
権利部乙区との関連分析
乙区の担保権(抵当権など)や用益権(地上権など)と甲区の所有者情報を合わせて分析することで、抵当権設定者と現在の所有者の関係や、所有権移転の頻度などを確認できます。
まとめ:権利部甲区を正しく読み解く重要性
不動産登記事項証明書の権利部甲区は、所有権に関する最も基本的かつ重要な情報源です。この情報を正確に読み解くことで、不動産取引や相続手続きを安全かつスムーズに進めることができます。
- 権利部甲区では、最新の順位番号に記載されている情報が現在の所有者情報
- 所有者の氏名・住所、取得原因、取得日付、持分割合を正確に確認することが重要
- 特殊な取得原因や共有状態など、複雑なケースでは専門家のアドバイスが望ましい
不動産登記事項証明書の見方をマスターし、安全でスムーズな不動産取引を実現しましょう。
■■□―――――――――――――――――――□■■
司法書士・行政書士和田正俊事務所
【住所】 〒520-2134 滋賀県大津市瀬田5丁目33番4号
【電話番号】 077-574-7772
【営業時間】 9:00~17:00
【定休日】 日・土・祝
■■□―――――――――――――――――――□■■
🌟 わずか10秒!あなたのその悩み、LINEで即解決しませんか?
相続や登記、会社設立の疑問を抱えたまま、重い腰を上げる必要はありません。
当事務所では、ご多忙な皆様のためにLINE公式アカウントを開設しています。
✅ 【手軽】 氏名や住所の入力は不要。匿名で相談OK!
✅ 【迅速】 お問い合わせから最短5分で司法書士に直接つながります。
✅ 【無料】 もちろん、初回のLINE相談は完全無料です。
▼ 今すぐLINEで友だち追加して、相談を開始!
◇ 当サイトの情報は執筆当時の法令に基づく一般論であり、個別の事案には直接適用できません。
◇ 法律や情報は更新されることがあるため、専門家の確認を推奨します。
◇ 当事務所は情報の正確性を保証せず、損害が生じた場合も責任を負いません。
◇ 情報やURLは予告なく変更・削除されることがあるため、必要に応じて他の情報源もご活用ください。
この記事を書いた人

司法書士・行政書士 和田正俊事務所 代表和田 正俊(Wada Masatoshi)
- 滋賀県司法書士会所属 登録番号 滋賀第441号
- 簡裁訴訟代理関係業務 認定番号 第1112169号
- 滋賀県行政書士会所属
登録番号 第13251836号会員番号 第1220号 - 公益社団法人 成年後見センター・リーガルサポート滋賀支部所属
会員番号 第6509213号
後見人候補者名簿 及び 後見監督人候補者名簿 搭載 - 法テラス契約司法書士
- 近畿司法書士会連合会災害相談員
不動産に関連する記事
【2月スタートが鍵】春の引越しを叶える!不動産売買手続き、なぜ今から?
2026年2月6日
確定申告前にチェック!贈与で取得した不動産の税務処理
2026年2月2日
【2026年最新版】夢のマイホームで後悔しない!司法書士が教える登記の重要性
2026年1月19日