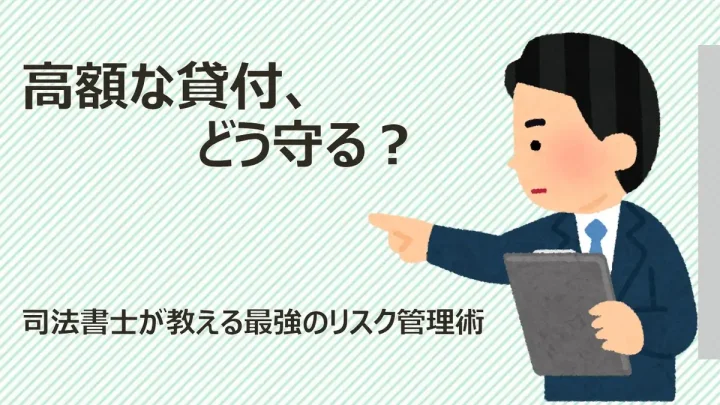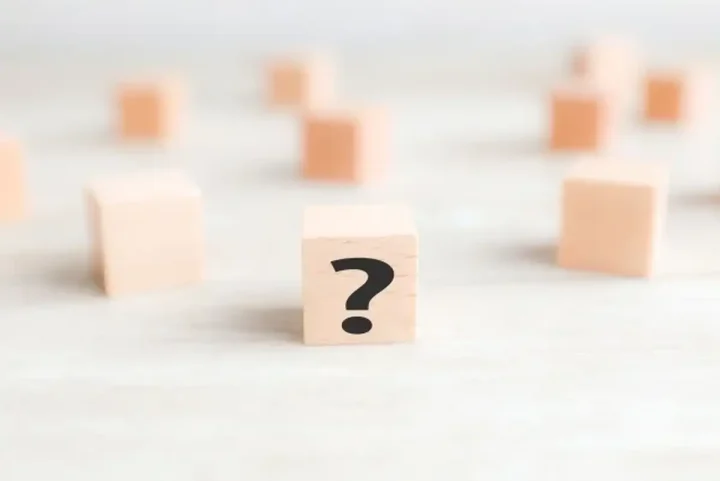最終更新日:2025年11月27日
自治会・町内会の不動産所有に関する法的解説と課題解決方法
地域コミュニティの核となる自治会・町内会は、集会所や公園などの不動産を所有していることがあります。しかし、自治会・町内会は法的にどのような存在なのか、またどのように不動産を所有すべきかについては、多くの方が疑問を持っています。このページでは、自治会・町内会の法的性質と不動産所有に関する問題点および解決策を詳しく解説します。
自治会・町内会の法的地位と活動
自治会や町内会は、地域住民が自主的に集まり、共同で様々な活動を行う組織です。これらの組織は、地域のつながりを深め、住民同士の交流を促進するために非常に重要な役割を果たしています。
自治会・町内会の主な活動
地域のコミュニティ組織として、自治会・町内会は以下のような多様な活動を行っています:
- 地域行事の開催:運動会、盆踊り、地蔵お盆、祭りなどの伝統行事
- 防災活動:防災訓練、災害時の避難計画策定、防災マップの作成
- 防犯活動:地域の安全パトロール、防犯灯の設置・管理
- 環境美化活動:道路や公園の清掃、花壇の整備、ゴミ集積所の管理
- 福祉活動:高齢者の見守り、子育て支援、地域の助け合い
- 広報活動:回覧板の回付、地域情報の発信
- 地域の歴史や文化の継承:伝統行事の保存、文化財の保護
これらの活動を通じて、住民の安心・安全な生活環境が確保され、地域全体の生活の質が向上します。

自治会・町内会の法的性質
法的な観点から見ると、自治会や町内会は「権利能力なき社団」として位置づけられています。これは、社団(人の集まり)としての実質を持ちながらも、法令上の要件を満たしていないために法人としての登記ができない、または登記を行っていないために法人格を持たない団体を指します。
権利能力なき社団の主な特徴は以下の通りです:
- 団体としての規約や会則が存在する
- 代表者や役員が選出される仕組みがある
- 構成員(会員)とは別に団体としての意思決定機関がある
- 会費の徴収など独自の財政的基盤を持つ
- 構成員が変わっても団体としての同一性が保たれる
しかし、権利能力なき社団は法人格を持たないため、法律上の権利や義務を直接持つことができないという制約があります。これが不動産所有などの場面で大きな問題となります。
自治会・町内会による不動産所有の課題
権利能力なき社団である自治会や町内会は、法人格を持たないため、団体名義で不動産登記をすることができません。このため、自治会・町内会が管理する集会所や公園などの不動産を登記する際には、さまざまな工夫が必要でした。

従来の不動産登記方法とその問題点
自治会・町内会が不動産を実質的に所有する場合、従来は以下の3つの方法が採られていましたが、それぞれに重大な問題がありました。
1. 代表者の個人名義での登記
自治会の代表者(町内会長など)の個人名義で不動産を登記する方法です。
主な問題点:
- 不動産が代表者の個人財産と区別がつかず、債権者による差押えのリスクがある
- 代表者が亡くなった場合、相続人に権利が移転し、相続人が複数いる場合は権利関係が複雑化する
- 代表者が交代しても登記上の名義変更が行われないケースが多く、長年経過すると実際の権利関係が不明確になる
- 名義人である元代表者と連絡が取れなくなった場合、登記の変更が事実上不可能になる
2. 構成員全員の共有名義での登記
自治会・町内会の全構成員(会員)の共有名義で不動産を登記する方法です。
主な問題点:
- 構成員が多数のため、登記手続きが煩雑になる
- 共有者の一人が亡くなるたびに相続手続きが必要となり、管理が非常に困難
- 会員の入れ替わりがあるたびに持分移転登記が必要となるが、実務上不可能
- 共有物の処分には共有者全員の同意が必要となり、意思決定が難しい
- 長年経過すると共有者の所在確認が困難になり、不動産の処分や管理が事実上不可能になる
3. 代表者以外の特定構成員の個人名義での登記
規約等に基づき、特定の構成員(役員や信頼できる会員など)の個人名義で不動産を登記する方法です。
主な問題点:
- 名義人の個人財産と区別がつかず、債権者による差押えのリスクがある
- 名義人が亡くなった場合の相続問題が発生する
- 名義人と自治会・町内会との間で信頼関係が崩れた場合、不動産の返還請求などのトラブルが生じる可能性がある
- 名義人が高齢化し判断能力が低下した場合、適切な管理が難しくなる

地縁による団体の認可制度 - 法的解決策
これらの問題を解決するために、平成3年(1991年)に地方自治法が改正され、「認可地縁団体制度」が創設されました。この制度により、自治会・町内会は法人格を取得し、団体名義で不動産登記ができるようになりました。
地縁による団体とは
地縁による団体(認可地縁団体)とは、地方自治法第260条の2に規定される団体で、以下の特徴を持ちます:
- 市町村内の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体
- 町や字の区域その他市町村内の一定の区域を単位として形成された団体
- 地域的な共同活動を行うことを目的とし、現にその活動を行っている団体
- 構成員の資格を当該区域に住所を有する全ての個人に対して付与するもの

認可の要件と効果
市町村長の認可を受けるためには、以下の要件を満たす必要があります:
- 規約を定めていること
- 代表者を定めていること
- 主たる事務所の所在地を定めていること
- 構成員の資格に不当な制限を設けないこと
- 地域的な共同活動を行うことを目的としていること
- 規約の適法性、民主性が確保されていること
- 不動産又は不動産に関する権利等を保有するため必要があると認められること
認可の効果として、以下のようなメリットがあります:
- 法人格を取得し、団体の名義で権利・義務の主体となることができる
- 不動産や不動産に関する権利を団体名義で登記できる
- 代表者や構成員が変わっても団体の同一性は維持される
- 個人名義での登記に伴う相続や名義変更の問題が解消される
- 団体の財産と個人の財産が明確に区別される
認可地縁団体への移行手続き
既存の自治会・町内会が認可地縁団体になるためには、以下の手続きが必要です:
- 規約の整備(目的、名称、区域、事務所の所在地、構成員の資格等を明記)
- 総会の開催(認可申請の決議、代表者の選任等)
- 申請書類の作成(認可申請書、規約、構成員名簿、議事録等)
- 市町村長への申請
- 審査・認可
- 告示(市町村長が認可した旨を告示)
- 登記手続き(不動産の名義変更登記)
特に難しいのが、現在個人名義になっている不動産を認可地縁団体に移転する手続きです。名義人が存命であれば、名義人からの贈与や売買の形で移転できますが、名義人が亡くなっている場合や所在不明の場合は、特例の手続きを利用することになります。
当事務所による自治会・町内会へのサポート
自治会・町内会の不動産所有に関する問題は、専門的な法律知識が必要な複雑な事案です。当事務所では、自治会・町内会の皆様をサポートするための以下のサービスを提供しております。
自治会・町内会向け法務サポート内容
- 認可地縁団体申請支援:規約の作成から市町村への申請手続きまで一貫してサポート
- 不動産登記手続き:個人名義から団体名義への移転登記、抵当権抹消登記など
- 法律相談:自治会・町内会内の揉め事解決、トラブル防止のアドバイス
- 規約整備:適法かつ民主的な運営を確保するための規約作成・改正支援
- 法律講座の開催:遺言書作成講座、相続講座など、会員向け勉強会の講師
- 補助金申請支援:自治会・町内会活動に関する各種補助金の申請サポート

認可地縁団体申請の具体的なサポート内容
当事務所では、認可地縁団体の申請に関して以下のような具体的なサポートを行っています:
- 現状分析:現在の不動産の登記状況や権利関係の確認
- 申請戦略の立案:最も効率的な申請方法の提案
- 規約作成支援:法律要件を満たす適切な規約の作成
- 総会運営アドバイス:認可申請に必要な総会の運営サポート
- 書類作成代行:申請に必要な各種書類の作成
- 行政との折衝:市町村担当課との打ち合わせ・調整
- 登記申請:認可後の不動産登記申請手続き
お問い合わせ・ご相談について
自治会・町内会の不動産所有に関するお悩みやご相談は、お気軽に当事務所までご連絡ください。初回相談は無料で承っております。また、役員会や総会への出席によるご説明も可能です。
地域コミュニティの発展と円滑な運営のために、専門家としてのサポートを提供いたします。長年の問題を解決し、将来にわたって安心して自治会・町内会活動を続けられるよう、お手伝いいたします。
お電話:077-574-7772(平日9:00-18:00)
自治会・町内会の皆様のご相談を心よりお待ちしております。
🌟 わずか10秒!あなたのその悩み、LINEで即解決しませんか?
相続や登記、会社設立の疑問を抱えたまま、重い腰を上げる必要はありません。
当事務所では、ご多忙な皆様のためにLINE公式アカウントを開設しています。
✅ 【手軽】 氏名や住所の入力は不要。匿名で相談OK!
✅ 【迅速】 お問い合わせから最短5分で司法書士に直接つながります。
✅ 【無料】 もちろん、初回のLINE相談は完全無料です。
▼ 今すぐLINEで友だち追加して、相談を開始!
◇ 当サイトの情報は執筆当時の法令に基づく一般論であり、個別の事案には直接適用できません。
◇ 法律や情報は更新されることがあるため、専門家の確認を推奨します。
◇ 当事務所は情報の正確性を保証せず、損害が生じた場合も責任を負いません。
◇ 情報やURLは予告なく変更・削除されることがあるため、必要に応じて他の情報源もご活用ください。
この記事を書いた人

司法書士・行政書士 和田正俊事務所 代表和田 正俊(Wada Masatoshi)
- 滋賀県司法書士会所属 登録番号 滋賀第441号
- 簡裁訴訟代理関係業務 認定番号 第1112169号
- 滋賀県行政書士会所属
登録番号 第13251836号会員番号 第1220号 - 公益社団法人 成年後見センター・リーガルサポート滋賀支部所属
会員番号 第6509213号
後見人候補者名簿 及び 後見監督人候補者名簿 搭載 - 法テラス契約司法書士
- 近畿司法書士会連合会災害相談員
不動産に関連する記事
【司法書士が徹底解説】個人間の高額融資で絶対に失敗しない!不動産担保(抵当権・譲渡担保)活用の完全ガイド
2025年12月17日
法改正で必須に!登記はメールアドレスで速く
2025年11月10日
司法書士による本人確認手続きの流れと実務のQ&A
2025年12月7日