HPを見たとお伝えください 077-574-7772
077-574-7772
営業時間|9:00~17:00 定休日|土・日・祝
HPを見たとお伝えください 077-574-7772
077-574-7772
営業時間|9:00~17:00 定休日|土・日・祝
相続が発生すると、故人の遺産を確定させるために相続財産調査を行います。預貯金などの金融資産も相続財産であるため、調査対象となります。では、なぜ預貯金の調査にあたり残高証明書の取得が必要なのでしょうか?
それは残高証明書を取得することで、相続発生日における預貯金の残高を、金融機関が発行する公式な書類によって証明できるためです。この正確な残高を把握することが、遺産分割協議や相続税申告を行ううえで非常に重要になります。
こちらでは、相続財産調査で必要となる残高証明書とは何か、具体的な取得方法、そして注意点について詳しく解説していきます。
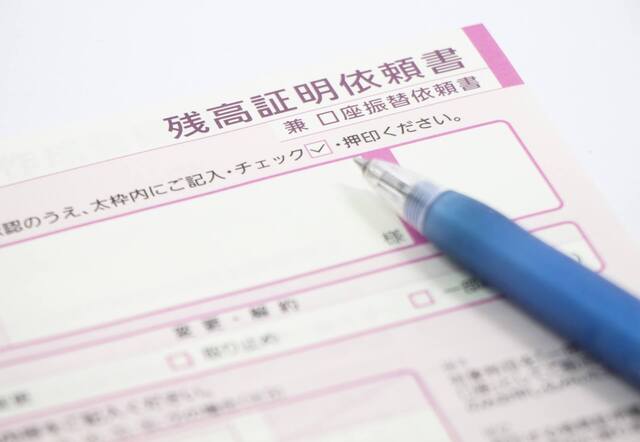
残高証明書とは、特定の日付における預貯金や有価証券、投資信託などの金融資産の額を金融機関が証明する書類です。相続手続きにおいては、亡くなった方がどの金融機関にどれだけの預貯金や有価証券などを持っていたのかを証明する書類となります。
相続手続きでは、遺産分割協議や相続税申告のために、被相続人の財産を把握することが必須です。預貯金や有価証券なども財産の一部であるため、残高証明書によって正確な金額を把握することが重要となります。
残高証明書が必要になるタイミングは、主に遺産分割協議と相続税申告時の2つです。
亡くなった人の遺産を相続人で分け、相続発生時の財産の総額を確認するために必要になります。
相続税の申告には、相続発生時の預貯金の残高を正確に把握し、申告書類に記載する必要があり、その際に残高証明書が必要になります。
残高証明書の請求は、相続人であれば誰でも単独で行うことができます。他の相続人の同意は必要ありません。また、相続人本人でなくても、委任状があれば代理人が申請できます。代理人として申請できるのは、弁護士や司法書士などの専門家や、遺言執行者、相続財産管理人などです。

預貯金などの残高証明書を取得するには、基本的に亡くなった方が口座開設していた金融機関へ問い合わせて、必要書類を提出します。こちらでは、その取得方法を詳しく見ていきましょう。
相続発生後、残高証明書を取得するためには、まずは被相続人が口座を開設していた金融機関に問い合わせるようにしましょう。
多くの金融機関や証券会社は、相続手続きをサポートする専用のダイヤルを設けており、残高証明書の取得を含む相続手続き全般について案内しています。問い合わせ先は、各金融機関のウェブサイトや電話で確認できます。
窓口へ出向いて手続きを行うことも可能ですが、必要書類が揃っていない場合は残高証明書を請求できないため、二度手間になる可能性があります。
残高証明書を取得するには、以下のような書類を金融機関に提出する必要があります。
多くの金融機関では、被相続人の相続関係を一覧にした「法定相続情報一覧図」を提出すると、被相続人や相続人の戸籍謄本は不要になります。
残高証明書の発行手数料は金融機関によって異なりますが、1通あたり1,000円前後が相場です。事前に金融機関に確認しておくとよいでしょう。
残高証明書は、必要書類を金融機関に提出後、1~2週間程度で発行されます。なお、金融機関や時期によっては、さらに時間がかかる場合もあるため、時間に余裕を持って申請する必要があります。
金融機関から残高証明書を取得する手続きは一見シンプルに見えますが、いくつか注意点があり、見落としがあると手続きが二度手間になる可能性もあります。
金融機関によって、残高証明書の発行に必要な書類や手続きが異なる場合があります。まずは、被相続人が口座を開設していた支店に電話で問い合わせることが重要です。相続による取得であることを伝え、必要書類や流れを確認しましょう。金融機関によっては、電話で被相続人の死亡を伝えてからでないと、窓口での手続きを受け付けてもらえない場合があります。
相続の場合、預貯金の評価額は被相続人の死亡日の残高で計算されます。そのため、残高証明書の証明日は被相続人の死亡日を指定することが非常に重要です。証明日を誤ると再発行の手間が発生し、相続税の計算や遺産分割協議が進まなくなってしまいます。
定期預金の場合、残高証明書には元本のみが記載され、死亡日までの利息は含まれていません。利息も相続財産に含まれるため、忘れずに「経過利息計算書」も請求しましょう。
残高証明書の請求によって金融機関は預金者の死亡を認識し、口座は凍結されます。凍結は相続手続きが完了するまで解除されないため、公共料金などの引き落とし口座になっていた場合は、速やかに別の口座に変更する必要があります。
これらの点に注意し、スムーズな相続手続きを進めましょう。
預貯金の調査では、残高証明書の取得以外にも知っておくべきポイントがいくつかあります。
相続開始を知った金融機関は、口座を凍結します。凍結されると、預金の払い出しや引き落としなどができなくなります。
被相続人が複数の金融機関に口座を持っている場合、すべての口座を把握することが重要となります。
生前の取引履歴を確認することで、財産の把握だけでなく、借金の有無や使途不明金がないかなどを調査することもできます。
預貯金以外にも、株式、投資信託、保険など、金融機関で保有している資産がないか調査する必要があります。
これらのポイントを踏まえ、漏れのない相続財産調査を行いましょう。
預貯金などの相続財産調査をスムーズに進めるには、専門家の活用が有効です。弁護士や司法書士、税理士などの専門家は、相続手続きや税務に関する知識を持ち、法的手続きを適切に進めるためのサポートを行います。
預貯金の名寄せや金融機関とのやり取り、複雑な書類の作成などは、専門家に依頼することで効率化が図れ、ミスを防げます。相続手続きでの負担を軽減するためにも、専門家の力を活用することを検討しましょう。
相続財産調査・預貯金などの残高証明書の取得は、相続手続きの最初のステップです。ここまで解説した残高証明書の取得方法や必要書類、注意点などを参考に、円滑な相続手続きを進めましょう。
滋賀県大津市にある和田正俊事務所では、長年の経験を持つ代表が直接対応し、皆様の不安や悩みを解消するお手伝いをいたします。
和田正俊事務所の強みの一つは「良い結果を追求する姿勢」です。複雑なご相談内容でも諦めずに解決方法を模索し、可能な限りご要望にお応えできるようサポートいたします。例えば、相続財産の中でも特に預貯金の調査に関しては、金融機関の口座情報や残高証明書を迅速かつ正確に取得することができます。また、凍結口座の払い戻しや名義変更手続きのサポートも可能です。
さらに、他士業との連携も私たちの大きな強みです。相続に伴う問題は多岐にわたりますが、和田正俊事務所では他士業の専門家と連携し、必要に応じてご紹介することが可能です。これにより、専門的な知識が求められる場面でもスムーズに問題を解決できます。
また、初回60分の出張相談を無料で対応し、遠方の方や移動が難しい方でも、気軽にご相談いただける環境を整えております。リーズナブルな料金体系を設定しており、費用面での心配も最小限に抑えられます。
相続が発生した、もしくは近いうちに発生することが見込まれるという状況に直面している方々にとって、和田正俊事務所は頼れる存在です。相続財産調査、預貯金口座の特定に関する手続きの手順や必要な書類、注意すべきポイントなど、具体的で網羅的な情報を提供いたします。
滋賀で相続に関するお悩みや疑問がある方は、以下のリンクからお問い合わせください。和田正俊事務所が全力でサポートいたします。
| 事務所名 | 司法書士・行政書士 和田正俊事務所 |
|---|---|
| 住所 | 〒520-2134 滋賀県大津市瀬田5丁目33−4 |
| TEL | 077-574-7772 |
| FAX | 077-574-7773 |
| URL | https://wada7772.com/ |
| 営業時間 | 9:00~17:00 |
| 定休日 | 土・日・祝(事前予約により対応させていただきます。) |
| 取扱業務 |
|