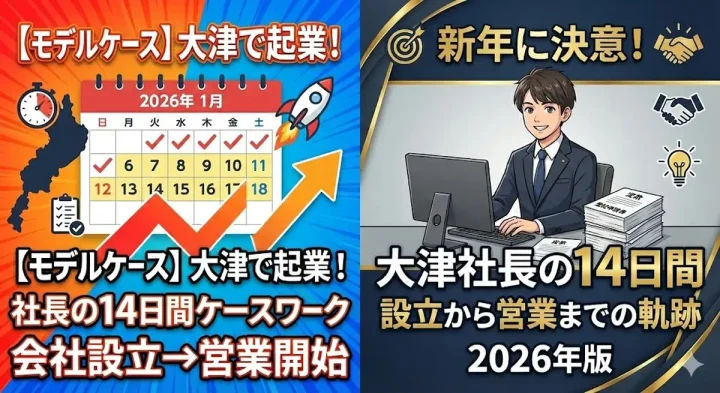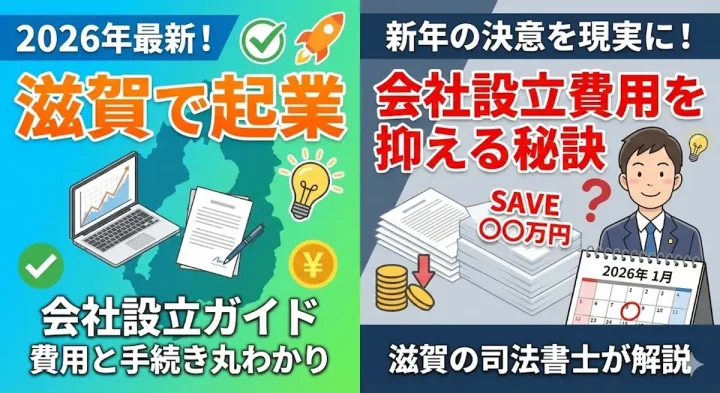事業承継における遺留分問題の対処法
この記事のポイント
- 事業承継において遺留分は重大な障害となる可能性がある
- 早期からの計画と家族間のコミュニケーションが重要
- 株式の評価と適切な資産配分による対策が有効
- 生命保険や生前贈与などの資金対策も検討すべき
- 専門家の助言を得ながら法的対応を準備する
1. 事前の計画と相続人への説明
後継者の選択と遺言の作成
後継者の明確化は重要です。誰を後継者とするかを事前に決め、他の相続人にもその理由や意図を十分に説明します。遺言書を作成することで、後継者に自社株を集中的に相続させる意図を明確にし、遺留分への配慮も記載します。
遺言書作成のポイント
- 公正証書遺言が最も確実(自筆証書遺言は無効リスクあり)
- 後継者への株式集中の意図を明確に記載
- 他の相続人への遺留分対策も明記
- 定期的な見直しと更新
- 保管場所を家族に伝えておく
相続人への説明のコツ
- 事業継続の重要性を丁寧に説明
- 株式分散がもたらすリスクの共有
- 後継者選定の合理的理由の提示
- 他の相続人への配慮を示す
- 定期的な情報共有と対話の機会を設ける
2. 株式の分散と維持
適切な株式の配分
自社株の評価を専門家に依頼し、適切な金額の株式を後継者に譲渡または贈与することを考慮します。遺留分として株式以外の資産を考慮し、後継者以外の相続人には可能な限り現金や不動産などの異なる資産を遺すようにします。
| 株式評価方法 | 特徴 | 適する企業タイプ |
|---|---|---|
| 純資産価額方式 | 会社の純資産(資産-負債)に基づく評価 | 資産型企業、不動産保有会社 |
| 類似業種比準方式 | 同業種の上場企業との比較による評価 | 収益性の高い事業会社 |
| 配当還元方式 | 配当額に基づく評価 | 同族以外の少数株主持分 |
| DCF法 | 将来キャッシュフローの現在価値 | M&A時の企業価値評価 |
3. 親族内合意の形成
家族会議の実施
家族全員での話し合いを定期的に行い、将来的な事業ビジョンや個々の役割について意識を共有します。事前に合意書を作成し相続が発生した際の承継内容について親族の合意を取り付けておきます。
事例:小売業A社の家族会議
創業40年の小売業A社では、創業者が65歳になった時点から毎月1回の家族会議を開始。社長の長男(後継者)、次男(別事業担当)、長女(非同族)とその配偶者も含めた話し合いを実施。会議では事業状況の共有だけでなく、将来の株式配分や役割分担、相続発生時の対応なども話し合った。
この結果、遺留分に関する基本合意書を作成。長男には株式と事業用資産、次男には新規事業と投資用不動産、長女には現金と居住用不動産を分配する計画に全員が合意。相続発生後も遺留分を巡るトラブルなく事業承継が完了した。
4. 保険の活用
生命保険を使った資金準備
生命保険を活用して、相続発生時に発生する遺留分への支払い資金を事前に準備することができます。これにより、現金流動性の確保を図ります。
生命保険活用のメリット
- 相続財産に含まれない:死亡保険金は受取人固有の財産として遺留分算定の基礎財産に含まれない場合がある
- 即時の現金化:相続発生後すぐに現金が手に入る
- 納税資金の確保:相続税や遺留分の支払い資金として活用可能
- 計画的な準備:必要資金を事前に見積もり準備できる
保険設計のポイント
- 受取人の指定:相続人ごとの公平性を考慮した設計
- 保険金額の設定:想定される遺留分減殺請求額を見積もる
- 契約者・被保険者の設定:税務上の効果を最大化する組み合わせ
- 保険種類の選択:終身保険、定期保険、養老保険など目的に合わせた選択
- 保険料の負担者:会社負担か個人負担かの検討
5. 法的手続きの準備
弁護士や専門家の相談
司法書士や弁護士の専門的なアドバイスを受け、遺留分問題について法的に対応できるよう準備を進めます。遺留分減殺請求が起こった場合に備え、しっかりとした法的対応策を考えておきます。
遺留分減殺請求への法的対応
- 遺留分算定の基礎財産の確定
- 相続開始時の財産
- 相続開始前1年間の贈与財産
- 相続人に対する生前贈与(期間制限なし)
- 遺留分侵害額の計算方法の検討
- 遺留分算定の基礎財産の価額×法定相続分×1/2
- 株式評価方法の適切な選択
- 支払い方法の協議
- 現物返還か価額弁償か
- 分割払いの可能性
- 時効の管理
- 遺留分侵害を知ってから1年
- 相続開始から10年
6. 生前贈与の活用
贈与税の非課税枠の利用
生前に非課税枠を活用しつつ、計画的に株式を後継者に贈与することで、遺留分問題を事前に軽減できます。教育資金贈与などの非課税制度を活用します。
| 贈与制度 | 非課税枠 | 特徴と注意点 |
|---|---|---|
| 暦年贈与 | 年間110万円 | 毎年継続的に贈与可能、計画的な資産移転に有効 |
| 相続時精算課税制度 | 2,500万円まで | 60歳以上の親から18歳以上の子への贈与、相続時に精算 |
| 教育資金贈与 | 1,500万円まで | 30歳未満の孫等への教育資金、使途制限あり |
| 結婚・子育て資金贈与 | 1,000万円まで | 50歳未満の子・孫への結婚・子育て資金、使途制限あり |
| 事業承継税制 | 非上場株式等 | 一定条件下で納税猶予・免除、事前の計画策定が必要 |
まとめ:遺留分対策は早期の計画が鍵
事業承継における遺留分問題は、早期からの計画的な対応が不可欠です。以下のステップで対策を進めましょう:
- 現状把握:自社株式の評価額算定と遺留分算定の基礎財産の確認
- 対策の検討:専門家チームによる総合的な対策立案
- 家族との対話:定期的な家族会議での情報共有と合意形成
- 段階的実行:生前贈与、保険活用、遺言作成などの順次実施
- 定期的見直し:環境変化や法改正に応じた計画の更新
遺留分問題は、事業承継の大きな障害となる可能性がありますが、適切な対策を講じることで円滑な事業承継を実現できます。お早めに専門家へご相談ください。
■■□―――――――――――――――――――□■■
司法書士・行政書士和田正俊事務所
【住所】 〒520-2134 滋賀県大津市瀬田5丁目33番4号
【電話番号】 077-574-7772
【営業時間】 9:00~17:00
【定休日】 日・土・祝
■■□―――――――――――――――――――□■■
法人・会社に関連する記事
【ケーススタディ】大津市で新年に起業した社長の14日間|会社設立から営業開始まで密着レポート
2026年1月12日
【2026年最新】滋賀県で起業する完全ガイド|会社設立の手続きと費用を司法書士が徹底解説
2026年1月5日
事業目的を追加・変更する登記。費用と期間、必要書類
2025年11月20日