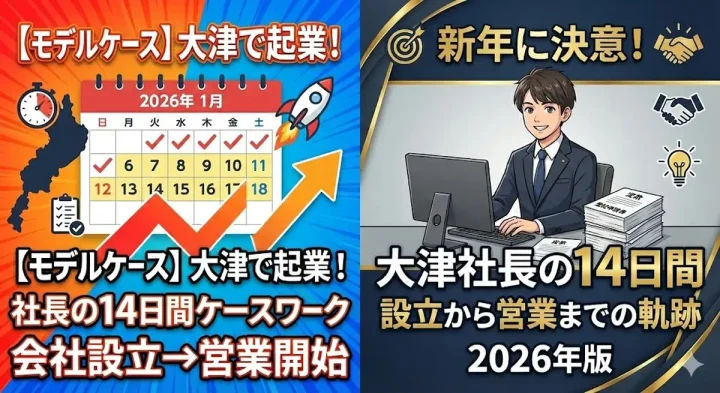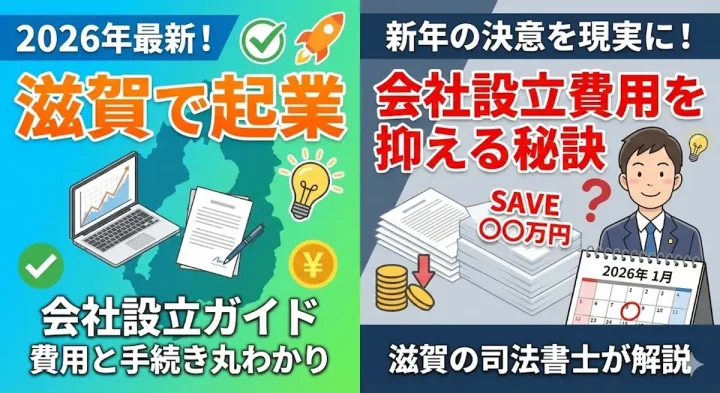取締役・監査役の任期について - 株式会社における役員任期の基本と実務上の注意点
株式会社の役員である取締役や監査役には、法律で定められた「任期」があります。この任期は単なる形式的な期間ではなく、コーポレートガバナンスや登記手続きに大きく関わる重要事項です。本記事では、会社法に基づく取締役・監査役の任期の基本ルールから、実務上の注意点、さらには登記を怠った場合のリスクまで、登記実務の専門家の視点から詳しく解説します。
本記事のポイント:
- 取締役・監査役の法定任期とその伸長可能性
- 任期設定における実務上の考慮点
- 役員変更登記を怠った場合のリスク(過料と「みなし解散」)
- 適切な任期管理の重要性
取締役の任期 - 基本ルールと特例
会社法の施行前(平成18年5月以前)は、株式会社の取締役の任期は一律「2年」と定められていました。しかし、会社法施行後は、条件によって最長10年まで任期を伸長できるようになりました。
取締役の法定任期
会社法第332条では、取締役の任期について次のように規定しています:
会社法第332条(取締役の任期)
1 取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。ただし、定款又は株主総会の決議によって、その任期を短縮することを妨げない。
2 前項の規定は、公開会社でない株式会社(委員会設置会社を除く。)において、定款によって、同項の任期を選任後10年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで伸長することを妨げない。

任期の計算方法
取締役の任期は単純に「2年間」ではなく、「選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで」と規定されています。これは実務上どのように計算するのでしょうか?
【具体例】3月決算会社の場合
2023年6月25日の定時株主総会で取締役に選任された場合:
- 選任日:2023年6月25日
- 選任後2年以内に終了する事業年度:2025年3月期
- その定時株主総会:2025年6月頃に開催予定
- 実際の任期:約2年(2023年6月25日〜2025年6月の定時株主総会終結時)
実際の任期は、選任された時期と事業年度の関係によって、2年より若干長くなったり短くなったりします。
任期の伸長要件
取締役の任期を最長10年まで伸長できるのは、以下の条件をすべて満たす場合に限られます:
- 公開会社でないこと:株式の譲渡制限がある会社(非公開会社)であること
- 委員会設置会社(指名委員会等設置会社)でないこと
- 定款に任期伸長の規定があること:「取締役の任期は、選任後10年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする」などの規定が必要
これらの条件を満たさない場合(公開会社や指名委員会等設置会社)は、法定の2年を超える任期設定はできません。
監査役の任期 - 基本ルールと特例
監査役についても、会社法施行前は一律「4年」と定められていましたが、会社法施行後は条件付きで最長10年まで伸長可能となりました。
監査役の法定任期
会社法第336条では、監査役の任期について次のように規定しています:
会社法第336条(監査役の任期)
1 監査役の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。
2 前項の規定は、公開会社でない株式会社において、定款によって、同項の任期を選任後10年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで伸長することを妨げない。

監査役の任期伸長の条件
監査役の任期を最長10年まで伸長できるのは、以下の条件を満たす場合です:
- 公開会社でないこと:株式の譲渡制限がある会社であること
- 定款に任期伸長の規定があること
なお、監査役設置会社か否かにかかわらず、公開会社でなければ任期伸長が可能です。
任期を10年とするのは本当に正しい選択か?
非公開会社では、役員の任期を10年に伸長することが可能ですが、実務上はそれが最適な選択とは限りません。任期設定にあたって考慮すべきポイントを検討しましょう。
任期を長くするメリット
- 登記手続きの負担軽減:役員変更登記の頻度が減り、手続きの手間と費用を節約できる
- 株主総会運営の簡素化:役員選任議案を頻繁に上程する必要がない
- 経営の安定性:長期的な視点での経営が可能になる
任期を長くするデメリット
- 登記申請の失念リスク:10年という長期間で登記期限を忘れるリスクが高まる
- ガバナンス上の問題:定期的な株主による信任機会が減少する
- みなし解散のリスク:登記を12年間行わないと「みなし解散」のリスクが生じる

実務上のバランス:
実務上のバランスを考慮すると、10年という最長期間ではなく、以下のような中間的な設定も検討価値があります:
- 取締役:3〜5年:基本任期の2年より長く、かつ管理しやすい期間
- 監査役:5〜7年:基本任期の4年より長く、かつ管理しやすい期間
また、役員の任期満了時期を揃えておくと、一括して役員変更登記を行えるため効率的です。
過料よりもっと恐ろしい「みなし解散」
役員の任期満了にともなう変更登記を怠ると、過料(行政罰)が科される可能性がありますが、それ以上に恐ろしいのが「みなし解散」の制度です。
変更登記を怠った場合の過料
会社法第909条および第976条により、登記事項に変更が生じた場合は遅滞なく変更登記を行う義務があり、これを怠ると100万円以下の過料に処せられる可能性があります。
会社法第909条(変更の登記及び消滅の登記)
この法律の規定により登記した事項に変更が生じ、又はその事項が消滅したときは、当事者は、遅滞なく、変更の登記又は消滅の登記をしなければならない。
会社法第976条(過料に処すべき行為)
発起人、設立時取締役、設立時監査役、設立時執行役、取締役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員、監査役、執行役、会計監査人...は、次のいずれかに該当する場合には、百万円以下の過料に処する。ただし、その行為について刑を科すべきときは、この限りでない。
一 この法律の規定による登記をすることを怠ったとき。
休眠会社のみなし解散制度
会社法第472条に基づき、12年間一度も登記申請を行わなかった会社は「休眠会社」とみなされ、法務大臣の公告から2ヶ月以内に届出をしないと自動的に解散したものとみなされます。
会社法第472条(休眠会社のみなし解散)
休眠会社(株式会社であって、当該株式会社に関する登記が最後にあった日から十二年を経過したものをいう。以下この条において同じ。)は、法務大臣が休眠会社に対し二箇月以内に法務省令で定めるところによりその本店の所在地を管轄する登記所に事業を廃止していない旨の届出をすべき旨を官報に公告した場合において、その届出をしないときは、その二箇月の期間の満了の時に、解散したものとみなす。ただし、当該期間内に当該休眠会社に関する登記がされたときは、この限りでない。

解散登記がもたらす深刻な問題
みなし解散により会社に解散登記がなされると、以下のような深刻な問題が発生します:
- 代表者の印鑑証明書が取得できなくなる:解散登記により代表取締役は当然退任するため
- 通常の商取引ができなくなる:印鑑証明書が必要な契約が締結できない
- 銀行取引に支障が生じる:新規融資が受けられない、既存の融資が一括返済を求められる可能性
- 取引先からの信用を失う:登記事項証明書に解散の記載があることで取引を断られる
実際のケースに見る深刻な影響:
- 「明日の重要な取引のために会社の印鑑証明書を取りに行ったが、みなし解散により取得できず、取引が不成立に」
- 「取引銀行から印鑑証明書を要求されたが取得できず、運転資金がショートして倒産の危機に」
- 「新規取引先が取得した登記事項証明書に解散の記載があり、信用不安から取引を断られた」
これらは実際に起こり得る深刻な事態です。
みなし解散後の救済措置
みなし解散となった場合でも、会社法第473条に基づく「会社の継続」という救済措置があります:
会社法第473条(株式会社の継続)
株式会社は、第四百七十一条第一号から第三号までに掲げる事由によって解散した場合(前条第一項の規定により解散したものとみなされた場合を含む。)には、次章の規定による清算が結了するまで(同項の規定により解散したものとみなされた場合にあっては、解散したものとみなされた後三年以内に限る。)、株主総会の決議によって、株式会社を継続することができる。
ただし、この救済措置を使う場合でも:
- みなし解散から3年以内に手続きを行う必要がある
- 過料のペナルティは免れない可能性が高い
- 取引への影響や信用低下などの実害は既に発生している
したがって、みなし解散を避けるための予防的措置が非常に重要です。
法務省による休眠会社整理作業
法務省は定期的に「休眠会社・休眠一般法人の整理作業」を実施しており、最後の登記から12年経過した株式会社が対象となります。
休眠会社・休眠一般法人の整理作業とは:
法務省が全国の法務局で実施する一斉整理作業で、以下が対象となります:
- 最後の登記から12年を経過している株式会社(会社法第472条の休眠会社。特例有限会社は含まれません)
- 最後の登記から5年を経過している一般社団法人または一般財団法人
該当する会社等は、公告日から2ヶ月以内に「まだ事業を廃止していない」旨の届出または登記申請を行わないと、解散したものとみなされ、登記官が職権で解散の登記を行います。
法務局から「休眠会社に関する通知」を受け取った場合は、速やかに対応することが重要です。通知を無視すると、会社が自動的に解散状態になり、事業継続に大きな支障をきたします。
適切な役員任期設定と登記管理のポイント
以上の内容を踏まえ、役員の任期設定と登記管理における実務上のポイントをまとめます:
適切な任期設定の考え方
- 会社の実情に合わせた設定:単に最長期間(10年)を選ぶのではなく、会社の実情に合わせた適切な期間を設定する
- 管理しやすい期間の検討:2年(取締役)・4年(監査役)の基本任期、または5年程度の中間的な期間など、忘れにくい区切りの良い期間を検討する
- 役員間の任期の調整:可能であれば取締役と監査役の任期満了時期を揃えることで、登記手続きを効率化できる
登記管理のベストプラクティス
- 登記カレンダーの作成:役員の任期満了日や登記期限を記載したカレンダーを作成し、定期的にチェックする
- 登記履歴の管理:最後に登記を行った日付を記録し、長期間登記がない場合のアラートを設定する
- 登記の定期的な実行:役員変更がなくても、住所変更や目的変更など、定期的に何らかの登記を行うことでみなし解散リスクを回避する
- 専門家との連携:司法書士などの専門家と定期的に連携し、登記状況の確認や必要な対応を相談する
実務上の工夫:
会社の登記を最低でも10年に1回は必ず行うようにするための工夫として、以下のような方法が考えられます:
- 取締役の任期を5年、監査役の任期を6年など、ずらして設定することで、定期的に何らかの役員変更登記が発生するようにする
- 5年ごとに定款変更(目的の微修正など)を行う習慣をつける
- 法人の決算月に合わせて「登記確認月間」を設け、年1回は登記状況を確認する
商業・法人登記のプロフェッショナルによるサポート
会社の役員任期管理や登記申請は、法的知識と実務経験が求められる専門的な業務です。当事務所では、以下のようなサポートを提供しています:
- 役員変更登記の代行:任期満了や辞任、新任に伴う役員変更登記を迅速・確実に代行
- 定款変更のサポート:役員任期の適切な設定のための定款変更をサポート
- 登記スケジュール管理:役員任期や登記期限の管理サービス
- みなし解散対応:休眠会社通知を受けた場合の対応サポート
- その他の法人登記:商号変更、目的変更、本店移転などの各種登記申請
- 登記事項証明書の取得代行:必要な証明書の迅速な取得
役員任期や登記に関するご質問やお悩みがございましたら、お気軽に当事務所までご相談ください。専門的な知識と経験を活かし、最適なアドバイスとサポートを提供いたします。

司法書士・行政書士和田正俊事務所
住所:〒520-2134 滋賀県大津市瀬田5丁目33番4号
電話番号:077-574-7772
営業時間:9:00~17:00
定休日:日・土・祝
役員任期や会社登記に関するご相談は、お電話またはメールにてお気軽にお問い合わせください。
まとめ - 役員任期と登記管理の重要性
会社の役員である取締役・監査役の任期は、単なる形式的な期間ではなく、会社運営において重要な意味を持ちます。任期設定を適切に行い、それに伴う登記を確実に実施することは、経営者の重要な法的義務であり、会社の健全な運営に直結します。
特に注意すべきは以下の点です:
- 10年という最長任期が必ずしも最適ではない:管理のしやすさや実務上のリスクを考慮した適切な期間設定を
- 登記を怠ることによる二重のリスク:100万円以下の過料と、12年間登記を行わない場合のみなし解散
- みなし解散が会社経営に与える深刻な影響:印鑑証明書が取得できず、通常の事業活動が困難になる
- 定期的な登記状況の確認と計画的な対応の重要性:少なくとも10年に1回は何らかの登記を行う習慣を
会社運営において、登記は単なる法的手続きではなく、会社の存続と円滑な事業活動を支える重要な基盤です。役員任期と登記管理に関する適切な知識を持ち、計画的に対応することで、思わぬトラブルや事業リスクを回避することができます。
当事務所では、中小企業の皆様の会社運営をサポートするため、登記に関する専門的なアドバイスと手続き代行を提供しています。会社の役員任期や登記に関してお悩みやご不明点がありましたら、ぜひお気軽にご相談ください。
最後に一言:
会社の登記は、「面倒だから後回し」にしがちな業務ですが、実は会社の「健康診断」のようなものです。定期的に確認し、必要な手続きを行うことで、会社の健全な運営を維持できます。「登記は会社の命綱」と心得て、適切な管理を心がけましょう。
法人・会社に関連する記事
【ケーススタディ】大津市で新年に起業した社長の14日間|会社設立から営業開始まで密着レポート
2026年1月12日
【2026年最新】滋賀県で起業する完全ガイド|会社設立の手続きと費用を司法書士が徹底解説
2026年1月5日
事業目的を追加・変更する登記。費用と期間、必要書類
2025年11月20日