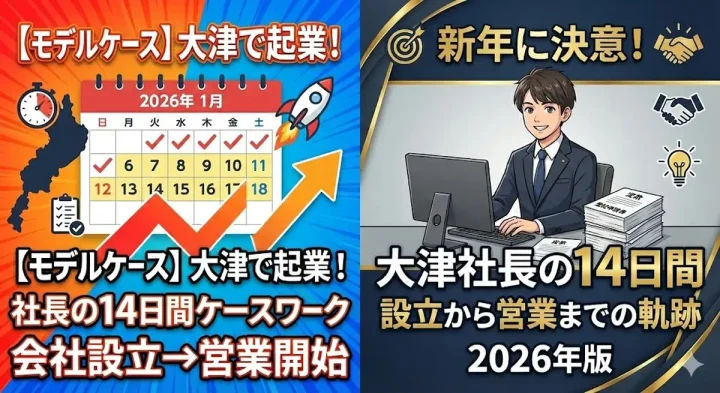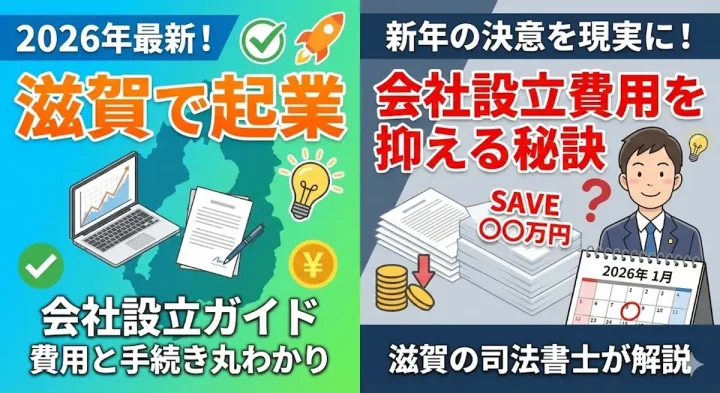株式譲渡契約書と株券が見当たらない場合の対処法
この記事のポイント
- 株式譲渡契約書の重要性と基本的な記載事項
- 株券が見当たらない場合の法的対処方法と具体的な手続き
- 電子化が進む現代での株券不在時の実務的な対応策
- 譲渡制限株式と自由譲渡株式それぞれの対応の違い
- 株式譲渡に関するトラブルを防ぐための予防策
株式譲渡契約書は、株式の譲渡に関する重要な書類であり、特に譲渡制限株式の場合には、適切な手続きを踏むことが求められます。しかし、昨今の電子化の流れや会社法改正の影響で、実際には株券が発行されていなかったり、発行されていても見当たらなかったりするケースが増えています。本記事では、株式譲渡契約書の基本と、株券が見当たらない場合の対処法について詳しく解説します。
株式譲渡契約書の基本
株式譲渡契約書は、株式の売買における権利と義務を明確にするための書類です。特に譲渡制限株式の場合、会社の承認が必要となるため、契約書には以下のような内容が含まれます。譲渡に関するトラブルを未然に防ぐためにも、詳細かつ明確な契約書の作成が重要です。
株式譲渡契約書に含まれる主な事項
- 譲渡する株式の詳細:株式数、株式の種類、一株あたりの金額など
- 譲渡価格と支払い条件:総額、支払方法、支払期限、分割払いの場合の条件など
- 譲渡の条件や制限事項:表明保証条項、競業避止義務、守秘義務など
- 会社の承認に関する条項:譲渡制限株式の場合の会社承認手続き
- 株主名簿書換えに関する事項:名義書換の時期と手続き
- 株券の引渡し:株券の有無、引渡し時期と方法
- 契約不履行時の対応:違約金、解除条件など
- 紛争解決方法:管轄裁判所、調停前置などの合意
譲渡制限株式と自由譲渡株式の違い
株式譲渡契約書を作成する前に、対象となる株式が譲渡制限株式か自由譲渡株式かを確認することが重要です。両者では手続きや必要な承認が異なります。
譲渡制限株式と自由譲渡株式の比較
| 項目 | 譲渡制限株式 | 自由譲渡株式 |
|---|---|---|
| 譲渡の承認 | 会社の承認が必要 | 会社の承認不要 |
| 譲渡手続き | 譲渡承認請求→取締役会決議→通知 | 当事者間の合意のみで有効 |
| 対抗要件 | 株主名簿の書換が必要 | 株主名簿の書換が必要 |
| 一般的な企業形態 | 非上場会社(中小企業)に多い | 上場会社に多い |
株式譲渡契約書の効力
株式譲渡契約書は、株式譲渡の当事者間の権利義務関係を明確にする重要な書面です。しかし、契約書の作成・締結だけでは株式譲渡の法的効力が完全に発生するわけではありません。
株式譲渡の法的効力と対抗要件
1. 当事者間の効力:株式譲渡契約の締結により、譲渡人と譲受人の間では株式譲渡の効力が発生します。
2. 会社に対する効力:
- 自由譲渡株式の場合:株主名簿の書換えがなくても会社に対して株主としての権利行使が可能
- 譲渡制限株式の場合:会社の承認と株主名簿の書換えが必要
3. 第三者に対する対抗要件:株券が発行されている場合は株券の交付、発行されていない場合は株主名簿の書換えが第三者に対する対抗要件となります。
つまり、完全な株式譲渡の効力を発生させるためには、契約書の作成だけでなく、会社の承認(譲渡制限株式の場合)、株券の交付(発行されている場合)、株主名簿の書換えなどの手続きが必要です。
実務上の注意点
株式譲渡契約書を作成する際には、以下の点に注意が必要です。
作成時の実務上の注意点
- 譲渡価格の妥当性:特に同族会社間の取引では、税務上の問題を避けるため、適正な価格設定が重要です。
- 表明保証条項:譲渡人が株式に関する事実(有効な発行、担保権の不存在など)を保証する条項を入れることで、将来のトラブルを防止できます。
- 税務上の取扱い:株式譲渡所得に対する課税関係を事前に確認し、必要に応じて契約書に明記しておくことが望ましいです。
- 株主間契約との整合性:既存の株主間契約がある場合、それとの整合性を確認する必要があります。
- 定款の確認:会社の定款に特別な譲渡制限や手続きが定められていないか確認しましょう。
- 株券の有無の確認:株券が発行されているか否かを事前に確認し、契約書に株券の引渡しに関する条項を適切に記載します。
株券が見当たらない場合の対処法
株券が見当たらない場合でも、株式の譲渡を行うことは可能です。しかし、状況に応じた適切な対処が必要です。以下に、株券が見当たらない場合の対処法を紹介します。
株券不所持の確認
まず、株券が本当に発行されているかどうかを確認します。株券が発行されていない場合は、株主名簿の記載をもって株主としての権利を主張できます。
株券発行の確認方法
- 会社への問い合わせ:会社の代表取締役や担当者に株券発行の有無を確認する
- 定款の確認:定款に「株券を発行する」旨の規定があるか確認する
- 株主名簿の確認:株主名簿に株券番号の記載があれば、株券が発行されている可能性が高い
- 会社法施行日(2006年5月)前後の状況確認:会社法施行後に設立された会社は原則として株券不発行(ただし定款で定めれば発行可能)
株券不発行制度について
2006年5月に施行された会社法により、株式会社は原則として株券を発行しないこととなりました(「株券不発行制度」)。ただし、定款で「株券を発行する」と定めれば発行は可能です。
株券不発行の会社では、株主名簿の記載が株主の権利を証明する唯一の手段となります。したがって、株主名簿の記載を確認し、適切に名義書換の手続きを行うことが重要です。
また、会社法施行前に設立された会社でも、定款変更により「株券を発行しない」旨を定めることができます。この場合、既に発行された株券は効力を失います。
株券喪失登録の申請
株券が発行されているが見当たらない場合は、株券喪失登録を申請します。これは、株券を紛失したことを公的に認めてもらう手続きです。申請には、所定の書類と手数料が必要です。
株券喪失登録制度から株券失効手続きへの変更
かつては「株券喪失登録制度」が存在しましたが、会社法施行に伴い「株券失効手続」に変更されました。この手続きは、紛失した株券を無効とし、新たな株券の発行を受けるための制度です。
株券失効手続きの流れ:
- 株券所持人(株主)が株券を紛失した場合、会社に「株券喪失」の届出をする
- 会社は株券失効手続の申立てを行うよう株主に指示する
- 株主は地方裁判所に「公示催告の申立て」を行う
- 裁判所は「公示催告」を行い、一定期間経過後に「除権判決」を下す
- 株主は除権判決を会社に提出し、新株券の発行を請求する
この手続きは時間と費用がかかるため、非上場会社の場合は、定款変更により「株券を発行しない」旨を定め、株券の効力を失わせる方法も検討する価値があります。
株主名簿の書き換え
株券喪失登録が完了したら、株主名簿の書き換えを行います。これにより、新たな株主としての権利が正式に認められます。
株主名簿書換手続きの流れ
- 書換請求書の提出:譲受人(新株主)は、会社に対して株主名簿書換請求書を提出します。
- 必要書類の添付:
- 株式譲渡契約書(または譲渡証書)
- 譲渡人の印鑑証明書
- 株券(発行されている場合)または除権判決謄本
- 譲渡承認書(譲渡制限株式の場合)
- 会社による確認:会社は提出された書類を確認し、問題がなければ株主名簿の書換えを行います。
- 新株主への通知:書換完了後、会社から新株主に通知が行われます。
株券が見当たらない場合でも、株券が発行されていないことが確認できれば、株式譲渡契約書と必要書類の提出により株主名簿の書換えが可能です。ただし、株券が発行されている場合は、原則として株券の提出または株券失効手続きが必要となります。
会社の承認を得る
譲渡制限株式の場合、会社の承認が必要です。株券が見当たらない場合でも、会社に事情を説明し、承認を得ることが重要です。
譲渡承認の手続き
- 譲渡承認請求:譲渡人または譲受人が会社に対して譲渡承認請求を行います。
- 取締役会決議:譲渡制限株式の場合、取締役会(または株主総会)で譲渡の承認について決議します。
- 通知:会社は決議結果を譲渡人・譲受人に通知します。
承認拒否の場合:会社が譲渡を承認しない場合、会社は譲渡人に対して買取人を指定するか、自社で買い取る必要があります(会社法第142条)。
実務上の対応策
譲渡制限株式の譲渡において、株券が見当たらない場合の実務上の対応策として、以下の方法が考えられます:
- 事前協議:譲渡を検討する段階で、会社(取締役会)と事前に協議し、株券不在の状況を説明する。
- 株主総会の活用:可能であれば、株主総会で譲渡承認と株券不発行への定款変更を同時に決議する。
- 誓約書の提出:譲渡人が「株券を所持していない」旨の誓約書を会社に提出する。
- 株券の効力を失わせる措置:定款変更により株券不発行会社とし、既発行株券の効力を失わせる。
- 条件付き承認:「株券失効手続き完了を条件に承認する」といった条件付きの承認を得る。
これらの方法は、会社の規模や株主構成、会社と株主の関係性などによって適切な選択が異なります。状況に応じた柔軟な対応が求められます。
株券不在時の実務的な対応例
株券が見当たらない場合の実務的な対応方法について、いくつかの具体的なケースを紹介します。
ケース1: 株券不発行会社の場合
状況:株券を発行していない会社の株式を譲渡する場合
対応策:
- 会社に株券不発行の確認を取る(定款や株主名簿で確認)
- 株式譲渡契約書を作成し、当事者間で締結する
- 譲渡制限株式の場合は会社の承認を得る
- 株主名簿書換請求を行い、必要書類を提出する
- 会社が株主名簿を書き換え、新株主としての権利が確定する
ポイント:株券不発行会社では、株主名簿の書換えが第三者に対する対抗要件となります。書換手続きを速やかに行いましょう。
ケース2: 株券紛失の場合
状況:株券が発行されているが、紛失してしまった場合
対応策:
- 株券失効手続きを行う(公示催告の申立てと除権判決の取得)
- 株式譲渡契約書に「株券は紛失しており、除権判決取得後に引渡す」旨を記載
- 除権判決取得後、譲渡制限株式の場合は会社の承認を得る
- 除権判決に基づき新株券の発行を受け、譲受人に引き渡す
- 株主名簿の書換手続きを行う
ポイント:株券失効手続きには時間がかかるため、契約書に手続完了までの権利義務関係を明記しておくことが重要です。
ケース3: 定款変更による対応
状況:株券発行会社だが、株券が見当たらず、手続きを簡略化したい場合
対応策:
- 株主総会を開催し、「株券を発行しない」旨の定款変更を決議する
- 定款変更により既発行株券の効力が失われる
- 株式譲渡契約書を作成・締結する
- 譲渡制限株式の場合は会社の承認を得る
- 株主名簿の書換手続きを行う
ポイント:この方法は、全株主の協力が得られる小規模な会社で特に有効です。株券失効手続きよりも時間と費用を節約できます。
ケース4: 株主全員の同意による特例
状況:小規模な同族会社で株主が少数の場合
対応策:
- 株主全員の同意書を作成し、株券不在でも譲渡を認める旨の合意を取り付ける
- 株式譲渡契約書に株主全員の同意がある旨を記載する
- 譲渡制限株式の承認と株主名簿書換えを同時に行う
- 株主全員の同意書と共に書換請求を行う
ポイント:法的には完全ではありませんが、実務上は株主全員の合意があれば問題なく処理できることが多いです。将来のトラブル防止のため、同意書は公正証書にすることも検討しましょう。
株券不在時の株式譲渡契約書における特別条項
株券が見当たらない場合、株式譲渡契約書に以下のような特別条項を設けることで、将来のトラブルを防止することができます。
【株券不在に関する条項例】
1. 株券不発行会社の場合
第○条(株券の不存在)
甲及び乙は、本件株式について会社が株券を発行していないことを相互に確認する。よって、甲は乙に対して株券を交付する義務を負わず、本契約に基づく株式譲渡は株主名簿の名義書換をもって完了するものとする。
2. 株券紛失の場合
第○条(株券の紛失と手続)
1. 甲は、本件株式に係る株券を紛失したことを表明し、本契約締結後速やかに株券失効手続を開始することを約束する。
2. 甲は、除権判決を取得次第、会社に対して新株券の発行を請求し、発行された新株券を直ちに乙に引き渡すものとする。
3. 本契約に基づく株式譲渡の効力は本契約締結時に発生するが、乙が会社及び第三者に対して株主としての権利を対抗するためには、除権判決の取得及び株主名簿の書換が必要であることを甲乙双方は了解する。
3. 定款変更を予定している場合
第○条(株券不発行への定款変更)
1. 甲は、本契約締結後速やかに会社に対して株券を発行しない旨の定款変更を株主総会に諮るよう請求することを約束する。
2. 前項の定款変更が行われた場合、既発行株券は効力を失うものとし、甲は乙に対して株券を引き渡す義務を免れる。
3. 乙は、前項の定款変更後、会社に対して株主名簿の書換請求を行うものとする。
4. 表明保証条項
第○条(表明及び保証)
1. 甲は、本件株式について以下の事項を表明し保証する。
(1) 甲が本件株式の適法かつ完全な所有者であること
(2) 本件株式について、質権その他いかなる担保権も設定されていないこと
(3) 本件株式について、第三者に対して譲渡、売却その他の処分を行う義務を負っていないこと
(4) 本件株式に係る株券を紛失した場合であっても、当該株券を第三者に譲渡していないこと
2. 前項の表明保証に反する事実が判明した場合、甲は乙に対して生じた一切の損害を賠償するものとする。
株式譲渡契約書のサンプル
株券が見当たらない場合を想定した株式譲渡契約書のサンプルを以下に示します。実際に使用する際は、個別の状況に応じて適宜修正してください。
株式譲渡契約書
譲渡人○○○○(以下「甲」という。)と譲受人△△△△(以下「乙」という。)は、甲所有の株式会社□□□□(以下「本件会社」という。)の株式譲渡に関し、以下のとおり契約(以下「本契約」という。)を締結する。
第1条(譲渡株式)
甲は、甲が所有する以下の株式(以下「本件株式」という。)を乙に譲渡し、乙はこれを譲り受ける。
- (1) 会社名:株式会社□□□□
- (2) 所在地:○○県○○市○○町○丁目○番○号
- (3) 発行済株式総数:○○○株
- (4) 譲渡株式数:○○○株
- (5) 株式の種類:普通株式
- (6) 譲渡制限の有無:あり
第2条(譲渡価格及び支払方法)
1. 本件株式の譲渡価格は、金○○○万円(以下「譲渡価格」という。)とする。
2. 乙は、譲渡価格を以下の方法により甲に支払うものとする。
- (1) 契約締結時に金○○○万円を甲の指定する銀行口座に振り込む方法により支払う。
- (2) 残金○○○万円は、第4条に定める会社の承認及び株主名簿書換手続完了後○日以内に、甲の指定する銀行口座に振り込む方法により支払う。
第3条(株券の不存在と対応)
1. 甲は、本件株式について株券を所持していないことを表明する。
2. 甲及び乙は、本件会社の調査により、以下のいずれかの事実が確認されたことを確認する。
- 【選択肢1】本件会社は株券不発行会社であり、本件株式について株券が発行されていない。
- 【選択肢2】本件会社は株券発行会社であるが、甲は本件株式に係る株券を紛失している。
3. 前項【選択肢2】の場合、甲は本契約締結後速やかに株券失効手続を開始し、除権判決取得後、本件会社に対して新株券の発行を請求し、発行された新株券を直ちに乙に引き渡すものとする。
4. 本契約に基づく株式譲渡の効力は本契約締結時に発生するが、乙が本件会社及び第三者に対して株主としての権利を対抗するためには、株主名簿の書換が必要であることを甲乙双方は了解する。
第4条(譲渡承認手続)
1. 甲は、本契約締結後速やかに本件会社に対して本件株式の譲渡承認請求を行うものとする。
2. 乙は、前項の譲渡承認請求に関し、本件会社から求められる資料の提出など、必要な協力を行うものとする。
3. 本件会社が本件株式の譲渡を承認しない場合、甲及び乙は誠実に協議し、本契約の取扱いを決定するものとする。
第5条(株主名簿の書換)
1. 甲及び乙は、本件会社による譲渡承認後、速やかに本件会社に対して株主名簿の書換請求を行うものとする。
2. 前項の書換請求に必要な書類の準備及び費用は、乙の負担とする。
第6条(表明及び保証)
1. 甲は、本件株式について以下の事項を表明し保証する。
- (1) 甲が本件株式の適法かつ完全な所有者であること
- (2) 本件株式について、質権その他いかなる担保権も設定されていないこと
- (3) 本件株式について、第三者に対して譲渡、売却その他の処分を行う義務を負っていないこと
- (4) 本件株式に係る株券を紛失した場合であっても、当該株券を第三者に譲渡していないこと
2. 前項の表明保証に反する事実が判明した場合、甲は乙に対して生じた一切の損害を賠償するものとする。
第7条(契約不履行)
甲または乙が本契約に定める義務を履行しない場合、相手方は相当の期間を定めて催告のうえ、本契約を解除することができる。この場合、契約不履行により生じた損害の賠償を請求することを妨げない。
第8条(秘密保持)
甲及び乙は、本契約の内容及び本契約に関連して知り得た相手方の情報を、相手方の事前の書面による承諾なくして第三者に開示してはならない。ただし、法令により開示が義務付けられている場合を除く。
第9条(管轄裁判所)
本契約に関して紛争が生じた場合は、○○地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
第10条(協議事項)
本契約に定めのない事項又は本契約の解釈に疑義が生じた場合は、甲乙誠意をもって協議し解決するものとする。
本契約締結の証として本書2通を作成し、甲乙記名押印のうえ、各1通を保有する。
令和○年○月○日
甲(譲渡人)
住所:○○県○○市○○町○丁目○番○号
氏名:○○○○ 印
乙(譲受人)
住所:○○県○○市○○町○丁目○番○号
氏名:△△△△ 印
よくある質問(Q&A)
株式譲渡と株券紛失に関するQ&A
Q1: 株券が見当たらないのですが、会社に株券発行の有無を確認する方法はありますか?
A: 株券発行の有無は以下の方法で確認できます:
- 会社の代表取締役や総務担当者に直接問い合わせる
- 定款を確認する(「株券を発行する」または「株券を発行しない」という条項を探す)
- 株主名簿を確認する(株券番号の記載があれば株券が発行されている証拠となる)
- 会社の登記事項証明書で会社の設立時期を確認する(2006年5月以降に設立された会社は原則として株券不発行)
最も確実なのは会社への直接問い合わせですが、会社と株主の関係が良好でない場合は、弁護士や司法書士などの専門家を通じて確認するとよいでしょう。
Q2: 株券不発行会社の場合、株式譲渡の証拠として何を残しておくべきですか?
A: 株券不発行会社の場合、以下の書類を証拠として保管しておくことをお勧めします:
- 株式譲渡契約書(原本)
- 譲渡代金の支払証明(振込控えなど)
- 会社の定款のコピー(株券不発行の条項があるもの)
- 譲渡承認書(譲渡制限株式の場合)
- 株主名簿書換請求書のコピー(受付印のあるもの)
- 株主名簿記載事項証明書(取得できる場合)
特に重要なのは株式譲渡契約書と譲渡代金の支払証明です。これらは譲渡の事実を証明する最も基本的な証拠となります。また、可能であれば契約書は公正証書として作成することも検討しましょう。
Q3: 株券失効手続きはどのくらい時間と費用がかかりますか?
A: 株券失効手続き(公示催告と除権判決)には、一般的に以下の時間と費用がかかります:
- 時間:通常3〜6ヶ月程度(裁判所の状況によって異なる)
- 費用:
- 申立手数料:5,000円程度
- 公告費用:5,000円〜10,000円程度
- 弁護士・司法書士に依頼する場合の報酬:5万円〜10万円程度
手続きは専門的で煩雑なため、弁護士や司法書士に依頼することをお勧めします。なお、株式の価値が低い場合や、定款変更により株券を不発行とする方法が取れる場合は、費用対効果を考慮して別の方法を検討した方がよい場合もあります。
Q4: 会社が譲渡承認を不当に拒否している場合、どうすればよいですか?
A: 譲渡制限株式の譲渡について会社が不当に承認を拒否している場合、以下の対応が考えられます:
- 再度の交渉:拒否理由を確認し、懸念点に対応した提案を行う
- 株主総会での検討:取締役会決議ではなく株主総会での検討を求める
- 裁判所への許可申立て:会社法第145条に基づき、裁判所に対して「株式譲渡許可の申立て」を行う(いわゆる「借地非訟」の手続き)
- 買取請求:会社または会社指定の第三者に対して、株式の買取りを請求する
不当な承認拒否の場合、裁判所は譲渡を許可する可能性が高いですが、手続きには時間と費用がかかります。そのため、まずは交渉による解決を試みることをお勧めします。この問題は専門的なため、弁護士に相談することが望ましいでしょう。
Q5: 株主名簿の書換えを会社が拒否した場合はどうすればよいですか?
A: 会社が正当な理由なく株主名簿の書換えを拒否した場合、以下の対応が考えられます:
- 書面による請求:内容証明郵便などで正式に書換請求を行う
- 取締役への個別交渉:取締役に直接会って事情を説明する
- 仮処分の申立て:裁判所に対して株主名簿書換の仮処分を申し立てる
- 訴訟の提起:株主名簿書換請求訴訟を提起する
特に譲渡制限株式の場合、会社の承認を得ていることを証明できれば、会社は正当な理由なく書換えを拒否できません。書換えが拒否された場合は、早めに弁護士に相談し、法的手段を検討することをお勧めします。なお、株主としての権利行使(配当の受領、株主総会での議決権行使など)には、基本的に株主名簿の記載が必要となるため、書換えは重要な手続きです。
まとめ
株式譲渡契約書は、株式の譲渡における重要な書類であり、特に譲渡制限株式の場合には、適切な手続きを踏むことが求められます。株券が見当たらない場合でも、適切な手続きを行うことで、株式の譲渡をスムーズに進めることができます。専門家の助言を得ながら、適切な手続きを行いましょう。
株券が見当たらない場合の株式譲渡の流れ
Step 1: 株券発行の確認
- 会社への問い合わせ
- 定款の確認
- 株主名簿の確認
- 設立時期の確認
Step 2: 株券紛失への対応
- 株券不発行の場合:そのまま手続き
- 株券発行の場合:株券失効手続き
- または定款変更による対応
- または株主全員の合意による対応
Step 3: 譲渡手続き
- 株式譲渡契約書の作成・締結
- 譲渡承認の取得(制限株式の場合)
- 株主名簿の書換請求
- 必要書類の提出
Step 4: 証拠の保管
- 株式譲渡契約書の保管
- 支払証明の保管
- 承認書の保管
- 書換請求書のコピー保管
株式譲渡に関する法的サポート
株式譲渡、特に株券が見当たらない場合の手続きは複雑で専門的な知識が必要です。当事務所では、株式譲渡に関する以下のようなサポートを提供しております:
- 株式譲渡契約書の作成・確認
- 株券不在時の対応策の提案
- 株券失効手続きのサポート
- 譲渡承認手続きのアドバイス
- 株主名簿書換請求のサポート
- 株式譲渡に関する税務相談
株式譲渡をスムーズに進め、将来のトラブルを防止するためには、専門家のアドバイスが重要です。株式譲渡についてのご相談は、初回相談無料で承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。
■■□―――――――――――――――――――□■■
司法書士・行政書士和田正俊事務所
【住所】 〒520-2134 滋賀県大津市瀬田5丁目33番4号
【電話番号】 077-574-7772
【営業時間】 9:00~17:00
【定休日】 日・土・祝
■■□―――――――――――――――――――□■■
法人・会社に関連する記事
【ケーススタディ】大津市で新年に起業した社長の14日間|会社設立から営業開始まで密着レポート
2026年1月12日
【2026年最新】滋賀県で起業する完全ガイド|会社設立の手続きと費用を司法書士が徹底解説
2026年1月5日
事業目的を追加・変更する登記。費用と期間、必要書類
2025年11月20日