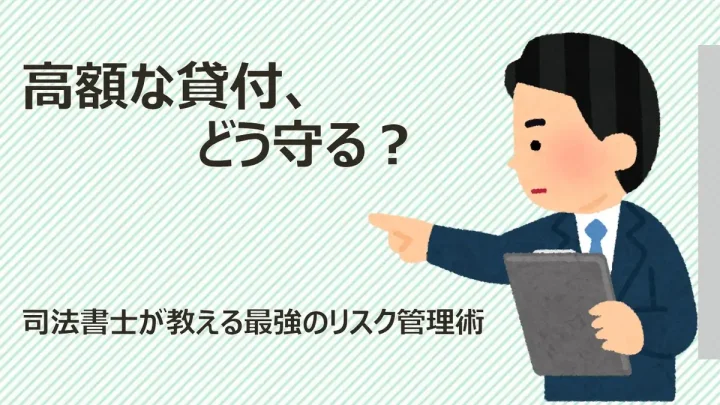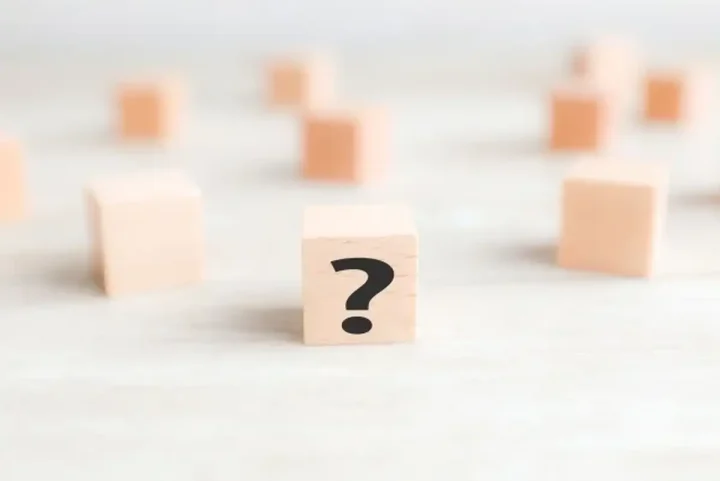所在不明共有者問題の解決策:裁判所の手続きで不動産持分を取得・譲渡する方法
不動産を誰かと共有している場合、共有者の所在が分からなくなると、不動産の売却や管理が進められず、大きな問題となります。しかし、2023年に施行された民法改正により、裁判所を通じて所在不明共有者の持分を取得したり、第三者に譲渡したりする新たな制度が整備されました。この記事では、所在等不明共有者に関する裁判所の手続きについて、分かりやすく解説します。
本記事のポイント:
- 不動産共有者の所在不明は、売却・管理・相続などの場面で大きな障害となる
- 民法第258条から第262条の3に基づく裁判所への申立てで解決可能
- 「持分の取得の裁判」で自分が所在不明共有者の持分を買い取る方法
- 「持分の譲渡権限の付与の裁判」で第三者への譲渡を実現する方法
- いずれの場合も供託金の支払いなど適切な補償措置が必要
所在等不明共有者とは?
「所在等不明共有者」とは、以下のいずれかに該当する共有者のことを指します:
- 所在不明共有者:共有者の所在が知れない場合
- 連絡不能共有者:共有者は知っているが、合理的な努力を払っても連絡がつかない場合
- 法人でない社団等の構成員不明共有者:法人格のない団体の構成員の所在が不明な場合
このような状況では、共有物の管理や処分に関する合意形成が困難になり、不動産の有効活用が阻害されます。特に、相続による共有状態が複雑化するケースや、古い共有名義の不動産で共有者との連絡が途絶えているケースなどが典型的な問題事例です。
民法改正による新制度の導入
2023年4月に施行された民法等の一部を改正する法律により、所在等不明共有者の持分を取得・譲渡するための新たな制度が導入されました。この改正は、増加する所有者不明土地問題への対応や不動産の利活用促進を目的としたものです。
改正前は所在不明共有者がいる場合、基本的に不動産の処分ができませんでしたが、改正後は裁判所の関与のもと、一定の条件を満たせば処分が可能になりました。
所在等不明共有者の持分を取得する手続き
STEP 1: 持分取得の裁判を申し立てる
他の共有者の持分を自分が取得したい場合、裁判所に「持分の取得の裁判」を申し立てます。申立ては不動産の所在地を管轄する地方裁判所で行います。申立書には、不動産の特定情報、共有者の持分、所在等不明共有者の情報、所在不明の事情などを記載します。
STEP 2: 裁判所による審理
裁判所は申立ての内容を審理し、要件を満たしていると判断した場合、申立人に対して「供託命令」を出します。この命令では、所在等不明共有者のために一定の金銭を供託所に供託するよう指示されます(非訟事件手続法第87条第5項)。
STEP 3: 供託金の支払い
裁判所が定めた供託金を指定された供託所に支払い、その旨を裁判所に届け出ます。この供託金額は通常、不動産の時価を基準に所在等不明共有者の持分に応じて算定されます。供託命令に従わない場合、申立ては却下されます(同条第8項)。
STEP 4: 裁判の確定と登記手続き
裁判が確定すると、所在等不明共有者の持分は申立人に移転します。この裁判の確定を待って、法務局で所有権移転登記を行います。登記申請には裁判の謄本などが必要です。
供託金の額
裁判所は、不動産の時価、所在等不明共有者の持分割合、管理費用の負担状況などを考慮して供託金額を決定します。通常は不動産鑑定士による鑑定評価や固定資産税評価額などを参考に算定されます。
所在等不明共有者の供託金還付請求
所在等不明共有者は、持分の取得の裁判が確定した後、供託所に対して供託金の還付を請求できます。その際は、自身が所在等不明共有者と同一人であることや裁判が確定したことを証明する書類を提出する必要があります。
所在等不明共有者の持分を第三者に譲渡する手続き
自分が所在等不明共有者の持分を取得するのではなく、第三者に譲渡したい場合は、「持分の譲渡権限の付与の裁判」の手続きを利用します。
持分譲渡権限の付与の裁判の特徴
この裁判では、裁判所が申立人に「所在等不明共有者の持分を第三者に譲渡する権限」を付与します。この権限付与には条件があり、「当該他の共有者以外の共有者の全員が特定の者に対してその有する持分の全部を譲渡すること」が停止条件となります(民法第262条の3第1項)。
つまり、共有者全員(所在等不明共有者を除く)が同じ買主に持分を売却することが条件となります。
STEP 1: 譲渡権限付与の裁判を申し立てる
不動産の所在地を管轄する地方裁判所に申立てを行います。申立書には、不動産の特定情報、共有者の持分、所在等不明共有者の情報、譲渡先となる第三者の情報などを記載します。
STEP 2: 裁判所による審理と供託命令
持分取得の裁判と同様に、裁判所は審理を行い、供託命令を出します。供託金額は、不動産の時価に所在等不明共有者の持分割合を乗じた額が基準となります。
STEP 3: 権限付与の裁判確定後、第三者への譲渡
裁判が確定すると、申立人は所在等不明共有者の持分を特定の第三者に譲渡する権限を得ます。譲渡契約の締結や登記手続きを行い、持分を第三者に移転します。
STEP 4: 所在等不明共有者への対価支払い
所在等不明共有者が現れた場合、譲渡をした共有者は、不動産の時価相当額を所在等不明共有者の持分に応じて按分した金額を支払う義務があります(民法第262条の3第3項)。また、所在等不明共有者は供託金の還付を請求することもできます。
申立て前に確認すべきこと
裁判所への申立てを行う前に、以下の点を確認しておくことが重要です:
所在等不明の確認
共有者が本当に所在不明か、連絡不能かを確認するため、以下の調査を行います:
- 住民票や戸籍の調査
- 最後の住所への郵便(内容証明など)
- 親族や知人への照会
- インターネットや SNS での検索
裁判所は「所在等不明」の要件を厳格に審査するため、調査記録や証拠を残しておくことが重要です。
不動産の評価
供託金額の基準となる不動産の時価を把握するため、以下の資料を準備しておきます:
- 不動産鑑定評価書
- 固定資産税評価証明書
- 周辺の取引事例資料
- 不動産会社による査定書
裁判所が適切な供託金額を決定できるよう、客観的な評価資料を提出することが重要です。
まとめ:専門家の支援を受けて解決を
不動産の共有者が所在不明になった場合、民法の新制度を活用することで、持分の取得や譲渡が可能になりました。この制度は、不動産の有効活用や権利関係の整理に大きく貢献します。特に次のようなケースで効果的です:
- 相続で生じた複雑な共有状態の解消
- 長年放置された共有不動産の活用
- 開発や売却を進めたい共有不動産の権利関係整理
ただし、裁判所への申立てや供託手続きは専門的な知識を要するため、司法書士や弁護士などの専門家に相談することをお勧めします。適切な手続きを踏むことで、不動産に関する悩みを解決し、資産の有効活用を図ることができます。
所在不明共有者問題でお困りの方へ
不動産の共有者が所在不明でお困りの方は、当事務所にご相談ください。民法改正による新制度を活用した解決策をご提案いたします。裁判所への申立て手続きや必要書類の準備、登記手続きまで一貫してサポートいたします。
司法書士・行政書士和田正俊事務所
住所:〒520-2134 滋賀県大津市瀬田5丁目33番4号
電話番号:077-574-7772
営業時間:9:00~17:00
定休日:日・土・祝
不動産に関連する記事
【司法書士が徹底解説】個人間の高額融資で絶対に失敗しない!不動産担保(抵当権・譲渡担保)活用の完全ガイド
2025年12月17日
法改正で必須に!登記はメールアドレスで速く
2025年11月10日
司法書士による本人確認手続きの流れと実務のQ&A
2025年12月7日