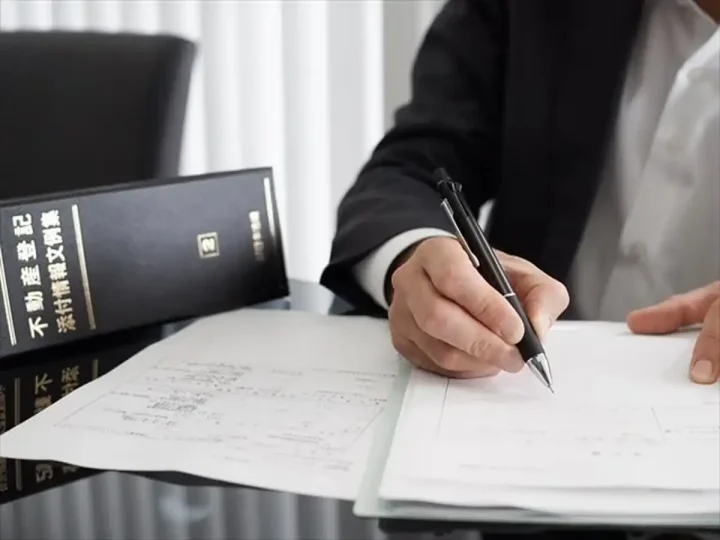最終更新日:2025年11月27日
所有者不明土地(建物)管理命令に伴う供託事務の新ガイドライン
2023年6月30日、所有者不明土地(建物)管理命令に関する供託事務の取扱いについてのガイドラインが発表されました。このガイドラインは、所有者やその所在が不明な不動産に対する管理命令に基づく供託手続きの詳細を示すものです。本記事では、この制度の概要から具体的な供託方法、複数不動産の一括管理における注意点まで詳しく解説します。
本記事のポイント:
- 所有者不明土地(建物)管理命令の法的根拠と要件
- 管理命令に基づく供託手続きの具体的方法
- 複数不動産を一括管理する場合の供託の注意点
- 所有者不明不動産の適切な管理による社会的意義
- 管理人による金銭管理と供託の重要性
所有者不明土地(建物)管理命令の概要
所有者不明土地(建物)管理命令は、民法第264条の2及び第264条の8に基づく制度で、平成30年の民法改正により新設され、平成31年4月1日から施行されています。この制度は、所有者を知ることができないまたはその所在が不明な不動産に対して、裁判所が管理人による管理を命じるものです。
この管理命令は、所有者不明の不動産が増加する社会問題に対応するための重要な法的手段です。特に空き家問題や耕作放棄地の増加、災害復興の妨げとなる所有者不明土地など、様々な社会課題の解決に寄与することが期待されています。
管理命令発令の要件
所有者不明土地(建物)管理命令が発せられるためには、以下の要件を満たす必要があります:
- 所有者不明の状態:土地や建物の所有者を知ることができない、またはその所在が不明であること
- 管理の必要性:当該不動産について管理が必要であると裁判所が認めること
- 利害関係人からの請求:利害関係人からの請求があること
利害関係人とは:当該不動産に対して権利を有する者、権利を行使する権限を有する者、直接または間接的に収益を得ている者、または当該不動産から生じる危険によって権利や法的利益が侵害される恐れがある者を指します。
所有者不明土地(建物)管理命令に伴う供託の方法
管理命令が発せられると、裁判所によって選任された管理人は、管理対象となった不動産から生じた金銭(賃料収入や売却代金など)を供託することができます。この供託手続きは、非訟事件手続法第90条第8項及び第90条第16項に準じて行われます。
供託金の目的と供託所の選定
供託する金銭は、管理対象となった不動産の所有者のために供託されます。供託は、不動産の所在地の供託所(法務局または地方法務局)で行います。この選定は、不動産の所在地が明確な場合は容易ですが、複数の不動産が異なる地域に存在する場合は、それぞれの所在地に応じた供託所で手続きを行う必要があります。
供託書の作成と必要記載事項
供託書には、以下の情報を明確に記載する必要があります:
- 不動産の所在地と物件の特定情報(地番、家屋番号など)
- 権利関係の詳細(所有者不明の状況など)
- 管理人の氏名及び住所
- 供託の事由(所有者不明土地管理命令に基づく供託である旨)
- 供託金額及びその内訳(賃料収入、売却代金、管理費用の差引など)
供託書には管理人の印鑑を押印する必要があります。
必要書類の添付と提出
供託書には、裁判所から交付された所有者不明土地(建物)管理命令の写しを添付します。これは、供託の法的根拠を示す重要な書類です。供託書及び管理命令の写しは、原本と写しを各1通ずつ作成し、原本を供託所に提出します。また、手続きの記録として、写しを裁判所に提出します。
供託が受理されると、供託所から「供託書正本」が交付されます。この正本は、管理人が供託手続きを適切に行ったことを証明する重要な書類です。
複数の不動産が一括して管理対象となった場合の供託の注意点
金銭の内訳の明確化
複数の不動産から生じた金銭を一括して供託する際には、それぞれの不動産から生じた金銭及び管理に要した費用(管理人の報酬を含む)の内訳を明確に記載する必要があります。この明確化は、将来所有者が判明した際に、適切に金銭を分配するために重要です。
所有者の同一性の確認
複数の不動産から生じた金銭を一括して供託できるのは、各不動産の所有者が全てまたは一部判明しておらず、かつそれら所有者が同一人である場合に限られます。所有者が異なる場合には、一括供託はできず、それぞれ別個に供託手続きを行う必要があります。
管理費用の配分
複数の不動産を一括管理する場合、管理人の報酬などの共通費用をどのように各不動産に配分するかも重要な検討事項です。公平かつ合理的な配分方法を採用し、供託書にその根拠を明記することが望ましいでしょう。
異なる地域の不動産
管理対象となる不動産が異なる法務局の管轄地域に所在する場合、供託所の選定や手続きが複雑になる可能性があります。このような場合は、事前に供託所に相談し、適切な手続き方法を確認することをお勧めします。
実務上の重要ポイント
所有者不明土地(建物)管理命令に関連する供託手続きを行う際は、以下の点に特に注意が必要です:
- 正確な記録管理:管理人は、不動産から生じた収益や支出した管理費用について、詳細かつ正確な記録を保管しておく必要があります。
- 定期的な報告:管理人は、裁判所に対して定期的に管理状況を報告することが求められます。供託を行った場合も、その内容を報告書に記載することが重要です。
- 専門家との連携:複雑な案件では、司法書士や弁護士などの専門家と連携し、適切な手続きを行うことが推奨されます。
- 供託金の払戻し:所有者が判明した場合の供託金の払戻し手続きについても、あらかじめ理解しておくことが重要です。
所有者不明土地(建物)管理命令の意義と影響
所有者不明土地(建物)管理命令制度は、増加する所有者不明不動産問題に対応するための重要な法的枠組みです。この制度が持つ社会的意義と影響は以下の通りです:
- 適切な管理の実現:管理不全による周辺環境への悪影響や安全上の問題を防止します。
- 地域開発の促進:所有者不明不動産が地域開発の障害となるケースが多い中、この制度により適切な管理と利用が可能になります。
- 権利関係の明確化:管理命令の過程で権利関係の調査が行われ、不明確だった権利関係が明らかになることもあります。
- 資産の保全:供託制度を通じて、不動産から生じた金銭を安全に保管し、所有者が判明した際に適切に引き渡すことができます。
- 社会的コストの削減:放置された不動産による社会的コスト(治安悪化、景観毀損など)を減少させる効果があります。
まとめ
所有者不明土地(建物)管理命令に伴う供託事務の取扱いは、所有者不明不動産問題に対応するための重要な法的手続きです。管理人は、不動産から生じた金銭を適切に供託することで、将来所有者が判明した際の権利保全を図るとともに、透明性の高い管理を実現することができます。
特に、複数の不動産を一括管理する場合には、金銭の内訳の明確化や所有者の同一性の確認など、細心の注意を払った手続きが求められます。この制度の適切な運用により、所有者不明不動産の適正管理が進み、地域社会の健全な発展に寄与することが期待されます。
相続・不動産に関するお悩みは専門家へ
所有者不明土地問題や相続手続き、不動産登記に関するご相談は、当事務所までお気軽にお問い合わせください。滋賀県大津市を中心に、相続・遺言・不動産登記などの法律手続きを専門的にサポートしています。
司法書士・行政書士和田正俊事務所
住所:〒520-2134 滋賀県大津市瀬田5丁目33番4号
電話番号:077-574-7772
営業時間:9:00~17:00
定休日:日・土・祝
🌟 わずか10秒!あなたのその悩み、LINEで即解決しませんか?
相続や登記、会社設立の疑問を抱えたまま、重い腰を上げる必要はありません。
当事務所では、ご多忙な皆様のためにLINE公式アカウントを開設しています。
✅ 【手軽】 氏名や住所の入力は不要。匿名で相談OK!
✅ 【迅速】 お問い合わせから最短5分で司法書士に直接つながります。
✅ 【無料】 もちろん、初回のLINE相談は完全無料です。
▼ 今すぐLINEで友だち追加して、相談を開始!
◇ 当サイトの情報は執筆当時の法令に基づく一般論であり、個別の事案には直接適用できません。
◇ 法律や情報は更新されることがあるため、専門家の確認を推奨します。
◇ 当事務所は情報の正確性を保証せず、損害が生じた場合も責任を負いません。
◇ 情報やURLは予告なく変更・削除されることがあるため、必要に応じて他の情報源もご活用ください。
この記事を書いた人

司法書士・行政書士 和田正俊事務所 代表和田 正俊(Wada Masatoshi)
- 滋賀県司法書士会所属 登録番号 滋賀第441号
- 簡裁訴訟代理関係業務 認定番号 第1112169号
- 滋賀県行政書士会所属
登録番号 第13251836号会員番号 第1220号 - 公益社団法人 成年後見センター・リーガルサポート滋賀支部所属
会員番号 第6509213号
後見人候補者名簿 及び 後見監督人候補者名簿 搭載 - 法テラス契約司法書士
- 近畿司法書士会連合会災害相談員
法改正・時事情報に関連する記事
令和8年4月施行・住所変更登記の義務化とは?~改正不動産登記法のポイントと実務対応~
2025年12月4日
【2025年改正解説】供託金払渡し時の印鑑証明書添付義務が緩和されました
2025年12月3日
紙からデジタルへ!「電子署名」は実印を超える?法的有効性と司法書士が使う電子証明書
2025年12月15日