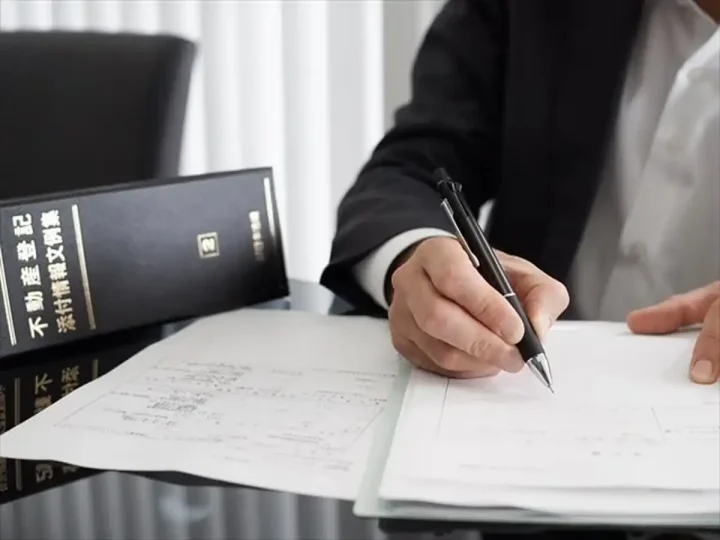遺言書保管制度の指定者通知が拡大:2023年10月から最大3名まで指定可能に
日本司法書士会連合会から重要な通知がありました。遺言書保管制度における「指定者通知」の運用が2023年10月2日(月)から大きく変更されます。これまで1名のみに限定されていた通知先が最大3名まで指定できるようになり、さらに通知先の範囲も拡大されます。この変更は遺言者の意思をより確実に実現するための重要な改善点となります。
改正のポイント:
- 指定者通知の人数が1名から最大3名に拡大
- 指定できる対象者の範囲制限が撤廃
- 施行日は2023年10月2日(月)から
- 遺言の存在を確実に伝達できる可能性が向上
- 遺言執行の円滑化と相続トラブル防止に貢献
遺言書保管制度とは
遺言書保管制度は、2020年7月にスタートした比較的新しい制度で、自筆証書遺言を法務局で保管してもらえるサービスです。この制度には以下のようなメリットがあります:
- 遺言書の紛失防止:自宅での保管より安全に保管できます
- 改ざん防止:法務局で原本を保管するため、内容の書き換えができません
- 検認不要:家庭裁判所での検認手続きが不要となり、相続手続きが迅速に進みます
- 方式違反の減少:法務局が形式的なチェックを行うため、無効になるリスクが低減します
この制度を利用すると、遺言者が亡くなった後、相続人等が法務局から遺言書の内容を正確に確認できるため、遺言者の最終意思を確実に実現することができます。
指定者通知とは
「指定者通知」とは、遺言者が法務局に申出をしておくことで、遺言者の死亡後に、法務局が指定された人に対して「遺言書が保管されている」という事実を通知する制度です。この通知により、遺言の存在を知らなかった相続人等に確実に情報が伝わり、遺言の内容に沿った相続手続きが進められるようになります。
指定者通知の変更内容
変更前(現行制度)
現在の制度では、指定者通知の対象として指定できるのは以下の条件に限定されています:
- 遺言者の推定相続人、受遺者、遺言執行者のうち1名のみ
この制限により、指定した1名が何らかの理由で通知を受け取れない場合や、通知を受け取っても他の関係者に伝えない場合などに、遺言の存在が適切に伝わらないリスクがありました。
変更後(2023年10月2日〜)
新制度では、指定者通知の対象が大幅に拡大されます:
- 対象者の範囲制限が撤廃(推定相続人等に限定されない)
- 最大3名まで指定可能
これにより、遺言者は信頼できる友人や専門家(弁護士、司法書士など)も含めて指定することができ、複数の人に通知することで遺言の存在を確実に伝えることができるようになります。
指定者通知拡大のメリット
遺言者の意思実現の確実性向上
複数の人に通知することで、遺言の存在を知らせる確率が高まり、遺言者の最終意思が確実に実現される可能性が向上します。
相続トラブルの防止
遺言の存在を複数の関係者が知ることで、一部の相続人だけが遺言の内容を秘匿するといった問題を防ぎ、公平で透明な相続手続きが期待できます。
専門家への通知が可能に
弁護士や司法書士などの専門家を指定者に含めることで、相続手続きの円滑な進行を期待できます。専門家は適切なアドバイスや手続き支援を提供できます。
柔軟な指定が可能に
推定相続人等に限らず、遺言者が信頼する人を指定できるようになるため、家族関係が複雑な場合や、特定の相続人と疎遠な場合でも適切な人選が可能になります。
活用例
指定者通知の拡大を活用できる具体的なケース:
- 遠方に住む相続人がいる場合:地元に住む相続人と、遠方に住む相続人の両方を指定
- 相続人同士の関係が良くない場合:各グループから1名ずつと、中立的な立場の専門家を指定
- 相続手続きを特定の専門家に依頼したい場合:信頼できる司法書士等の専門家を含めて指定
- 相続人がいない場合:受遺者や信頼できる友人、福祉施設の関係者等を指定
遺言書保管制度の利用方法
遺言書保管制度を利用するには、以下の手順で手続きを行います:
STEP 1: 自筆証書遺言の作成
法務局保管用の自筆証書遺言を作成します。財産目録については、パソコンで作成したものや通帳のコピーなどを添付することも可能です(ただし表紙と日付・氏名は自署が必要)。
STEP 2: 予約
最寄りの法務局(遺言書保管所)に予約をします。本人確認書類や印鑑(認印可)を準備しましょう。
STEP 3: 法務局での手続き
法務局で申請書を記入し、遺言書を提出します。この際、指定者通知を希望する場合は、指定者の氏名・住所等の情報を提供します。手数料(3,900円)を納付します。
STEP 4: 保管証の受領
手続き完了後、「遺言書保管証」が交付されます。この保管証は大切に保管し、相続人等に保管場所を知らせておくことをお勧めします。
なお、すでに遺言書保管制度を利用している方で、指定者通知の変更を希望する場合は、10月2日以降に法務局で手続きを行うことができます。その際には、遺言書保管証が必要となりますので、ご注意ください。
まとめ
指定者通知の拡大は、遺言書保管制度の利便性と有効性を大きく向上させる重要な変更です。遺言者の意思をより確実に実現するための環境が整備されることで、相続トラブルの防止や円滑な相続手続きの促進が期待されます。
遺言の作成や相続に関する不安や疑問がある方は、ぜひ専門家にご相談ください。司法書士は遺言作成のサポートから遺言書保管制度の利用手続き、さらには相続手続き全般まで、幅広くサポートいたします。
詳細な情報は法務省のホームページでも確認できます:法務省:遺言書保管制度
遺言・相続のご相談
遺言書の作成や遺言書保管制度の利用方法、相続手続き全般についてのご相談は当事務所にお気軽にお問い合わせください。専門的な視点から、あなたの状況に最適なアドバイスを提供いたします。
司法書士・行政書士和田正俊事務所
住所:〒520-2134 滋賀県大津市瀬田5丁目33番4号
電話番号:077-574-7772
営業時間:9:00~17:00
定休日:日・土・祝
法改正・時事情報に関連する記事
令和8年4月施行・住所変更登記の義務化とは?~改正不動産登記法のポイントと実務対応~
2025年12月4日
【2025年改正解説】供託金払渡し時の印鑑証明書添付義務が緩和されました
2025年12月3日
紙からデジタルへ!「電子署名」は実印を超える?法的有効性と司法書士が使う電子証明書
2025年12月15日