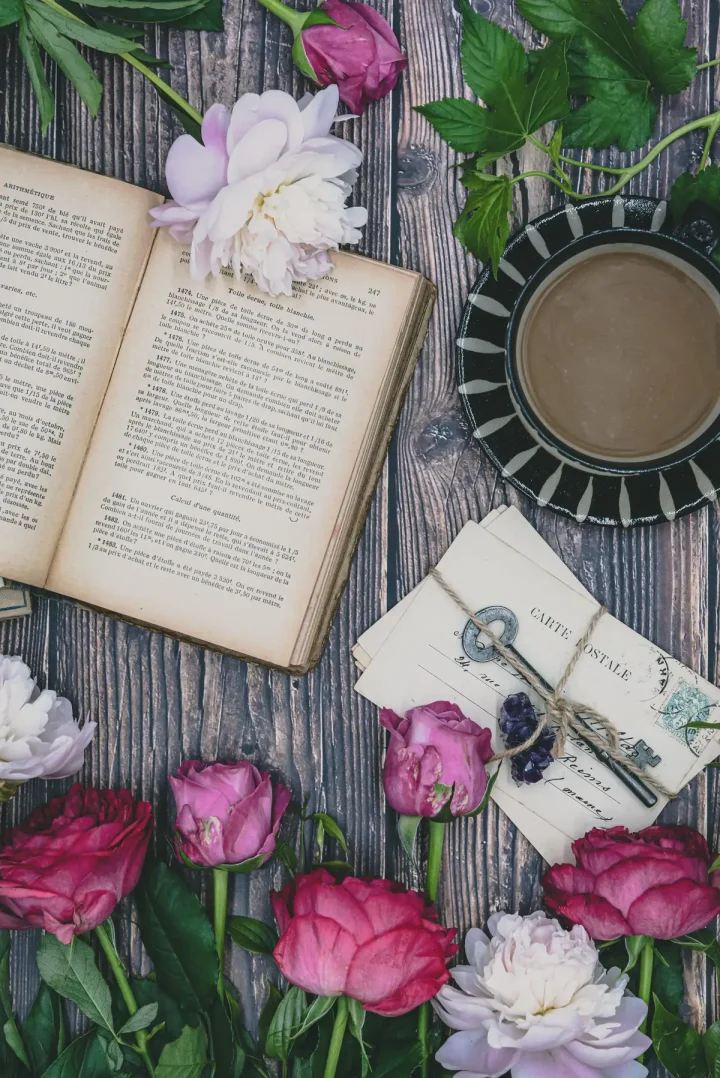2025年1月13日
不動産不動産登記を司法書士に依頼するメリットは?所有権を守る法的保護と手続きの全貌
不動産を購入したら登記はなぜ必要?第三者対抗要件や抵当権確認など、登記簿の役割を解説。煩雑な手続きを司法書士に代行依頼するメリットもご紹介します。
2024年12月17日
不動産抵当権抹消の「弁済」と「解除」についての完全ガイド
住宅ローン完済後の抵当権抹消には「弁済」と「解除」という2つの原因があります。銀行直接型は金銭消費貸借契約の終了による「弁済」、保証会社介入型は保証委託契約の終了による「解除」が適切です。抹消手続きは法務局での申請書入手、書類準備、登録免許税の印紙の用意、提出という流れで進みますが、複雑な場合は司法書士に依頼するのが安心です。
2024年6月21日
不動産日本における農地の貸借手続きの一本化とその重要性
日本の農業経営基盤強化のため、令和7年4月から農地貸借手続きが一本化されます。農地中間管理機構(農地バンク)を介した新制度では、分散錯圃の解消や経営規模拡大が期待されます。貸し手は安定した賃料収入と相続時の安心を得られ、借り手は集約された農地で効率的な農業が可能に。司法書士などの専門家も、農地相談時にこの新制度を紹介し、持続可能な日本農業の実現をサポートします。