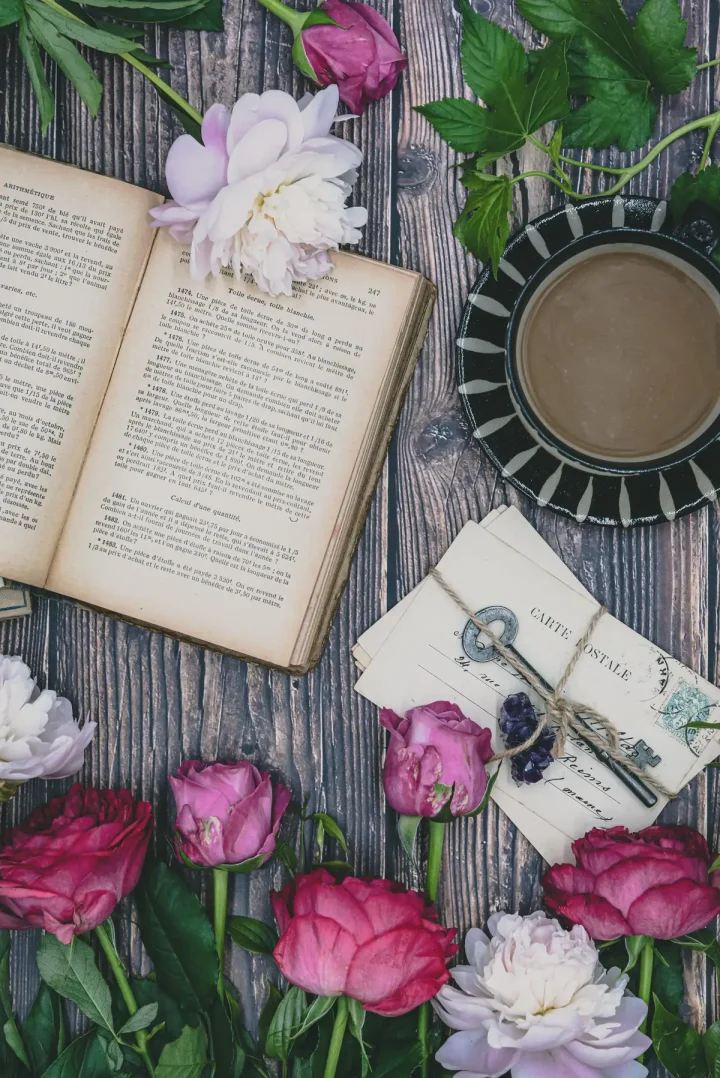2025年1月14日
法人・会社会社設立時に知っておくべき法的手続き
会社設立は1ヶ月で可能!登記専門家が、定款認証から法務局への申請まで、法的な専門知識が必要な手続きを解説。電子定款を利用し印紙代を節約する方法やサポート内容も紹介します。
2025年1月13日
不動産不動産登記を司法書士に依頼するメリットは?所有権を守る法的保護と手続きの全貌
不動産を購入したら登記はなぜ必要?第三者対抗要件や抵当権確認など、登記簿の役割を解説。煩雑な手続きを司法書士に代行依頼するメリットもご紹介します。
2025年1月12日
相続・財産管理相続手続きの基本とよくある質問:司法書士が解説する安心のガイド
相続は6ステップの法的手続きで、死亡届提出から名義変更完了まで専門知識が必要です。遺産分割協議では全相続人の合意形成が重要で、相続税申告は10ヶ月以内という期限があります。司法書士は戸籍収集から不動産登記まで一貫してサポートし、トラブル予防と手続き効率化を実現。複雑な相続も専門家の助けで安心して進められます。
2025年1月11日
事務所からのお知らせ司法書士の新人研修で学ぶ「相談」の重要性とその技法
法的知識だけでなく「聴く力」も求められる司法書士。本記事では、「聞く・訊く・聴く」の違い、相談者の心理的不安を軽減する環境づくり、適切な質問技法など、新人研修で学ぶ相談対応の核心を解説。相談者がリラックスして話せる雰囲気作りから、専門用語を避けた分かりやすい法的アドバイスまで、信頼される司法書士になるための実践的知識を提供します。
2025年1月10日
法改正・時事情報女性に対する暴力をなくす運動
「女性に対する暴力をなくす運動」が11月12日から25日まで全国で実施されました。内閣府や警察庁など政府機関が主唱し、地方自治体や関係団体と連携したこの運動では、広報活動の強化、啓発イベントの開催、相談窓口の周知、防犯指導の強化、犯罪行為の取締り強化という5つの重点項目に取り組み、女性に対する暴力の根絶を目指しています。
2025年1月9日
相続・財産管理期限内に相続登記をすることが難しい方へ 相続人申告登記
相続登記義務化に対応する新制度「相続人申告登記」は、相続人全員の同意不要で手続き可能な画期的システムです。7ステップの簡易手続きで義務を履行でき、罰則を回避できます。不動産の権利移転は行われないため将来的には通常の相続登記が必要ですが、期限内に義務を果たす応急措置として最適な選択肢となります。
2025年1月8日
事務所からのお知らせ消費者相談の現状と司法書士の役割
20年間増加し続ける消費者相談。令和5年には90.9万件に達し、平均契約額83万円、平均既支払額44.3万円という実態が明らかになりました。本記事では迷惑メールや架空請求など多発するトラブルの現状と、契約内容確認から法的手続き代理まで司法書士が提供できる具体的支援を解説。消費者被害を未然に防ぐための実践的アドバイスも提供します。
2025年1月7日
成年後見・権利擁護成年後見制度の基本 あなたの権利を守るために知っておくべきこと
成年後見制度は高齢者や障害者の権利擁護と生活支援のための制度であり、専門職には高い倫理が求められます。後見業務は心(倫理・使命感)、技(知識・行動指針)、体(体力・事務所体制)の三要素で支えられ、被後見人の意思決定支援と最善の利益追求が基本です。司法書士は本人との信頼関係構築、適切な代理権行使、利益相反回避などを通じて、被後見人の尊厳ある生活を支えます。
2025年1月6日
成年後見・権利擁護成年後見(保佐制度と補助制度)の重要性と役割
成年後見制度の中でも中間的支援である保佐・補助制度は、本人の判断能力に応じた適切な支援を提供します。保佐人は重要な財産行為への同意・取消権を持ち、補助人は特定の法律行為に限定された権限を有します。両制度とも本人の自己決定権を尊重しながら必要な支援を行い、家庭裁判所の監督下で適切に運用されます。本人の状況に合わせた制度選択が、権利と利益を最大限に保護する鍵となります。
2025年1月5日
事務所からのお知らせリーガルサポートの役割と活動
判断能力が不十分な方の権利を守るために活動するリーガルサポート。本記事では、後見人としての業務をサポートする体制や、就任・業務遂行・終了という各段階での報告義務の意義を詳説します。また、財産調査や目録作成、金融機関への届出、財産の分別管理など、後見人として実践すべき重要な業務手続きについても解説し、被後見人の最善の利益を守るための指針を提供します。
2025年1月4日
相続・財産管理長期相続登記等未了土地解消作業について
所有者不明土地問題を解消する「長期相続登記等未了土地解消作業」は、公共事業の遅延防止を目的とした法務局の重要施策です。登記名義人死亡後10年超の未相続土地を対象に、司法書士協会等が相続人調査を実施。調査結果は法定相続人情報として保管され、対象地には付記登記がされます。土地の適正利用を促進し、相続手続きの負担軽減にも寄与する社会的意義の高い取り組みです。
2025年1月3日
相続・財産管理長期相続登記等未了土地解消作業と法定相続人情報の提供
所有者不明土地問題解決のため、法務局は相続登記未了土地の法定相続人情報を提供するサービスを開始しました。本人確認後に無料で情報を入手でき、戸籍謄本収集の手間を省くことが可能です。書面交付は窓口・郵送両方に対応し、相続登記促進と土地の適正管理につながる公益性の高いサービス。地域発展と公共事業推進の基盤となります。